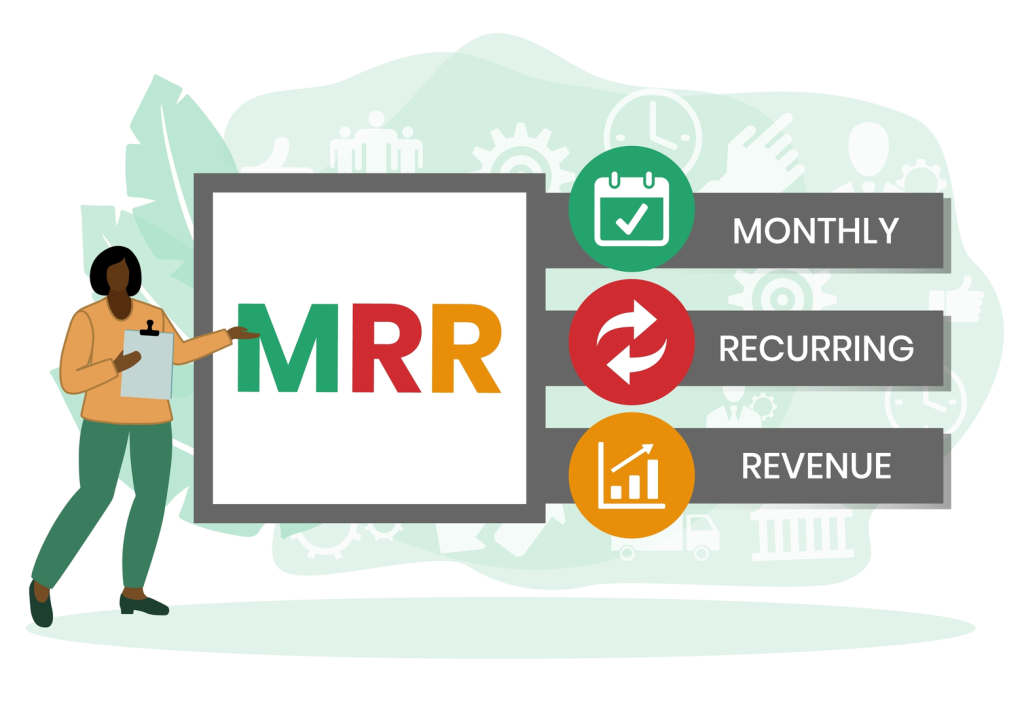営業効率を高める手法として注目を集める「インサイドセールス」。
しかし、いざ導入しようとすると「内製化すべきか、外注すべきか分からない」と悩む企業も少なくありません。
本記事では、インサイドセールスの内製と外注それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較し、どのような企業にどの方法が向いているのかを分かりやすく解説します。
さらに、実績豊富なおすすめ代行企業も紹介しますので、自社に最適な運用体制を検討する際の参考にしてください。
この記事の内容
インサイドセールスとは
インサイドセールスとは、電話・メール・オンライン商談ツールを活用し、非対面で顧客とコミュニケーションを取る営業手法です。
訪問営業のように移動時間が発生せず、効率的に商談を創出できることから、BtoB企業を中心に急速に普及しています。
主な役割は「見込み顧客の育成(ナーチャリング)」と「商談化」です。
マーケティングで獲得したリードに対し、課題のヒアリングや情報提供を行い、購買意欲が高まったタイミングで営業担当に引き継ぎます。
インサイドセールスの引き継ぎ先となるのが、対面での商談やクロージングを担当する「フィールドセールス」です。
両者は連携して営業活動を進める関係にあり、インサイドセールスが「商談の質を高める準備」を担い、フィールドセールスが「契約を獲得する最終工程」を担う構造です。
また、CRMやSFAなどのツールを活用すれば、顧客データを一元管理でき、再現性の高い営業活動が可能になります。
営業効率を改善し、組織全体の生産性を高めたい企業にとって欠かせない仕組みといえるでしょう。
関連記事:インサイドセールスとは?概要やメリット、おすすめツールをわかりやすく解説!
インサイドセールスの運用体制
インサイドセールスの運用体制は主に「内製化」「外注」「ハイブリッド型」に分かれます。企業の規模やリソース、目指すスピード感によって最適な体制は異なります。
内製化
自社内でチームを構築し、運用まで行う方法です。
自社の製品やサービスを深く理解した担当者が対応するため、提案内容の精度が高くなりやすい点が特徴です。
おすすめできる企業の特徴は以下の通りです。
- 自社の強みや提供価値を深く理解した上で提案したい企業
- 顧客との関係構築を重視し、長期的な信頼を積み上げたい企業
- 営業やマーケティングのノウハウを自社内に蓄積したい企業
ただし、採用や教育にコストと時間がかかるため、短期的な成果を求める企業には不向きかもしれません。
中長期的な視点で営業組織を育てたい企業に向いている運用体制といえるでしょう。
関連記事:売れる営業人材の育成方法|計画の立て方・ポイントを解説
外注
インサイドセールスの代行会社に業務を委託する方法です。
専門知識と実績を持つ外部パートナーに任せることで、短期間で仕組みを構築しやすくなります。
おすすめできる企業の特徴は以下の通りです。
- 営業リソースやノウハウが不足しており、早期に成果を出したい企業
- 商談数の拡大や新規リード獲得をスピーディーに進めたい企業
- 成果報酬型など柔軟な契約でリスクを抑えたい企業
一方で、自社理解が浅いまま進行すると、コミュニケーションのズレが生じることもあります。
外部パートナーとの連携体制や情報共有のルールを明確にすることで、成果を最大化できるでしょう。
ハイブリッド型
内製と外注の両方を組み合わせる方法です。
初期フェーズは外注で成果を出しつつ、ノウハウを社内に移行するケースが多いでしょう。
柔軟に対応できる反面、情報共有の設計が不十分だと運用が複雑化するリスクもあります。
おすすめできる企業の特徴は以下の通りです。
- 短期の成果と長期の自走化、どちらも重視したい企業
- 外部パートナーの知見を吸収しながら、自社で再現性を高めたい企業
- 将来的に外注コストを削減し、内製比率を高めたい企業
ハイブリッド型の体制は、スピードと学習の両立を目指す企業に最適です。
外部の力を借りながらも、自社にノウハウを残したい場合に選ぶと効果的でしょう。
インサイドセールスの運用体制ごとのメリット・デメリット
運用体制を決める際は、各手法の特徴を比較し、自社のフェーズに合った選択をすることが重要です。
参照:https://marketingcommit.com/blog/insidesales/575/
内製化のメリット・デメリット
インサイドセールスを内製化する場合、最大の特徴は「自社にノウハウを蓄積できること」です。
一方で、立ち上げ初期はリソース負担が大きく、成果が出るまでに時間を要する点には注意が必要です。
以下では、内製化における主なメリットとデメリットを整理します。
メリット
- 自社理解が深く、顧客対応の質が高い
- ノウハウが社内に蓄積され、再現性が高まる
- 他部署との連携が取りやすく、戦略の一貫性を保てる
- チームの成長が企業の資産になり、属人的な営業から脱却できる
- 顧客との関係を長期的に維持し、LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できる
デメリット
- 立ち上げ・教育に時間とコストがかかる
- 人材不足の際にリスクが高く、離職時にノウハウが失われやすい
- 成果が出るまでのリードタイムが長い
- PDCAを回す工数がかかり、改善スピードが遅くなりやすい
- 外部の最新ノウハウを取り入れにくい
内製化は、短期的な結果よりも「自社の成長基盤を整える」ことを重視する企業に向いています。
すぐに成果を求めるよりも、中長期的な視点で営業組織を育てたい企業にとって、有効な選択肢といえるでしょう。
関連記事:インサイドセールスの設計図|部門立ち上げの全ステップと成功のコツを解説
外注のメリット・デメリット
インサイドセールスを外注する方法は、短期間で成果を出したい企業や、社内リソースが限られている企業に向いています。
専門チームに業務を委託することで、スピード感のある立ち上げが可能になる一方、委託先との連携やコスト管理には注意が必要です。
以下では、外注の主なメリットとデメリットを整理します。
メリット
- 専門知識を持つスタッフが即戦力として稼働できる
- 短期間で成果を出しやすい
- KPIやスクリプト設計をプロに任せられる
- 最新の営業手法やツールを活用できる
- 社内リソースをコア業務に集中させやすい
デメリット
- 自社理解が浅く、顧客との温度差が生じやすい
- 長期的にはコストが割高になりやすい
- 委託先への依存度が高まる
- 情報共有や管理が複雑化しやすい
- 品質のばらつきが発生する可能性がある
外注は、スピードと専門性を重視したい企業に有効な選択肢です。
ただし、長期的に継続する場合は、委託先との関係を「任せきり」ではなく「協働パートナー」として位置づけることで、より安定した成果を得られるでしょう。
ハイブリッド型のメリット・デメリット
ハイブリッド型は、内製化と外注の両方を組み合わせた運用体制です。
初期段階では外部パートナーの知見を活かしながら成果を出し、同時に自社内でノウハウを蓄積していくことができます。
スピードと自走力の両立を目指す企業にとって、柔軟で実践的な選択肢といえるでしょう。
メリット
- 外注のスピードと内製の深さを両立できる
- ノウハウ移転を通じて自社チームの育成が進む
- リスク分散ができる
- フェーズに応じて体制を調整できる
- 外部の最新知見を取り入れながら、自社の強みに合わせた改善が行える
デメリット
- 情報共有や責任範囲の明確化が難しい
- 運用管理コストが増加する
- 外注先と社内チームの連携不足によってミスが起こりやすい
- 意思決定のスピードが遅れることがある
- 外注・内製それぞれのKPIを整合させる仕組みづくりが必要になる
ハイブリッド型は、段階的に自社体制を強化したい企業に最適です。
外部のノウハウを活用しつつ、最終的に自社で運用を完結できるように設計することで、安定的かつ効率的なインサイドセールスの仕組みを構築できるでしょう。
代表的なインサイドセールスの代行企業3選
成果を最短で出したい場合、インサイドセールスを外注するのは効果的な手段です。
そこで豊富な実績とノウハウを持ち、信頼性の高い代表的なインサイドセールス代行企業を3社紹介します。
参照:https://willof-work.co.jp/salesmedia/article/2868/#10
SORAプロジェクト
SORAプロジェクトは、BtoB企業を中心に営業代行を行う企業です。
リスト作成からスクリプト設計、架電までを一貫して支援し、成果に直結する運用体制の構築をサポートします。
業界や商材特性に応じた柔軟な提案が可能で、アポイント獲得の質と量の両立を目指す企業に適しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス内容 | アポ獲得注力型・クロージング型・既存アップセル型 |
| 料金形態 | 固定報酬型(50万円〜) |
| URL | https://sora1.jp/ |
セイヤク
セイヤクは、成果報酬型のインサイドセールス代行サービスを提供する企業です。初期費用を抑えながら、短期間でリード獲得や商談化を実現できる点が強みです。
スタートアップや中小企業からの支持が高く、スピード感を重視する企業やテスト導入を検討している企業におすすめできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス内容 | リード獲得・商談化支援・成果報酬型営業代行 |
| 料金形態 | 要問い合わせ |
| URL | https://lp.seiyaku-sales.jp/general/index.html |
アースリンク
アースリンクは、営業代行だけでなくマーケティング支援にも強みを持つ総合型の支援企業です。
AIツールやCRMを活用し、データドリブンなアプローチで顧客との接点を最適化します。
単発のリード獲得にとどまらず、長期的な営業体制の構築を目指す企業に適したパートナーといえます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス内容 | 営業代行・インサイドセールス支援・マーケティング連携支援 |
| 料金形態 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.earthlink.co.jp/services/sakura-outsourcing/ |
内製化でインサイドセールス立ち上げる手順
自社でインサイドセールスを立ち上げる際は、段階的に進めることが成功のポイントです。
目的を定める
まずは「何を達成したいのか」を明確にしましょう。インサイドセールスを立ち上げる際に目的が曖昧だと、チームの方向性が揃わず、成果指標(KPI)の設定やアプローチ手法がちぐはぐになってしまいます。
目的の例としては、次のようなものが挙げられます。
- 商談数を増やしたい
- 休眠リードを掘り起こしたい
- 営業効率を改善したい
- マーケティング施策との連携を強化したい
- 顧客データを活用した再アプローチを仕組み化したい
目的を明確にすると、優先すべき施策やリソース配分が判断しやすくなります。
例えば「商談数の増加」を目標にする場合、アプローチ件数や通話率などの量的指標を重視し「営業効率改善」であれば、1商談あたりのコスト削減や成約率向上をKPIに設定することが有効です。
目的が定まることで、シナリオ設計やKPI設定の軸がぶれにくくなります。
関連記事:インサイドセールス(SDR)のKPI|目標設定と管理のポイント
シナリオ・KPIを設定する
次に、リードへのアプローチ方法を「シナリオ」として設計します。
シナリオは顧客の購買段階や属性に応じて、どのようなコミュニケーションを取るかを可視化するプロセスです。
KPIは、以下のようにフェーズごとに段階的に設定するのが理想です。
- 架電件数
- 通話率
- 商談化率
- 成約率
各種KPIを数値化して追うことで、どの段階にボトルネックがあるかを特定しやすくなります。
例えば「通話率が低い」場合はリスト精度の見直し、「商談化率が低い」場合はトークスクリプトや訴求内容の改善が必要です。
また、ツールを活用してリアルタイムにデータを可視化することも効果的です。
CRMやMAツール(例:HubSpot、Senses、Salesforceなど)を使えば、チーム全体で数値を共有し、改善のスピードを上げられます。
実は多くの企業が正しく使えていないKPI。
正しくマネジメントする方法を学び、営業強化に繋げませんか?
本日はKPIについて1から学べる資料をご用意いたしました。ぜひ併せてご覧ください。
▶︎▶︎KPIの資料を無料でダウンロードする。
人材を確保・育成する
最後に、人材の確保と教育体制を整えましょう。
インサイドセールスにおいては、営業スキルだけでなく、顧客理解力・ヒアリング力・データ分析力が求められます。
特に、電話やオンラインを通じた営業では「短時間で信頼を築く力」が重要です。
商談目的ではなく、課題を引き出す姿勢を持つ担当者が成果を出しやすい傾向にあります。
採用段階では、傾聴力や論理的思考力、情報整理力に注目するとよいでしょう。
育成フェーズでは、ロールプレイや通話録音のフィードバックを習慣化し、成果事例や失敗事例をチーム内で共有します。
加えて、定量データ(通話数・商談率)と定性情報(顧客の反応)を両面から分析できるようにすることで、再現性の高いチームへと成長します。
関連記事:新人営業を即戦力にするための育成方法5つ|身につけさせるべきスキルとSFAを活用した教育術を紹介
まとめ
インサイドセールスの導入では「スピードを重視するか」「ノウハウを蓄積するか」によって最適な体制が異なります。
- 短期成果を求めるなら外注
- 長期的な組織強化を目指すなら内製化
- 両方のバランスを取りたいならハイブリッド型
まずは自社の現状を見極め、無理のない形から始めてみましょう。
立ち上げの具体的なステップを詳しく知りたい方は「明日からはじめるインサイドセールス」資料をご覧ください。
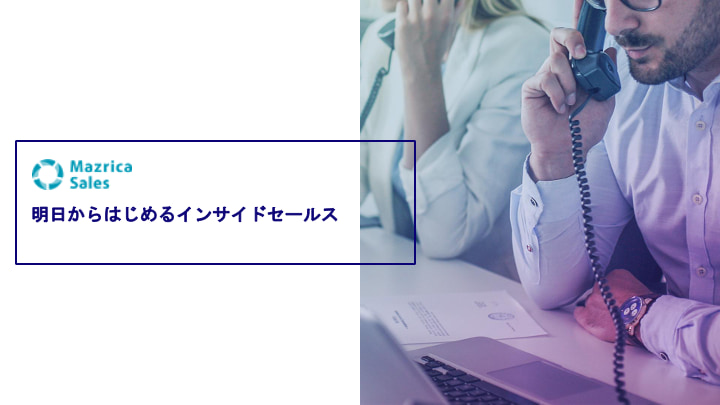
明日からはじめるインサイドセールス
インサイドセールスの立ち上げのポイントを紹介します。「アポイントの獲得率が低い」や「受注率が低い」といった課題別の考え方や対策まで紹介しています!
資料をダウンロードする