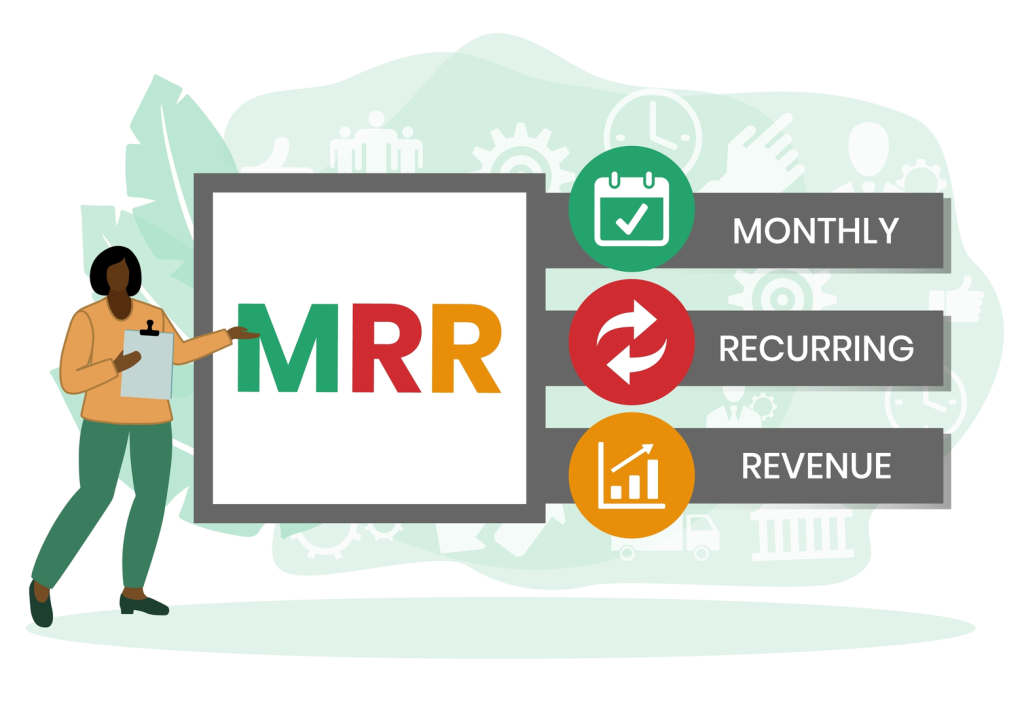営業活動の効率化を図る上で、案件共有は欠かせない要素です。情報が各担当者に分散していると、対応の遅れや重複作業が発生し、成果に悪影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、営業チーム内での案件共有の重要性とその方法、実践時のポイントについて解説します。営業の業務効率化やチームの生産性を向上させるための参考になれば幸いです。
この記事の内容
営業活動で案件管理が重要な理由
営業組織が成果を上げるためには、案件ごとの進捗状況や対応履歴を明確に管理し、チーム全体で共有する仕組みが不可欠です。ここでは、案件管理がなぜ重要なのか、4つの視点から具体的に解説します。
ナレッジの蓄積で属人化を防げる
案件管理を行うことでナレッジが蓄積され、属人化を防ぐことができます。
営業活動が個人に依存している状態では、担当者の異動や退職があった場合に、案件の引き継ぎがスムーズにいかず、対応の質が低下するリスクがあります。
たとえば、過去にどのようなアプローチを行ったかや、顧客が抱えていた課題とその反応を共有しておくことで、新たに担当するメンバーもスムーズに対応できるようになります。
関連記事:営業の属人化はなぜ起こる?原因と7つの解消方法を解説
営業組織の関係性向上
案件共有を通じて営業組織内の関係性が強化され、チームワークの向上につながります。
情報が共有されていない状態では、「言った・言わない」「聞いていない」といったトラブルが起こりやすくなり、それがチーム内の信頼関係を損ねる原因になることもあります。
たとえば、前任者が顧客と合意していた内容を後任者が知らずに別の提案をしてしまった場合、顧客対応に齟齬が生じ、クレームや信頼低下に直結する恐れがあります。
しかし、案件情報をチーム全体で正確に共有していれば、こうしたリスクを回避することが可能です。
情報の透明性が担保されている営業組織では、メンバー同士が互いに連携しやすくなり、自然とチーム内の関係性も向上していきます。
業務効率化の実現
案件管理により、営業活動の無駄を省き、業務効率を高めることができます。
情報が一元化されていれば、必要な情報を都度メンバーに確認する手間が省け、スピーディーな意思決定や対応ができます。
特に引き継ぎや担当者不在の場面では、顧客とのこれまでのやり取りや次のアクション内容が可視化されていれば、他のメンバーでも即座に対応可能です。
さらに、CRMなどのツールを活用することで、商談のステータスや行動履歴、過去の提案内容まで一目で確認できるようになります。これにより、適切な営業資料をすぐに準備できるだけでなく、状況に応じた提案内容の工夫や改善も行うことができるでしょう。
営業機会の損失を防げる
案件管理は、対応の漏れや遅れを防ぎ、営業機会の損失を防ぐことができます。
営業活動では「いつ、誰が、何をするか」のタイミングが成果に直結しますが、案件管理が適切に行えていないと、営業機会を失ってしまう可能性があります。
たとえば、ある案件の次回アクション日を担当者が記録していなかった場合、タイミングを逸して競合に顧客を奪われてしまうこともあります。
案件管理により、適切なタイミングで顧客にアプローチでき、商談機会の損失を防げます。
関連記事:機会損失とは?営業活動における機会損失の意味と具体例、対策を紹介
案件共有がされない背景
案件共有の重要性が理解されていても、現場で十分に実践されていないケースは少なくありません。ここでは、案件共有が進まない主な要因を2つ取り上げて解説します。
ナレッジ共有に後向き
営業現場では、担当者が自らの案件情報や知見を積極的に共有しないケースがあります。
これは、情報を共有することが自分の武器を手放すことだと捉えられたり、評価や成果が個人単位でされる文化が根付いているために起こりやすい傾向です。
また、すでに成果を上げている営業パーソンからすれば、他者のナレッジを共有するメリットをあまり感じていない場合もあります。
案件共有を活性化させるには、共有による組織全体へのメリットや、評価指標を「個人」から「チーム」へとシフトすることが求められます。
後手に回ってしまっている
案件共有の重要性は理解していても、日々の業務に追われ、情報共有のタイミングを逃してしまうケースが少なくありません。
営業パーソンは、顧客対応や商談の準備、提案書の作成、社内での調整業務など、常に多くのタスクに対応しています。そのため、案件情報の入力や共有が後回しにされがちです。
さらに、システムへの情報入力に時間がかかる場合、共有の手間が心理的なハードルとなり、実行されにくくなります。こうした状況を改善するには、案件共有そのものが業務の負担とならない仕組みを整えることが重要です。
具体的には、共有作業が簡単に行えるフローを構築したり、入力の手間を減らせるツールを導入することで、忙しい営業現場でもスムーズに情報が共有される環境を整備できます。
営業の案件共有を行う具体的な方法
営業の案件共有を効果的に進めるには、「何を・どうやって・どのルールで共有するか」を整理することが大切です。ここでは、案件共有を行う具体的な方法を紹介します。
共有すべき案件情報を設定する
まずは、何を共有するのかを明確にすることが案件共有の第一歩です。共有する内容が人によって異なると、情報に抜けや偏りが出てしまい、チーム全体での活用が難しくなります。
顧客の基本情報や商談の進捗、提案内容、顧客の反応、今後のアクション予定など、共有すべき項目をあらかじめ統一しておくことで、誰が入力しても同じフォーマットで情報が蓄積されます。これにより、引き継ぎや分析の精度が高まり、営業活動の質が安定します。
また、業務と関係のない個人的な情報や、機密性の高い情報など、共有すべきでない情報も明らかにしておくことで、リスクヘッジもできます。
情報共有の手段を決める
効果的な案件共有を実現するには、情報共有の手段を自社の目的や業務スタイルに合わせて決める必要があります。
管理ツールを選ぶ際は、社内外からのアクセス方法、検索や更新のしやすさ、情報の利用方法などの観点から検討することが重要です。
たとえば、営業チームが外出先から確認できるようにするなら、スマホやクラウド対応のツールが有効です。また、情報を履歴として残したい場合は、変更ログの記録や検索機能の強いシステムが適しています。
また、業務プロセスによっては1つのツールですべてをカバーするのは難しいため、CRMやSFA、チャットツールなどを組み合わせて運用することを念頭にツールを選ぶとよいでしょう。ツールの詳細や選び方については、記事の後半でも詳しく解説します。
情報共有のルールを定める
情報共有を形骸化させないためには、運用ルールをあらかじめ定めておく必要があります。
誰が・いつ・どのように情報を記録するのかを明確にしておくことで、情報の更新や管理が習慣化されます。
たとえば、「商談後は24時間以内にCRMへ記録する」「次回アクションは必ず期日とセットで明記する」といったルールを設ければ、共有漏れや記載のばらつきを防ぐことができます。ルールは現場の声を反映しながら定期的に見直し、実用性を保つことがポイントです。
案件共有を行う際のポイント
案件共有を円滑に進め、継続的に運用していくためには、単に仕組みを整えるだけでなく、失敗しないために気をつけるべきポイントがあります。ここでは、3つのポイントを紹介します。
目的を明確にする
案件共有の取り組みを始める際は、まず「なぜ共有するのか」という目的を明確にすることが重要です。 目的が曖昧なままだと、共有が形だけのものになり、実際の行動に結びつきません。
たとえば「営業効率を上げたい」「属人化をなくしたい」「チーム全体の案件状況を把握したい」「顧客満足度をアップさせたい」といった明確なゴールがあれば、共有すべき情報の範囲や活用方法も定まりやすくなります。
また、目的をメンバーと共有することで、共通認識を持った上で取り組むことができ、組織全体の協力も得やすくなるでしょう。
スモールスタートで始める
案件共有の仕組みは、いきなり部署をまたいで大規模に展開するよりも、小規模なチームや一部の業務から始める方が現実的です。最初から全体に適用しようとすると、運用が複雑になり、現場が付いていけず失敗に終わってしまう可能性があります。
まずは営業会議での情報共有から始めたり、特定の案件だけを対象にして共有を試みるなど、試行錯誤を前提とした導入方法が効果的です。段階的に運用を広げていけば、チームに合ったスタイルを見つけやすく、定着率も高まります。
目的を果たせるSFA/CRMツールを導入する
案件共有を継続的かつ効果的に行うには、目的に合ったツールの導入が欠かせません。手間がかかる共有方法では運用が続かず、情報も活用されなくなってしまいます。
たとえば、SFAやCRMを活用すれば、商談の進捗状況や顧客対応履歴をリアルタイムで管理できるため、共有内容が自然と蓄積されていきます。また、過去のデータを分析して営業戦略に活かすことも可能になります。
ただし、SFAやCRMはツールベンダーによって機能が異なったり、得意領域があるため、どのツールが自社の営業プロセスに合っているか、自社の目的を果たせそうかを慎重に選ぶことが大切です。
関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説
SFA/CRMを導入する際のポイント
SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)は、案件情報の可視化やチーム間の情報共有を支援する重要なツールです。しかし、自社の業務フローやニーズに合ったツールを選び、正しく活用することが成功の鍵となります。
ここでは、SFA/CRM導入を検討する際に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
▶︎▶︎40以上の製品から自社にあったSFA/CRMがわかる分類チャートはこちらから
使いやすいツールを選ぶ
SFA/CRMを導入する際、操作性の高さは最も重視すべきポイントの一つです。 どれほど高機能でも、営業担当者が日常的に使いこなせなければ意味がありません。
実際、弊社が実施した「SFA/CRMの利用実態と活用課題に関する調査」によると、43.6%の企業が「情報の入力・更新が複雑」と感じており、40.6%が「営業メンバーが情報を入力しない」という課題を抱えています。さらに、現場が入力しない最大の理由として54.5%の企業が「入力作業に時間がかかるから」と回答しています。
この結果からも明らかなように、入力負荷が少なく、直感的に使えるUIを備えたツールを選ぶことが、導入成功のポイントとなります。
サポート体制が整ったツールを選ぶ
ツール導入後の運用をスムーズに進めるためには、ベンダーによるサポート体制の充実も重要です。 操作に関する疑問点への対応やトラブル発生時のサポート、アップデート時の情報提供など、導入後のフォローがしっかりしていれば、現場の不安や混乱を最小限に抑えることができます。
具体的にどのようなサポートを受けられるのか、相談窓口はどこか(電話、メール、Webサイト、チャット)など、事前に確認しておきましょう。
現場に導入の目的を伝える
どれほど優れたツールを導入しても、現場に目的や意義が伝わっていなければ、十分に活用されないまま形骸化してしまいます。
導入によって何が改善されるのか、現場の業務にどのようなメリットがあるのかを具体的に伝えることで、営業パーソンの納得感と協力が得られます。
また、導入後のルール設定やツールの使い方についても、現場の声を反映させながら調整することで、現実的で使いやすい運用フローを構築することが可能です。目的をしっかりと伝え、現場とのコミュニケーションを丁寧に行うことが、ツール活用を成功に導くポイントです。
まとめ
営業活動における案件共有は、生産性の向上や営業機会の最大化に直結する重要な取り組みです。情報が整理・共有されていれば、属人化を防ぎ、チームでのスムーズな連携が可能になります。
案件共有を実現するには、共有すべき情報の明確化、ルールづくり、そして使いやすいSFA/CRMツールの導入が不可欠です。特に、現場がストレスなく使える操作性と、導入後のサポート体制は重視すべきポイントです。
「Mazrica Sales」は、直感的な操作性と充実したサポートを兼ね備えた、案件共有に最適なSFA/CRMです。詳しい機能やサポート内容は、下記の資料からご確認ください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI
資料をダウンロードする