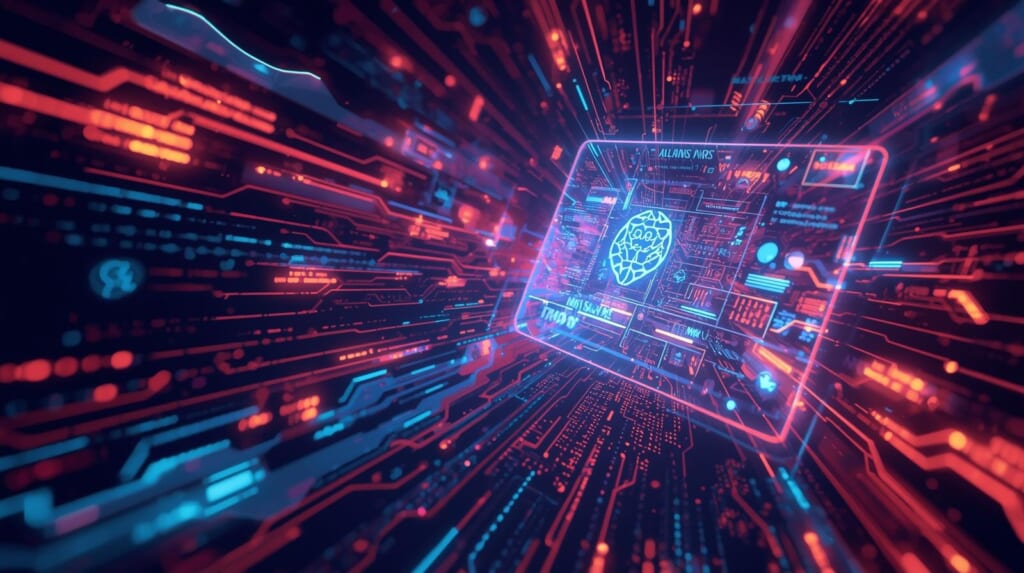「ロングテール戦略」という言葉を、マーケティングやECに関する話題で目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
特に、Amazonの成長戦略を語るうえで欠かせないキーワードとして知られています。
しかし、言葉は知っていても、実際にどのような戦略で、どんな場面に活用できるのかを正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。
そこで本記事では、ロングテール戦略の基本的な考え方から、ビジネスへの活用方法、そして実施する際のポイントまでをわかりやすく解説します。
この記事の内容
ロングテール戦略とは?
ロングテール戦略とは、売れ筋の商品に依存するのではなく、販売総数の少ないニッチな製品を数多く取り扱うことで対象となる顧客の総数を増やし、販売利益を増やすマーケティング戦略です。
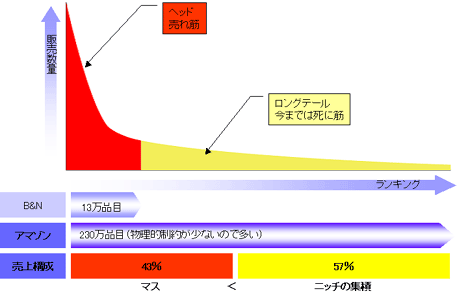
(富士通総研HPより)
販売量を縦軸に取り、横軸に商品を並べた場合上記のような図が出来上がります。この図で黄色で表されている販売数量が少ない部分の総量で利益を得よう、ということがロングテール戦略の基本の考え方です。
ロングテールとは英語のLong tail(長い尻尾)のことですが、上図の黄色の部分が細長く尻尾のように見えることからその名前がつけられました。
その名前をつけたのが雑誌『Wired』の編集長であったクリス・アンダーソンという人物であり、ロングテールの概念の始まりとなりました。その考え方は、それまで主流であったパレートの法則と対立するものとしてビジネス界を驚かせました。
パレートの法則とは、全売上の8割を2割の顧客が担っているということを示すもので、この法則はその2割の顧客にターゲットを絞ることが重要であるという考え方に帰結しています。
しかし、アンダーソンのロングテールはそれとは全く逆で、むしろ残りの8割の顧客に目を向けてものを売ろうとする考え方だったのです。
ロングテールの生まれた背景
ロングテール戦略の生まれた背景には、WEBによるマーケティングの普及があります。
今まではものを売るためにコストがかかっていましたが、インターネットの発展により物を対面で売る必要はなくなり、物を売るためのコミュニケーションコストは限りなくゼロに近くなりました。
ロングテール戦略で売り上げを伸ばしたAmazonを見ればわかるように、ロングテールの舞台(=サイト)を作ってしまえば、あとは商品をどんどん追加していくだけで売れていくのでコストが低いのです。
こうした背景から、パレートの法則だけに固執するのではない、ロングテール戦略という新しい考え方が生まれてきました。
関連記事:マーケティング戦略とは?立案手順とフレームワーク・事例を解説
ロングテール戦略のメリット
ロングテールのメリットには3点挙げられます。
売り上げが安定すること
一つの商品に依存しているわけではなく、そこそこの人気の多くの商品によって支えられているために売り上げが安定します。
もし一つの商品に依存してしまっていたら、その商品の人気がなくなってしまうとすぐに売り上げが落ちてしまいますが、多数の、幅広い需要がある商品に支えられているためにそうした心配はありません。
流行やブームといったものに左右されずに必ず売り上げを出し続けられる、ということが強みです。
コストパフォーマンスがいい
導入に際し、在庫の仕入れ以外の初期費用がほとんどかかりません。サイトを作るコストのみで始めることができます。
さらに、ウェブを通して運営を行うために人的コストもほとんどかかりません。
もちろん、サイトの更新は売れ続けるために必要ですが、逆に言えばそのコストのみで長い間安定した売り上げを挙げ続けられます。
長期的に見てコストパフォーマンスがいいこともロングテール戦略の強みです。
不良在庫という概念がなくなる
全ての商品がウェブ上で商品として提示されており、売り上げをあげる可能性を内包しているために不良在庫という概念はなくなります。
そもそもロングテールとは、売れにくい商品にこそ目をつけたものであり、サイトや大規模店舗など環境さえ整えて多くの商品を並べればいいのです。
そうすれば集客がより見込めるようになりますし、それに伴って売り上げも上昇します。
顧客の幅広いニーズを拾える
ロングテールの販売戦略をとると、販売する商品を絞る必要がなく顧客の幅広いニーズに対応することが可能です。
ECサイトでは年に数回しか売れない商品であっても、商品ページの作成後は手間もスペースもかからないため、販売し続けることができます。
店頭よりも幅広い種類の商品を低コストで販売し続けることができるため、ニッチな商品を求めている顧客へのアプローチにもつながります。
幅広い商品を販売することで顧客の求める商品が見つかる可能性が高まり、顧客満足度の向上やリピートも期待できるでしょう。
ロングテール戦略のデメリット
ロングテール戦略を行うことには、デメリットもあります。
結果が出るまで時間がかかる
ロングテール戦略は、短期的な成功を狙うのではなく、長期的な視点で少しずつ売上を積み上げていく方法です。
工夫をしてもすぐに結果が出るわけではなく、時間がかかる傾向があるため、根気強く継続することが重要です。
ECサイトを作成し、商品ページを充実させても、顧客に見つけてもらわなければ売上につながりません。
見つけてもらうためのSEO対策を行っても、すぐに検索結果の上位に表示されるわけではないため、顧客の流入までに時間がかかります。 この時間がかかることを考慮しないと、大量の在庫を抱えてしまうリスクもあります。
在庫管理にコストがかかる
ロングテール戦略では、多くの商品を取り扱うため、在庫を保管するスペースが必要となり、在庫管理にコストが発生します。
ECサイトを利用することで陳列スペースの問題は解消されますが、在庫を保管するためのスペースは依然として必要です。 多くの在庫を抱える場合、大きな倉庫を借りる必要があり、業務効率が低下する可能性もあります。
そのため、在庫管理システムの導入を検討することが重要です。
Webマーケティングスキルが必要
ロングテール戦略を成功させるためには、ECサイトを作成し、各商品ページに顧客を誘導する必要があります。
そのためにはSEO対策が欠かせません。自社のECサイトを検索結果の上位に表示させるためには、Webマーケティングの知識が必要です。
また、集客のためにはターゲットを絞り、適切なプラットフォームを選んで、SEOに適したサイト構築を行うことが求められます。
さらに、SEO対策に加えて、オンライン広告やSNSの活用も重要です。自社でWebマーケティングを行うのが難しい場合は、外注を検討することも有効です。
関連記事:コンテンツSEOとは?8ステップで成果を出す手順と事例を紹介
ロングテール戦略の実施方法
ここからは、具体的なロングテール戦略の実施方法を解説します。
顧客を分析する
ロングテール戦略は数多くの商品を取り扱う方法ですが、最初から複数のジャンルの商品を取り扱うとコストが膨大になります。
まず、購買履歴や閲覧履歴などをもとに顧客分析を行い、売上につながるジャンルを見極めることが重要です。 ターゲットを絞ったうえでニッチな商品も取り扱うと、長期的に利益を得られる可能性が高まります。
ECサイトの構築
ターゲットや取り扱う商品を決定したあとは、ECサイトの構築が必要です。
構築の際には、検索エンジンで上位表示されるように設計することが重要です。商品ページを随時更新し、詳細情報や関連情報を追加するなどの工夫を凝らすことで、売上に直結しやすくなります。
SEOを考慮した設計を行うだけでなく、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)にもこだわった商品ページにすることで、ECサイトに訪れた顧客の購買意欲を高めることができるでしょう。
ロングテールの成功事例とそのやり方
では、実際にロングテール戦略の成功例を見てみましょう。
Amazon
すでに取り上げたように、Amazonはロングテール戦略で成功した最も有名な例の一つです。
Amazonは、ニッチな商品を非常に多く集めることで売り上げを伸ばしています。
実際、売り上げの57%はロングテール商品が担っており、それらは販売数ランキングが40,000位~2,300,000位の商品です。
ニッチな商品を多く集めてページをとにかく増やすことで集客を行い、売り上げを伸ばしているのです。
さらに、Amazonは商品の保管場所を地価の安い場所に設けることで最大限までコストを抑えています。
こうして巨大倉庫を作ることで多くの商品を保持することとコストの削減を同時に果たしているのです。
Netflix
Netflixもロングテール戦略で大成功を収めました。
そもそも、ロングテールの提唱者のクリス・アンダーソンにロングテールという名前を使うように薦めたのはNetflixの創業者のリード・ヘイスティングスだったそう。
Netflixの強みは、そもそも在庫がないということ。データを取り扱っているので商品を収納しておく倉庫がそもそも必要でなく、場所的な制約は一切ありません。
そのため、Netflixはマイナーな映画やテレビ番組まで取り扱うことができ、それによって集客力を高めました。Netflixの仕組みでは、ランキングが5万位の商品でも売り上げをあげることが可能なのだそうです。
裾野を広げることで、新たな顧客を掴みやすくなり競合他社よりも一歩リードをしているのです。
実店舗での成功事例
次に、実店舗でのロングテール戦略の成功事例を解説します。
IKEA
IKEAは実店舗を持った販売形態ながら、ロングテール戦略で成功しています。
IKEAの成功の秘密は、おしゃれな家具を取り扱っており一度で家具の買い物を済ませられるために集客力が高く、郊外に店舗を構えられるというところにあります。
地価の安い郊外に倉庫と一体化した店舗を構えられるために店舗を巨大化しやすく、ロングテール戦略の条件が整えられているのです。
鹿児島のスーパー 「A-Z」
A-Zは東京ドームのグラウンド面積3個分という広大な敷地を擁しており、そこに乗用車や仏具までをも揃えたありとあらゆる商品を扱っています。
実店舗でロングテール戦略を行う際のネックである場所の制約をその広大な敷地でカバーし、「ここに来たら欲しいものがすべて揃う」というモットーを元にロングテール戦略を展開しているのです。
その結果、A-Zは一日の平均来店者数が約3万人という大人気スーパーとなり成功を納めました。
ロングテールの限界
ここまでロングテール戦略について説明してきましたが、ビジネスの世界の流れは早く、ロングテール戦略のリスクや次の展望までもが見え始めています。
リスクが高い
ロングテール戦略は、十分な売り上げを得るためにかなりの日数を要するという弱点があります。
かなり長期的な視点を持たなければロングテール戦略は行えません。
利益を十分に得る前に大量の在庫を抱えて倒産する危険性も容易に想定されます。ロングテールには長期的な施策であるが故のリスクが存在するということを意識しておきましょう。
Googleの障壁
ロングテール戦略は、ニッチな商品を多数扱うことで利益を上げる手法ですが、Googleの検索結果がユーザーごとにパーソナライズされているため、新しいページや商品が見つかりにくいという課題があります。
この限界を補う戦略として注目されているのがブロックバスター戦略です。
これは、多くの人に響くヒット商品に資源を集中させて収益を狙う方法で、エンタメ業界などで活用されています。
さらに、ビッグデータを活用してニーズを分析し、ヒットの可能性を高めている点が現代的な特徴です。
高リスクになりがちな戦略を、データに基づいて再現性のあるものへと進化させています。
終わりに
ロングテール戦略とは、ニッチな商品の総体によって利益を生み出すアプローチです。
定番商品の売上に頼らず、幅広い品揃えで顧客ニーズを捉えることで成果を上げてきた成功例も少なくありません。
ただし、市場や顧客のニーズが急速に変化する現在において、この戦略だけで優位性を保ち続けるのは難しくなってきています。
ブロックバスター型の戦略のように、ヒット商品にリソースを集中させる手法も併存する中で、ロングテールの活用にも工夫が求められています。
とはいえ、適切なターゲティングや顧客理解があれば、ロングテール戦略は今なお有効です。
市場の隙間を見極め、独自の価値を提供することができれば、それは大きな差別化要素となるでしょう。
自社に合った形で、ロングテール戦略を柔軟に取り入れていく姿勢が、これからのビジネスにおいて重要になります。

Mazrica Sales メール一斉配信機能のご紹介
弊社が2020年4月に実施した調査によると、8割以上の営業組織が「商談機会が減少している」と回答しています。 過去の失注案件への定期フォローが出来ていない場合、 多くの見込案件が眠っているケースがあります。 商談の機会を増やすための施策として、メール配信は有効です。
資料をダウンロードする