現代の医療業界は、超高齢化社会による患者数の増加や人口減少による医療従事者の減少傾向などの課題を抱えています。
これらの課題は、CRMの導入により解決・改善できる可能性を秘めており、経営戦略の立案や改善点の明確化といった経営改善につながることもメリットです。
本記事では、医療機関でCRMを導入した場合、どのような活用ができるのかを紹介し、メリットや導入の注意点について解説します。
この記事の内容
医療業界が抱える課題
CRMの導入は、医療現場の課題にアプローチできる可能性を秘めています。まずは、医療業界が現在抱えている以下の課題について整理してみましょう。
- 超高齢化社会により患者数が増加している
- 医療従事者が不足している
- 地域医療が十分に連携していない
- IIT化やDX化が遅れている
- 病院数が減少している
超高齢化社会により患者数が増加している
2015年にベビーブーム世代が前期高齢者となり、2024年9月15日時点の人口推計によると65歳以上の人口は過去最高の3,625万人です。日本の総人口に占める65歳以上の割合は29.3%で、3割近くが高齢者となっています。
また、厚生労働省の「令和5年簡易生命表の概況」によると、2023年の平均寿命は男性で81.09歳、女性は87.14歳と1990年の男性75.92歳、女性81.90歳から6年近く増加しました。
超高齢化社会となり高齢者の人口が増加したことで、今後も患者数が増えることが予測されています。さらに、平均寿命が延びることで疾病や症状が多様化し、一人の患者が複数の疾患を抱えるケースが増えることも予想されます。
現在の医療状況のままでは、患者数やニーズに対してスタッフや施設の数が不足し、必要な対応ができなくなることが懸念点です。
医療従事者が不足している
高齢者が増加する一方で、2023年の出生数は約72万人、2024年は70万人を切る試算となっており日本の人口そのものが減少に転じています。
しかし、厚生労働省の「令和4年版厚生労働白書」によると、2021年の就業者数は6,713万人で、1990年代後半の水準を維持しています。これは、2000年の法改正により老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられ、定年年齢が繰り上げられたことで60歳以上の就業者が増加したことが理由の一つです。
医療・福祉分野の就業者数は2021年時点で891万人おり、2040年の推定就業者数は974万人と考えられています。医療・福祉分野の就業者数も増加傾向にあるものの、2040年に必要と推計される就業者数は1,070万人です。つまり、96万人もの医療従事者が不足すると予想されています。
医療従事者が不足することで、医療サービスの質が低下する可能性が高まるだけでなく、緊急対応が必要な患者が迅速な医療を受けられなくなるリスクもあります。
地域医療が十分に連携していない
地域医療が十分に連携していないことも、日本の医療業界が抱える課題の一つです。
カナダやイギリスなどはホームドクター(かかりつけ医)制を導入している場合、どのような症状でもかかりつけ医が最初に診察し、その後必要な医療を受けられる病院を紹介します。
しかし、日本にはホームドクター制の概念はまだ薄く、症状に応じて自らクリニックや病院を探して受診することが多い状況です。そのため、患者の病歴を総合して診断することが難しく、適切な医療機関を紹介できず治療開始が遅れてしまう可能性があります。
また、かかりつけ医を通して別の医療機関を紹介してもらう場合でも、一部の医療機関では手書きで紹介状を作成するなど、施設ごとの差が大きく連携しにくいのが現状です。
IT化やDX化が遅れている
医療現場は他業界と比べてIT化が遅れていると言われており、厚生労働省の「電子カルテシステム等の普及状況の推移」によると、2020年時点の電子カルテ普及率は病院で57.2%、診療所で49.9%と低い状況です。
IT化やDX化が遅れているのは、コスト面での理由が大きいとされています。政府は医療DXを推進する施策を打ち出していますが、医療保険制度による診療報酬によって収入が制限されてしまう医療業界では財源確保が難しい状況であるためです。
病院数が減少している
厚生労働省の「令和5年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、2023年10月1日時点で稼働している医療施設は179,834施設で、前年より1,259施設減少しています。また、医療施設のうち20病床以上ある病院は8,122施設となっており、前年から34施設の減少です。
病院は年々減少傾向にあり、高齢者の増加に伴う医療サービスの需要と受け入れる施設数のギャップが今後も大きくなっていくでしょう。
都市部は病院が多く医療サービスが充実しているイメージがあるかもしれませんが、東京都や埼玉県、神奈川県、愛知県など人口が多い地域は人口あたりの病院病床数が少ない傾向にあります。反対に、高知県や鹿児島県、長崎県は人口当たりの病院病床数が多く、人口が集中する都市部でも病院数の減少への対策は重要です。
病院におけるCRMの活用方法
医療業界が抱える課題には、主に患者数の増加や病院数の減少、医療従事者の不足といったものが挙げられます。これらの課題は国全体で取り組んでいく必要はありますが、医療施設ごとにできる対策がCRMの導入です。CRMを導入すれば、次のように活用できます。
- 営業先や新規連携先の開拓
- 効率的かつ迅速な情報共有
- 院内の弱点や改善点の明確化
- 経営戦略の立案
確かにCRMは大きな可能性を秘めていますが、導入すればすぐに課題を解決してくれる魔法のツールではありません。ここでは、CRMの有効的な活用方法についてそれぞれ詳しく解説します。
関連記事:CRMとは?導入メリットや機能、ツールの選び方/活用例を解説
営業先や新規連携先の開拓
CRMを活用すると、医療施設の紹介数や転院数、医師情報などの情報を一元管理できます。データを時系列で分析したり、必要な情報だけをピックアップしたりすることも可能です。
たとえば、空き病床数や医師のスケジュールを外部施設と共有することで、患者の受け入れ先を一件一件あたる必要がなくなり、ダイレクトに打診できるようになります。
また、エリアごとに病院をマッピングすれば、空き病床や診察に余裕がある紹介先をピックアップできるようになり、営業活動や新規連携先の開拓がしやすくなるでしょう。営業先の開拓については、次の記事を参考にしてください。
関連記事:新規開拓営業とは?14の営業手法とうまくいかない時の対処法
効率的かつ迅速な情報共有
CRMは単体でも活用できますが、電子カルテやレセコンと連携することでより効果的に利用できるようになります。
インターネット環境があれば、どこにいてもアクセス可能となるため、急いで対応が必要な場合でも医師が自宅や出張先から情報を確認できます。医師や看護師、事務スタッフなどがリアルタイムで患者情報を共有できるため、内部連携が強化されることもCRM活用の魅力です。
CRMを活用することで質の高い治療プランを構築できるだけでなく、カルテ記入やレセプト業務といった事務作業の省力化やペーパーレス化を進められます。
院内の弱点や改良点の明確化
CRMは診療科や医師別の患者数、新規患者数、入退院数、在院日数、病床回転率などを時系列で確認できます。客観的に数字で表すことで、院内の弱点や改善点が明らかになり、運営の効率化やサービス向上につなげることが可能となり、運営手法の改善や強化に役立ちます。
経営戦略の立案
医療施設の経営戦略を立案してもらえることも、CRMの活用方法の一つです。
多くのCRMツールには、ベンダーのコンサルティングサービスが付いており、専門的な知識を持つコンサルタントによる現場分析や目標設定、改善策の提案などのサービスを受けられます。
日々の業務に忙しい医師や看護師、その他医療スタッフがCRMの機能を駆使して活用するためには時間の確保が課題となります。しかし、専門知識を持つコンサルタントがプロの視点から現場で集めたデータを分析し、経営戦略に落とし込むことで業績向上を期待できるでしょう。
病院でCRMを導入するとできること
CRMは顧客情報を収集・管理・分析することで、顧客との関係を構築するために役立つツールです。一般企業で活用されており、医療機関には馴染みのないツールかもしれませんが、実は医療分野でもさまざまな活用方法があります。
ここでは、CRMを医療機関に導入した際、どのようなことができるようになるかを解説します。病院でCRMを導入するとできることは以下のとおりです。
- 情報の一元管理
- 取引先管理
- 案件管理
- 予約管理
- 在庫管理
それぞれ解説します。
情報の一元管理
医療機関や製薬会社にCRMを導入すると、顧客(患者)の基本情報や受診歴、服薬情報を一元管理できるようになります。Excelやスプレッドシートなどに書式を作って管理する必要がなくなるため、スタッフ間の情報共有もしやすくなり、コミュニケーションコストの削減も可能です。
また、受付・看護師の問診・医師の診察など同じ質問を何度もされることは、患者にとって苦痛の原因となりかねません。CRMを導入することで、リアルタイムで情報共有できるようになるため、患者にとっても満足度の高い医療を受けられるようになります。
取引先管理
取引先の連絡先を一元管理できることも、CRMの特徴の一つです。アクセス権限があれば誰でも閲覧できるシステムに商談内容を残すことで、見込み顧客の分析が可能となります。
また、医療施設であれば地域の施設と情報を共有することで、転院先や検査機関を探す際に役立つでしょう。取引先管理の方法は次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:取引先管理の4つの方法!目的の整理と方法選定のポイント
案件管理
CRMでは、商談や案件の進捗状況や見積もり、発注金額も一元管理できるため、効率的な情報管理ができるようになります。
競合他社が多い製薬業界では、失注分析や見込み顧客獲得のための情報管理が重要です。徹底的に分析することで、新規顧客の獲得や既存顧客への提案にもつながります。
CRMに登録した案件をもとに、自動でレポートを作成することも可能で、失注した要因の分析など次の機会に役立てる手助けになるでしょう。CRMの案件管理については、次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:CRMで変わる案件管理!CRMのメリットや導入のポイント
予約管理
医療機関にとって必要不可欠な予約管理が可能なことも、CRMの特徴です。非接触の来院受付やリマインド機能を使うことで、患者がスムーズに受診できるだけでなく、医療機関にとっても業務負担を軽減できます。
また、CRMの予約管理機能はLINEなどのSNSや電子カルテ、会計システムと連携できるため、予約から診察、会計まで一元管理できるようになります。
在庫管理
薬剤や医療材料などの在庫管理は医療業界にとって重要な機能ですが、CRMを導入すれば在庫管理も一元化できます。
患者の命に直結する医療機関や製薬会社、医療機器メーカーの在庫管理業務では、正確な管理環境が必要です。CRMを使って患者情報と在庫管理を一元管理することで、投薬情報を把握し、在庫不足によるトラブルを避けてリスクを低減することが可能となります。
▶︎▶︎病院での導入にもおすすめの使いやすいCRMの詳細はこちらから
病院にCRMを導入するメリット
CRMには、効率的な情報共有や改善点の明確化などさまざまな活用方法があります。
では、CRMを導入することで具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、CRMを導入するメリットを5つ紹介します。
- 医療業務を効率化できる
- 情報をデータベース化できる
- 患者データを管理できる
- 円滑なコミュニケーションを促進できる
- 医療機関との連携を強化できる
それぞれ解説します。
医療業務を効率化できる
CRMを導入することで、医療業務を効率化できることがメリットの一つです。
医療機関では医師や看護師、リハビリスタッフ、検査スタッフなどさまざまな専門性を持つ医療スタッフが協力することで、医療サービスを提供しています。一人の患者に関わるスタッフの数が多ければ多いほど、情報伝達のミスによる事故が起こりやすくなるため、スムーズな情報伝達が必要不可欠です。
CRMを活用すれば、リアルタイムで情報共有が可能となるため、紙を使ったオーダーや口頭での指示が不要となりミスの防止につながります。さらに、情報伝達にかかる時間を大幅に短縮できるようになり、患者の待ち時間軽減など利用者の満足度向上も期待できます。
情報をデータベース化できる
膨大な情報をデータベース化できることも、CRM導入のメリットです。患者情報や医薬品情報といった膨大な情報も一度データベース化してしまえば、利用したい情報を瞬時に引き出して利用できるようになります。
製薬会社や医療機器メーカーと連携して薬の使用状況や在庫情報を共有することで、患者に必要な薬の在庫量を自動で計算して、在庫不足を防ぐ在庫管理の自動化も実現可能です。
CRMを使ってデータベース化する方法は、次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:顧客データベースの作り方 CRMとエクセルでの顧客管理方法を解説
患者データを管理できる
CRMを導入するメリットには、患者情報を効率的かつ活用しやすい形で管理できることも挙げられます。
患者一人ひとりの情報を集約管理し、診察内容や検査結果、治療歴、薬歴、看護記録などを一元管理できるようになります。管理している情報は、他院への紹介時にデジタルデータとして簡単に情報共有できるため、業務効率や品質が飛躍的に向上するきっかけになるでしょう。
円滑なコミュニケーションを促進できる
CRMは単純に情報を管理するためだけのツールではなく、スムーズな情報共有によりコミュニケーションコストを削減できることもメリットです。
最新の検査結果やバイタル情報など、患者に関する医療情報がリアルタイムでCRMに集約されることにより、口頭や書面による情報共有は不要となります。各部署に行って直接やりとりする手間を省き、聞き間違いや書き取りミスなどによる医療事故を未然に防ぎ、円滑なコミュニケーションを促進します。
また、近年は複数部署のスタッフが連携して患者の治療やケアに当たるチーム医療が推進されており、CRMはそれぞれの持ち場で働くチームメンバー同士の連携を強化するためにも重要です。
医療機関との連携を強化できる
CRMの導入には、地域の医療機関との連携を強化するメリットもあります。
従来、地域の医療機関と連携する際は電話やFAX、郵送でやり取りしていました。しかし、これらの情報共有方法はリアルタイムではないためタイムラグが生じたり、ヒューマンエラーが起こりやすいデメリットがあります。
CRMを導入すればタイムリーに最新の情報を共有でき、言い間違えや聞き間違えなどのヒューマンエラーのリスク低減が期待できます。地域全体で同じCRMツールを導入することで、医療連携のインフラを整えることも可能です。
病院にCRMを導入する際の注意点
CRMを導入すると患者情報や医薬品情報を一元管理できるようになり、業務の効率化や他の医療機関との連携強化といったメリットがあります。
一方で、CRMを導入する際の注意点も知っておく必要があるでしょう。ここでは、医療機関でCRMの導入を検討するときに知っておきたい注意点を4つ解説します。
- 導入や運用などにコストがかかる
- 既存のシステムと連携できない可能性がある
- 教育や研修にリソースが必要になる
- セキュリティを強化しなければならない
それぞれ解説します。
導入や運用などにコストがかかる
CRMは医療機関が抱える膨大な情報を一元管理できる便利なツールですが、導入には初期費用やランニングコストがかかります。初期設定やカスタマイズはオプションであることがほとんどで、実際に使用するスタッフへのトレーニングにも費用が必要です。
また、一度導入したら終わりではなく、月々の利用料や定期的なシステム更新費用、保守管理のためのメンテナンス費用などのランニングコストも加味しなくてはなりません。
導入コストや運用コスト、求める機能やシステム規模によって費用が大きく変わるため、費用対効果を十分にシミュレーションして導入する必要があるでしょう。
既存のシステムと連携できない可能性がある
CRMは電子カルテシステムや受付システムなどの他システムとの連携が可能ですが、既存のシステムと連携できるかはCRMの選定時に確認が必要です。連携できない場合は、データの二重入力や情報共有の遅れが生じて、CRMを導入したにもかかわらず業務効率が低下してしまう恐れがあります。連携には追加開発や費用が必要になるケースもあるため、事前に確認してよく検討する必要があるでしょう。
また、連携可能だとしても、実際の運用時に互換性の問題が発生することも考えられます。そのため、CRMの本格運用までの入念なシミュレーションと準備が大切です。
教育や研修にリソースが必要になる
CRMは導入すればすぐに活用できるものではなく、活用方法をユーザーが学ぶ必要があります。CRMに関する教育や研修を怠ってしまうと、スタッフが使いこなせないことからツールが定着せず、コストをかけて導入しても効果を感じられない結果になりかねません。
導入前にCRMのメリットを知ってもらい、使い方のレクチャーや運用ルール・マニュアルの共有を行うことでスムーズに導入できます。また、定期的に研修を開催することで、有効活用できているかを確認し、定着を図ることも重要です。
セキュリティを強化しなければならない
CRMは情報を一元管理し、スタッフ間や医療機関間の情報伝達をスムーズに行えるメリットがある一方で、ユーザーは情報流出といったセキュリティ面での危険性も理解しておくことが大切です。
電子カルテシステムの普及に伴い、近年は医療機関へのサイバー攻撃も散見されます。たとえば、2024年には岡山県精神科医療センターの電子カルテシステムがサイバー攻撃に遭い、最大4,000人分の患者情報などが流出したと発表されました。
CRMを使った情報共有は便利である反面、十分なセキュリティ対策の強化が求められています。しかし、闇雲にセキュリティ面でのリスクを恐れる必要はありません。アクセス制限やユーザー一人ひとりの意識を高めるセキュリティ研修会など、対策を講じることでリスクの低減を図ることが重要です。
病院にCRMを導入する際のポイント
実際に、医療機関がCRMを導入する際、どのような視点でツールを選定して導入準備を進めれば良いのでしょうか。
CRMを選定する際に押さえたいポイントは、主に次の5つです。
- 必要な機能を精査する
- 複数の候補を決めて比較する
- 現場担当者の意見を重視する
- 顧客目線でCRMを選定する
- 事前に社内の理解を深める
ここでは、上記の5つのポイントをそれぞれ解説します。
必要な機能を精査する
CRMは基本的な機能だけを備えているシンプルな製品から、こだわった使い方ができる多機能な製品まで幅広いものが販売されています。さまざまな使い方ができる多機能なCRMは魅力的でもありますが、多機能であるほどコストがかかったり、不要な機能が多いと操作性が悪かったりといったデメリットも発生します。
そのため、自院・自社に必要な機能を取りまとめたうえで、CRMのベンダーに相談して選定していくと効果的です。
複数の候補を決めて比較する
CRMを選定する際は、一つの製品だけを見て決めることは避けましょう。
ベンダーの説明は魅力的に感じるかもしれませんが、複数の候補をピックアップして比較することで、より自院・自社に合ったCRMの導入が可能となります。
候補となった製品を導入している医療機関や企業の事例・口コミを参考にしながら、近隣の医療施設が使っているCRMのリサーチも行うとより効果的です。また、デモで実際に触れられる機会があるものは、積極的に活用して比較材料を集めましょう。
現場担当者の意見を重視する
CRMを導入する際は、実際にツールを使用する現場の担当者の意見を重視することが大切です。現場担当者の意見を反映せずCRMを導入した場合、使い勝手が悪くツールが定着しない可能性があります。業務効率を上げるためにCRMを導入するのに、ツールが使いにくいばかりに担当者に負担をかけてしまっては元も子もありません。
現場の課題点やツールに期待する機能などをヒアリングし、無料トライアルや体験デモを通じて実際の使用感を把握してもらうと失敗を避けられます。
顧客目線でCRMを選定する
CRMを活用する現場担当者が使いやすいツールであることはもちろん、顧客満足度の向上が期待できるツールを選ぶことでより効果を実感しやすくなります。
たとえば、CRMを導入した場合に患者の待ち時間をどれくらい短縮できるかシミュレーションすることで、医療サービスの質向上が期待できます。無料体験期間があるCRMツールを選べば、実際の使用感を確認したうえで選定できるでしょう。
CRMの選び方については、次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:CRMの正しい選び方とは?導入前に確認すべき5つのポイント
事前に社内の理解を深める
CRMを導入する際は、日常的にツールを活用する現場の担当者の理解を深めることが重要です。
よくわからないツールを渡され、「今日からこれを使ってね」と言われても、結局使わなくなってしまったり有効に活用できなかったりするでしょう。導入するメリットを事前に説明し、どのように活用できるかを理解してもらったうえで導入することで、ツールの定着を図れます。
また、CRMの導入直後は慣れないツールを使うことで、普段より手間が増える可能性もあります。導入前後の流れについても、担当者に周知しておくことでスムーズな導入が実現可能となるでしょう。
病院にCRMを導入する流れ
医療機関でCRMを活用する際、基本的な導入の流れは次のとおりです。
- 要件を定義し必要なシステムを選定する要件の定義とシステムの選定
- 実際に導入し運用していく導入準備と本格運用
- PDCAを回し業務の見直しや新機能追加を検討するPDCAサイクルによる評価と改善
それぞれのステップを詳しく解説します。
要件を定義し必要なシステムを選定する
CRMを導入することが決まったら、まずは自院に必要となる機能をピックアップして要件定義を行います。要件定義が曖昧だと、必要のない機能を持つCRMを導入してしまい使い勝手が悪くなったり、必要な機能がなく実務に使えなかったりと導入失敗になりかねません。
要件定義の後、必要な機能を兼ね備えたCRMを選定していく流れです。実際にCRMを利用する現場の担当者にデモを触ってもらい、要望などを取りまとめて選定すると失敗のリスクを低減できます。
ベンダーが決まったら、導入の初期費用やランニングコストなど、運用にかかる費用の見積もりを取って、予算と照らし合わせて契約締結へと進みます。
▶︎▶︎40以上の製品から自社にあったSFA/CRMが選定できる分類チャートはこちらから
実際に導入し運用していく
CRMは、導入すればすぐに使えるものではありません。使用する際は基本設定が必要で、ユーザーアカウントの作成やアクセス権限の設定など情報セキュリティを確保することも重要です。
また、既存の電子カルテシステムや受付システムとなど他のシステムとの連携、統合も行う必要があります。
基本設定が完了したら、既存の患者情報を新しいCRMシステムにデータを移行して正確性を検証した後、本格運用となります。
PDCAを回し業務の見直しや新機能追加を検討する
CRMを、導入前後は現場の担当者に対してトレーニングを実施することも重要です。基本的な操作方法の研修やマニュアル作成など、現場でCRMを活かせるような環境づくりを目指しましょう。
また、導入後はPDCAサイクルを回して効果や現場のフィードバックといった情報を収集し、業務の見直しや必要に応じた新機能の追加を検討します。評価に対して改善策を講じることで、CRMの有効活用につながります。
まとめ
医療業界が抱える人材不足や患者数の増加といった課題に対し、厚生労働省はIT化やDX化を推進しています。
CRMを導入すると患者情報など膨大な量のデータを一元管理できるようになり、業務を効率化できるため結果的に医療サービスの質向上にもつながることがメリットです。
ただし、CRMは多くの製品が販売されており機能もさまざま。自院に合ったCRMを選定することで、より効率的かつ有効的に活用できるようになるため、導入の際は信頼できるベンダーを選ぶことが重要です。
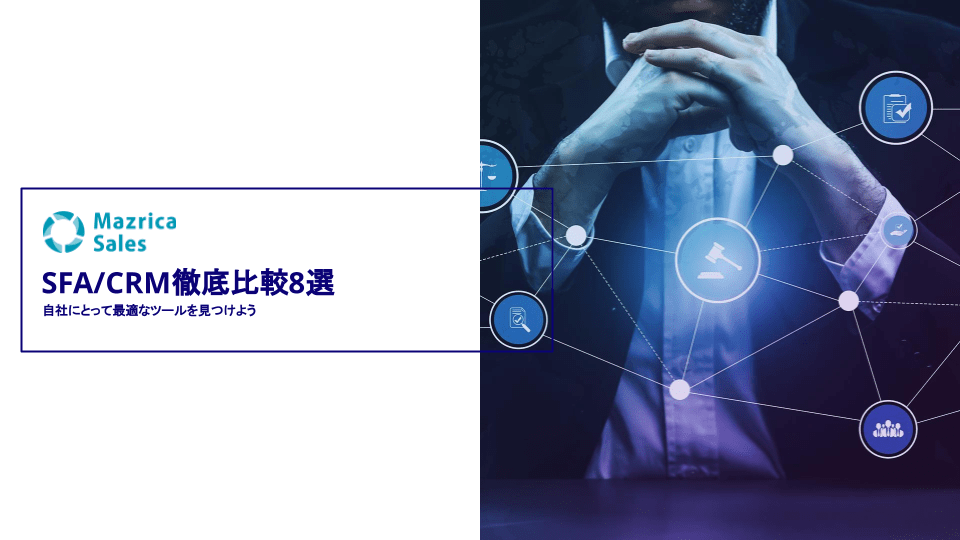
SFA/CRM徹底比較8選
SFA、CRMを導入したいけど、ツールの種類がたくさんありすぎて、それぞれの特徴や自社に合ったものがわからない…という方向けに、SFA/CRMツールを8つピックアップし、それぞれの特徴をまとめてみました。
資料をダウンロードする






















