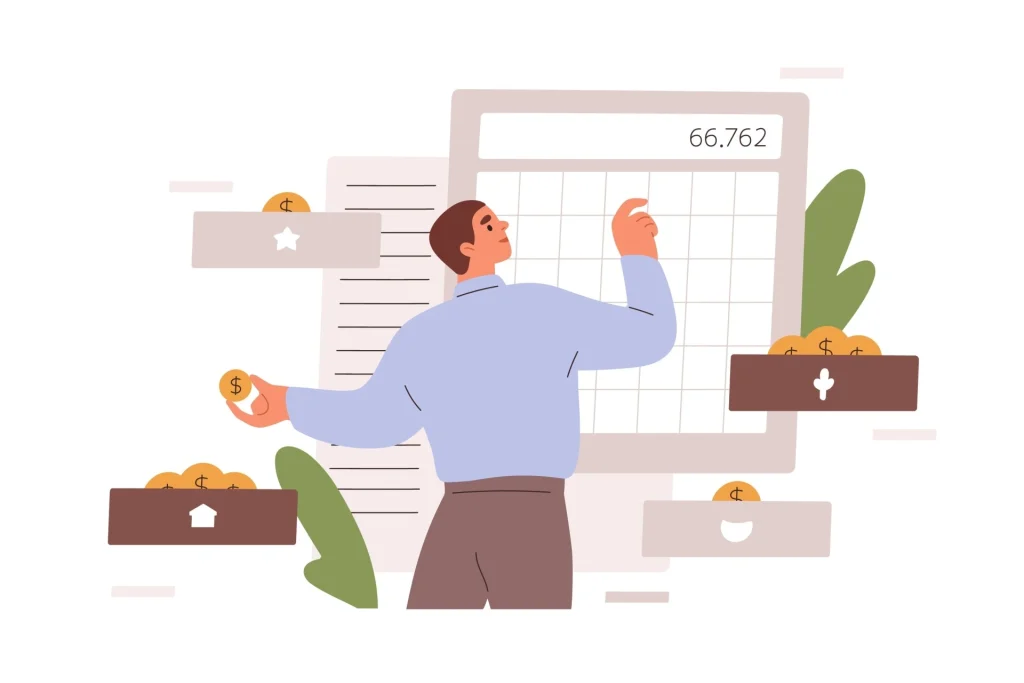近年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする機会が増えました。DXは、大企業だけでなく、中小企業にとっても事業成長の鍵を握る重要な経営戦略となっています。
しかし、「何から始めればいいのか」「本当に効果があるのか」といった疑問や不安から、DX推進に踏み出せない中小企業も少なくありません。
本記事では、中小企業におけるDXの本質的な意味から、今なぜDXがこれほどまでに求められているのかという必要性、そして、多くの企業が直面する課題とその解消策までを網羅的に解説します。
この記事の内容
中小企業のDXとは
近年注目されるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるデジタル化とは一線を画します。
中小企業にとってDXとは、ITやIoTなどのデジタル技術を導入するだけでなく、それらを活用して業務、サービス、商品、さらにはビジネスモデルそのものに変革を起こすことです。
DXの真の目的は、顧客へ新たな価値を提供し、市場での競争優位性を確立することにあります。
つまり、様々なITツールを導入する「デジタル化」はDXの手段に過ぎません。中小企業が目指すべきDXは、デジタル技術を梃子に、業務プロセスや企業のあり方を変革し、最終的に顧客に新しい価値を届けるという視点なのです。
関連記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義と成功事例を紹介
中小企業がDXが必要な理由
なぜ今、中小企業にとってDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略がこれほどまで
に重要視されているのでしょうか。
DXが脚光を浴びるきっかけは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」でした。
このレポートは、複雑化・老朽化した既存システムが残存することで、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性、いわゆる「2025年の崖」を警告し、DX推進をその解決策として提示しました。
当初は「レガシーシステム刷新」と誤解され、主に大企業中心の動きでしたが、現代では社会全体のデジタル化が加速し、企業規模を問わずDXの必要性が高まっています。
法制度改正への対応が喫緊の課題に
政府が推進するデジタル社会の実現に伴い、様々な法制度がデジタル対応を前提に改正されています。
例えば、改正電子帳簿保存法では電子取引データの保存が義務化され、単に保存方法を変えるだけでなく、業務プロセスの見直しも求められます。また、2023年に始まったインボイス制度においては「デジタルインボイス」の導入が進むなど、電子取引が主流となる流れは明らかです。
こうしたデジタル化の潮流に乗れない場合、コンプライアンス上のリスクだけでなく、業務効率の低下も招きかねません。
企業は遅くとも電子取引の電子データ保存が完全に義務化される2024年までには、ビジネスプロセスのデジタル化を進め、制度改正に適切に対応できる体制を整えることが必須です。
深刻化する人材不足への対策
少子高齢化が進行し、2025年には団塊世代が75歳以上の後期高齢者となり、日本の超高齢化社会が本格化します。
これにより生産年齢人口の減少が加速し、企業の人材不足問題は一層深刻化するでしょう。
限られた人材でいかに生産性を高めるかが問われる時代において、DXによる業務効率化は避けて通れません。
また、採用競争が激化する中、テレワークやオフィス環境のデジタル化といったDXの進捗度は、求職者が企業を選ぶ重要な要素となっています。
DX化の遅れは、労働力や生産性の低下を招き、人材確保や経営スピードに致命的な影響を与える可能性があるのです。
中小企業でDXが進まない理由
多くの企業がDXの重要性を認識する一方で、特に中小企業ではその推進に課題を抱えています。
ここでは、その上位4つの課題と、それぞれの解消策を具体的に解説します。
人材が足りない
中小企業がDX推進で直面する最大の壁の一つが、ITやDX推進に携わる専門人材の不足です。
2023年の調査では、「ITに関わる人材が足りない」が28.1%、「DX推進に関わる人材が足りない」が27.2%と高い割合を示しています。
この人材不足の背景には、専門人材の確保にかかる予算の確保が難しいという課題も深く関係していることが読み取れます。
解消策:社内人材の育成に注力する
外部からの専門人材獲得が難しい場合、社内人材の育成が有効な解決策となります。
未経験者や新卒を対象に、オンライン学習や外部教育機関を活用したIT・DX教育を施すことで、時間をかけて自社に合った専門人材を育成できます。
即効性は低いものの、長期的な視点で見れば、コストを抑えつつ持続可能なDX推進体制を構築し、企業の成長基盤を強化することにつながります。
予算の確保が難しい
「DXに取り組むに当たっての課題」として、「予算の確保が難しい」と回答した中小企業は24.9%に上り、人材不足に次ぐ主要な障壁となっています。
新たなシステムの導入や設備投資には多額の費用がかかるため、資金面での制約がDX推進の足かせとなるケースが多く見られます。
解消策:補助金・助成金の活用を検討する
予算不足を補うためには、国や自治体が提供する補助金や助成金の活用が非常に有効です。
DX推進助成金、IT導入補助金、事業再構築補助金など、DXに関連する様々な支援制度が存在します。
これらの補助金を活用することで、システム導入や設備投資にかかる初期費用を大幅に軽減し、コスト負担を抑えながらDXを加速させることが可能です。申請には準備期間を要するため、DX戦略の立案と並行して情報収集と準備を進めることが重要です。
効果や成果が見えない
DXへの取り組みは始めたものの、「具体的な効果や成果が見えない」という課題を抱える中小企業も21.0%に達します。
先行きの不透明さは、経営層や従業員のモチベーション低下を招き、DX推進の停滞につながる可能性があります。
解消策:先行事例を参考に具体像を描く
DXの具体的な効果や成果をイメージできない場合は、他社の成功事例を参考にすることが有効です。
同業他社や規模の近い企業のDX導入事例を調査し、どのような課題が解決され、どのような効果が得られたのかを具体的に把握しましょう。
経済産業省や中小企業庁などが公開している事例集などを活用することで、自社に当てはまるヒントを見つけやすくなります。
これにより、DXで何を目指し、どのような成果が得られるかを経営層だけでなく従業員全体で共有し、全社一丸となって取り組むための共通認識を醸成できます。
始め方がわからない
DXに取り組みたいものの、「何から始めてよいかわからない」と回答した中小企業は19.9%に上り、特に従業員20人以下の小規模企業では27.7%ともっとも高い割合を占めています。
DXの全体像が見えにくく、最初の一歩を踏み出せない企業が多いのが現状です。
解消策:まずは「デジタル化」から着手する
経済産業省の「DX支援ガイダンス」が示すように、DXへの道のりは「デジタイゼーション(アナログ情報をデジタル化)」「デジタライゼーション(デジタル技術で業務を効率化)」といった段階を経て「DX(ビジネスモデルの変革)」へと進みます。
まずは、既存業務の中でデジタル化できる部分を洗い出す「デジタル化」から着手しましょう。
例えば、紙の書類を電子化したり、手作業をソフトウェアに置き換えたりすることから始めます。
この小さな一歩が、DXの全体像を明確にし、その後の大きな変革へとつながる道筋となります。デジタル化を通じて得られる効率化を実感しながら、最終的にどのようなビジネスモデルの変革を目指すのか、その戦略を具体化していくことがDX成功への鍵です。
中小企業がDXを進める方法
中小企業にとってDX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビジネスを成長させるための重要な戦略です。
ここでは、DXを効果的に進めるための4つのステップを紹介します。
▶︎▶︎今すぐに始め方がわかる!営業DXの始め方の詳細はこちらから
DX戦略を策定する
DXの第一歩は、目的の明確化と全体戦略の立案です。
デジタル技術で何をどう変革したいのか、具体的なゴールを設定しましょう。
戦略策定と同時に、推進体制の構築も不可欠です。
予算に限りがある場合は、既存の社員で役割分担を検討したり、ITベンダーやITコーディネーターといった外部の専門家からの協力を仰ぐことも有効です。
DX推進の体制を整える
DXは全社的な取り組みであるため、特定の部署だけでなく、企業全体でDXを推進できる土台を整える必要があります。
DX推進チームだけでなく、現場の従業員一人ひとりがDXの意義を理解し、協力的になるよう浸透させることが大切です。
いきなり全社で進めるのが難しい場合は、まずは営業部門など特定の部署に絞ってDXを導入し、そこで成功事例を積み重ねてから、そのノウハウを全社に展開するスモールステップで進める方法も効果的です。
データ利活用を実施する
DXで新たな価値を創造したり、ビジネスを変革したりするためには、データの利活用が不可欠です。まずは、収集したデータを分析し、活用できる基盤を構築します。
データ分析の専門知識を持つ人材がいない場合でも、AIを搭載したSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールなどを導入すれば、AIが分析を自動化してくれるため、専門知識がなくてもデータの利活用をスムーズに進められます。
中小企業でDXを成功させるポイント
中小企業がDXを単なるデジタル化で終わらせず、変革を実現するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、その中でも特に大切な3つの要素について解説します。
経営陣が先頭に立って進める
DXの目的は、顧客に新たな価値を提供し、ビジネスモデルを変革することです。
この大きな目標に向かって何をどのように変えるべきか、その方向性を明確に示すのは経営層の役割です。経営層自らがリーダーシップをとり、DXの目的、具体的なゴール、実行プロセス、そして期待される効果までを明確にした全体戦略を策定しましょう。
従業員が変革に協力し、一丸となって取り組むためにも、この戦略を社内で共有し、納得感を持たせることが成功への第一歩となります。
すぐに成果を求めない
多くの中小企業では、DX推進のための予算に限りがあるのが実情です。そのため、一度に全てを変えようとするのではなく、スモールステップで着実に進めることが重要です。
まずは小さな成功を積み重ね、その成果を社内外に示すことで、次のステップへとつなげられます。
DX戦略を立案する際には、短期的な成果だけでなく、数年先を見据えた中長期的なゴールを設定し、段階的に実現していく計画を立てましょう。着実に歩みを進める姿勢が求められます。
中小企業のDXにおすすめのツール
中小企業がDXを成功させる上で、そのデータ基盤の中核となるのが、SFA/CRMの導入です。
SFA/CRMは、顧客情報だけでなく、営業活動の履歴(商談履歴、提案内容、顧客とのコミュニケーション記録など)やマーケティング活動のデータ(キャンペーン反応、Webサイト訪問履歴など)を一元的に蓄積・管理します。
これにより、これまでバラバラに管理されがちだった顧客に関するあらゆる情報を「見える化」し、営業担当者やマーケターが効率的にアクセスできる環境を構築します。
さらに、単にデータを集めるだけでなく、SFA/CRMは業務の効率化と自動化の面でもDXに寄与します。
営業担当者の日々の活動報告やタスク管理、見込み客のフォローアップなどを自動化し、ルーティンワークにかかる時間を削減します。
このように、SFA/CRMは中小企業がデジタル技術を活かして業務を変革し、顧客に新たな価値を提供するDXを実現するための、まさになくてはならない基盤ツールと言えるでしょう。
導入により、営業活動の効率化だけでなく、顧客理解を深め、競争力を高めることができます。
関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説
SFA/CRMを活用した中小企業のDX成功事例
最後に、弊社が提供するSFA/CRMのMazrica Salesで営業のDX化に成功した中小企業の事例を紹介します。
大道エンジニアリング株式会社

産業用電気機器の代理店販売を手掛ける従業員30〜50名の大道エンジニアリング株式会社は、ソリューション営業を強みとしていました。
しかし、営業情報の属人化や活動の可視化不足に課題を抱え、Excel管理ではノウハウが埋もれ、特に失注案件からの学びが得られない状況でした。こうした背景から、社長の金澤氏は、ソリューション営業のビジョンを現場に浸透させるには、営業環境そのもののデジタル変革が必要だと判断し、SFA/CRM導入によるDXへの舵を切りました。
同社は、SFA/CRMを単なるツールではなく、営業文化を変え、知見を共有する手段と位置づけ、約10社の中からMazrica Salesを選定しました。
決め手となったのは、忙しい営業担当者でも使いこなせる直感的な操作性と、案件進捗を視覚化する「案件ボード」でした。この案件ボードの活用により、従来の「日報」を撤廃し、営業生産性を劇的に向上できると判断しました。さらに、既存の名刺管理やMAツールとの連携性も重要な選定理由となりました。
Mazrica Sales導入後、同社はDXによる具体的な効果を実感し始めました。まず、営業プロセスの可視化が進み、案件ボード上でリード獲得やアプローチ段階の案件が少ないという、受動的な営業スタイルが明確になりました。
これにより、営業プロセスの初期段階への注力が必須であると認識を改めました。また、システム活用度合いが可視化されることで、マネージャー層は適切な指導が可能になり、組織全体の営業力向上に寄与しました。
社長の営業ビジョンもSFA/CRMを通じて情報の可視化・共有として実現され、デジタルを活用した企業文化の変革が着実に進みました。
SFA/CRMの定着にあたっては、「営業体制を変える」のではなく「入力する場所を変えるだけ」という説明で現場の抵抗を抑え、さらに、当時65歳だった営業課長が率先してツールを活用したことも、全社員の意識改革と定着を後押ししました。
参照記事:SFA/CRM運用の定着で日報を撤廃|デジタル化で進む営業ビジョンの浸透
株式会社パフ

人材コンサルティングを手掛ける従業員30〜50名の株式会社パフは、「顔の見える就職と採用」をポリシーに掲げ、新卒採用コンサルティングを展開する中小企業です。
同社は長年、Excelによる営業案件管理の限界に直面していました。リアルタイムでの状況把握が困難な上、特に「提案からクロージングまでのリードタイムが平均3ヶ月と長すぎる」という深刻な課題を抱え、顧客の熱量が下がり失注につながるケースも少なくありませんでした。
また、既存のSFA/CRMが顧客情報データベースの「入れ物」に過ぎず、案件管理が不十分で対応漏れが頻発し、複数のツールを併用することで管理が煩雑化していました。
このような状況を打開すべく、システム担当者からの問題提起をきっかけに、吉川社長がトップダウンでDX化を推進。10社以上のSFA/CRMを比較検討した結果、株式会社パフはMazrica Salesへの乗り換えを決定しました。
Mazrica Sales導入後、株式会社パフの営業プロセスは劇的に変化しました。最大の成果は、リードタイムが従来の3ヶ月からわずか1ヶ月へと、約1/3に短縮されたことです。
さらに、営業会議の準備時間が各営業担当者あたり30分〜1時間も削減され、会議自体も「状況報告の場」から「具体的な対策を議論する場」へと変革しました。
マネージャー陣はデータに基づいた的確なアドバイスが可能となり、成約率の向上にも寄与しています。
また、顧客データの一元管理により、手厚いフォローが必要な顧客を抽出し、営業担当者個別の「プライベートメルマガ」を配信するなど、顧客体験(CX)向上のための新たな取り組みも生まれ、商談獲得につながる好循環が生まれています。
参照記事:リードタイムが1/3に!Mazrica Sales(旧Senses)への乗り換えで実現した営業効率の大幅UP
まとめ
本記事では、中小企業におけるDXの必要性から、推進を阻む課題、具体的な進め方、そして成功のためのポイントまでを詳しく解説しました。
DXは単なるデジタルツールの導入ではなく、デジタル技術をテコに業務プロセスやビジネスモデルを変革し、顧客に新たな価値を提供することで競争優位性を確立するという、経営戦略そのものです。
SFA/CRMのようなデータ基盤ツールの導入は、営業活動の可視化と効率化、そして顧客理解を深める上で強力な武器となるでしょう。
以下は、中小企業の営業DXに特におすすめのSFA/CRM「Mazrica Sales」の資料です。気になった方はぜひDLしてみてください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI
資料をダウンロードする