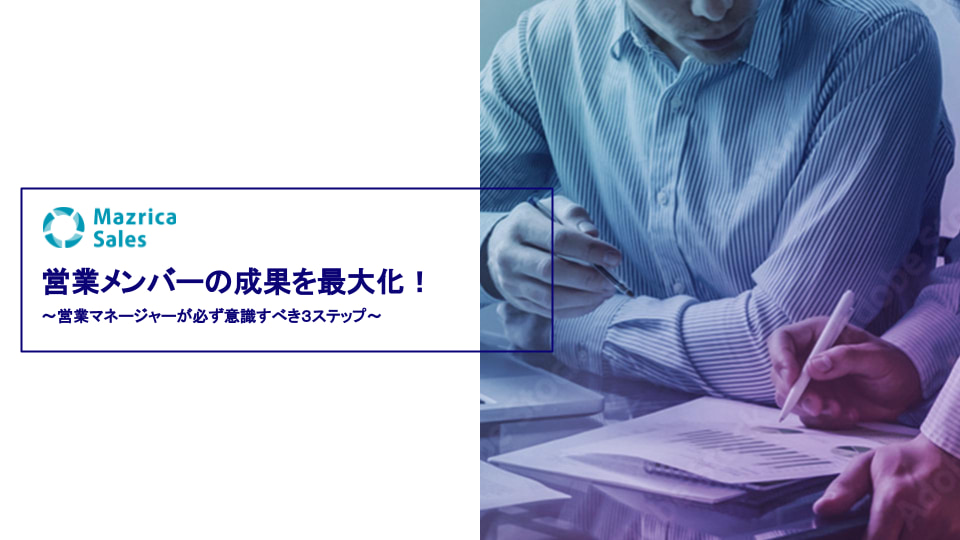同じ仕事をしていてモチベーションの高い社員と低い社員が生じてしまうのはなぜでしょうか。
社員のモチベーションが高ければ、好業績に結びつくことがわかっていますが、マネージャーとして、チームのモチベーションが低いと悩むケースも少なくありません。
今回は「そもそもモチベーションとは何か」ということを考え、組織で高い生産性に繋げるためのモチベーション管理方法をご紹介します。
この記事の内容
モチベーション管理とは?

モチベーション管理とは、社員のモチベーションを維持・向上させるための施策やプロセスを管理することです。
モチベーションとは、社員が目標に向かって行動するための内的なエネルギーのことで、一般的には「動機づけ」とも呼ばれます。
モチベーションの高い社員は自発的に業務へ取り組むことで、組織に対するコミットメントや会社への忠誠心が高く、顧客に対する貢献度も高い傾向があります。
業務に対する能力が高いということだけでなく、モチベーションを高い状態で維持管理することで仕事への成果が最大限引き出されます。
逆に仕事に対するモチベーションが低い社員は、業務に対する能力が高いとしても、やる気がない発言を繰り返したり、組織の他メンバーの士気を下げるような態度や発言をしたりと、業績に対して悪影響を与えやすくなります。
モチベーションの種類

モチベーションは「外発的動機付け」と「内発的動機付け」に分類されます。どちらも社員の行動意欲を高める要因です。
モチベーション管理を行う際には、これらの種類と内容を理解し、適切なアプローチを取ることが重要です。
外発的動機
外発的動機とはモチベーションの要因が「報酬」「評価」「懲罰」「強制」など人為的な刺激によるものです。
「報酬」の外発的動機づけがわかりやすいのですが、給与やボーナスを上げたとして一時的にはモチベーションが上がるかもしれません。
しかし、時間の経過とともにその効果は薄れてきます。
外発的動機づけは不足すると不満が出るが、満たしたからといって必ずしも高いモチベーションを維持できないことが多いと言われています。
内発的動機
続いて「内発的動機」ですが、こちらは行動要因が自分自身の内面から沸き起こった、興味や関心から業務へのモチベーションに結びついています。
外発的動機とは異なり、モチベーションの高い従業員は、この内発的動機が要因であることが多いです。
有名なモチベーション理論にアメリカの心理学者マズローが唱えた「欲求5段階説」があります。
一度は聞いたことがあるかもしれませんが、改めて考えたいと思います。
人の欲求は5つの階層があるという考え方に基づいています。
第1階層:生理的欲求
第2階層:安全欲求
第3階層:社会的欲求(帰属欲求)
第4階層:尊厳欲求(承認欲求)
第5階層:自己実現欲求
第1階層の生理的欲求とは、人が生きるために必要な「食べる」「飲む」「寝る」という基本的な欲求です。
第2階層の安全欲求とは、自分の身の安全や健康維持のための環境への欲求になります。
自分の身が危ないという環境で恐怖を感じ身を潜めたくなるのは、安全への欲求を求めているからです。
生きるために必要な材料や条件が整い、安全な場所に身を置ける環境となったら「仲間が欲しい」という第3階層の社会的欲求を求めるようになります。
個人から社会へ帰属したくなる欲求がこれに当てはまります。
仲間が集まり組織に属するようになると第4階層の尊厳欲求が現れます。
仲間の中に属するようになると、他の仲間から「認められたい」「尊敬されたい」という欲求のことです。
最後の第5階層、自己実現欲求とは自分の得意なことを活かしてこの社会(組織)の中で創造的な活動がしたいという欲求です。
この第1~5階層は仕事に当てはめることができます。
第1、2階層は基本的な欲求なので満たしているとモチベーションが高まるということはありえませんが、不足していると不満が溜まり良い結果にはなりません。
例えば、第1の欲求では食事も出来ない、トイレにもいけない、眠れないという環境でモチベーションが高まらないのは当たり前です。
しかし、この欲求を満たしたからといってモチベーションが大きく向上することもありません。
同じように第2欲求は安全な職場環境、適正な労働環境などへの欲求です。
生命の安全、労働環境の安全が満たされていても、社会から隔離された1人作業などをしていた場合は第3欲求を求めるようになります。
社会的に帰属したくなり、組織に対する一体感や人間関係への欲求です。
第4の尊厳欲求では上司から仕事を評価されることや、周囲から尊敬されることが考えられます。
そして最後の第5、自己実現欲求は自分の成長を実感したい、やりたい仕事で高い目標を達成したいという欲求になります。
この考え方は内発的動機づけと関連します。
例えば、報酬やボーナスを与えるのではなく「これはあなたにしか出来ない仕事です」と上司から褒められたり、認められたりすることで自己実現欲求が満たされ、モチベーションがより高まります。
自己実現欲求の満たされ方は人それぞれ異なります。
例えば、昇進することで周りから評価されていると実感する人もいれば、昇進に興味が無く技術を磨いてスペシャリストとして仕事することでやりがいを感じる人もいるでしょう。
マネージャーは部下一人ひとりの動機づけの要因を探り、メンバー個々にあった内発的動機づけをしてあげるようにしましょう。
モチベーションが下がってしまう原因

モチベーションの高い社員は自発的に行動し、顧客や他従業員にも良い影響を与え、業績の成長に直結します。
しかし、常にモチベーションが高ければ良いのですが、何かがきっかけとなってモチベーションが低下することもあります。
社員のモチベーションはなぜ低下してしまうことがあるのでしょうか。ここでは、その原因を解説します。
仕事に魅力ややりがいを感じられない
仕事に対するやりがいや充実感が感じられない状況が続くと、社員のモチベーションが下がる恐れがあります。
たとえば「仕事の内容が単調」「挑戦的なプロジェクトや成長の機会が提供されない」「自身のスキルや才能が生かされない」などの要因が考えられます。
このような状況を改善するためには、社員の希望する配置転換や業務の割り振り、適切な目標設定などを行うことが重要です。これにより、社員のモチベーションを維持しやすくなります。
給料や待遇に不満がある
仕事に対する充実感ややりがいがあっても、給料や待遇に不満があると、社員のモチベーションは低下しやすくなります。
例えば、仕事量に対して給料が不十分であったり、成果を挙げても昇給や昇進が見込めない場合、社員の不満や自社への不信感が高まる可能性があります。
適切な給料や待遇を提供し、仕事や成果に見合った報酬を与えることが重要です。また、キャリア成長に関するサポートを行うことで、社員のモチベーションを維持することができます。
人間関係に問題がある
職場の人間関係が悪化すると、社員は職場での安心感を失い、モチベーションが低下します。
上司や同僚との不和、コミュニケーションの不足、パワーハラスメント、差別、仕事上の対立などが原因となることがあります。
これらの問題は職場環境を悪化させ、社員のモチベーション低下やメンタル不調を招く可能性があります。風通しの良い職場環境を築くために、コミュニケーションを重視し、社員が安心して働ける環境を提供することが重要です。
労働環境が良くない
労働環境の悪さは、社員のモチベーションに大きな影響を与えます。 長時間労働や残業の常態化、適切な休息が取れない状況は、身体的な疲労や精神的なストレスを引き起こし、モチベーションを著しく低下させます。
有給休暇が取りにくい、あるいは休息時間が十分に取れない職場では、社員が疲弊してしまうでしょう。
業務量の見直しや福利厚生の充実など、健康的で快適な労働環境を提供することで、モチベーションの維持・向上が期待できます。
正当な評価が得られない
自身の努力や成果が正当に評価されないと感じると、モチベーションが低下しやすくなります。明確な評価基準がない、評価者によって評価がばらつく、フィードバックが行われないなどの評価制度では、公平性や透明性が担保されません。
人事評価に対して社員がどのような不満を感じているかを上層部が理解し、対応することが大切です。
モチベーション管理を行うメリット
モチベーション管理を行うことで、様々なメリットを得られます。ここでは、以下の点について詳しく解説します。
- 生産性の向上
- 適切な人材配置 離職率の低下
- 定着率の向上
生産性の向上
部下が高いモチベーションで仕事に取り組めば、高い成果を出すことを目指して質にこだわりながら業務を遂行し、効率化も進めるため、結果的に生産性が向上します。
生産性が向上すれば、安定した収益を得られ、企業の盤石な経営にもつながります。
適切な人員配置
モチベーション管理を行うことで、適切な人材配置が実現できます。 例えば、モチベーション低下の原因が人間関係や業務内容であれば、人間関係に悩まされない部署に配属したり、能力を最大限に発揮できる仕事を与えたりすることが可能です。
適切な人材配置により、部下一人ひとりの働きがいが向上し、企業の活気も増します。
定着率の向上
モチベーション管理を行うことは、定着率の向上にもつながります。 モチベーション低下の原因を見つけて改善することは、部下が働きやすい環境を整えることになります。
モチベーション低下の原因が改善され、部下一人ひとりが意欲的に働けるようになれば、離職率の低下とともに従業員満足度の向上も実現できるでしょう。
モチベーション管理を行う方法

効果的なモチベーション管理を行うためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、その具体的な方法について解説します。
アンケートなどで集まったデータを可視化する
まず、部下のモチベーションに関する内容をアンケートなどで調査し、集まったデータを可視化しましょう。
設問には、「今の仕事に満足しているか」「人間関係に困り事はないか」「待遇に不満はないか」などを含めます。 回答形式を数字で答えられるようにすれば、定量的に計測ができるのでわかりやすくなります。
アンケートは、回答してもらわないとデータとして収集できません。 答え忘れている人にはリマインドメールや呼びかけを行い、確実にデータを収集しましょう。
不満や要望に対する施策を実施
集まったデータから、仕事や人間関係に対する不満や要望を汲み取り、具体的な施策を実
施します。 例えば、人員配置の見直しや目標設定の変更など、部下のモチベーションを高めるための施策を検討し、実行に移します。
施策の振り返り
施策を実施した後は、部下のモチベーションにどのような変化があったかを必ず振り返りましょう。
モチベーションが上がった場合は、どの施策が効果的だったのかを分析し、逆にモチベーションが下がった場合は、施策のどの部分に課題があるのかを確認します。 このプロセスを繰り返し行うことで、施策の効果を最大化していきます。
データ収集から施策の実施、振り返りまでをひとつのサイクルとして、継続的にモチベーション管理を行いましょう。
モチベーション管理のポイント
モチベーションを高めるための方法は個人や状況によって異なるものの、一般的に効果的と言われる方法をいくつか解説します。
具体的に褒める
社員のモチベーションを高めるためには、達成した成果や努力を具体的に褒めることが重要です。
抽象的に褒めるのではなく、具体的な行動や成果に対して褒めるようにしましょう。 例えば、特定のプロジェクトでの貢献やスキルの向上を具体的に褒めます。
こうすることで、社員は「称賛される基準」が明確になり、同様の行動を取ろうとします。 具体的な褒め言葉は自信を高め、モチベーションの向上につながります。
適切な目標を設定する
モチベーションを維持するためには、達成可能な目標を設定することが必要です。 目標は具体的で、計測可能かつ達成可能な期限を設定することが重要です。
達成可能な目標を提示することで、社員は進捗を実感し、達成感を得られるため、モチベーションが向上します。
ただし、あまりにも簡単すぎる目標を設定すると「つまらない」と感じられ、モチベーションが低下する可能性があるため、注意が必要です。
メリハリをつける
仕事と休息のバランスを保つことは、モチベーションを高めるために重要です。 過度な労働やストレスは疲労を引き起こし、モチベーションを低下させる原因となります。
仕事とプライベートのメリハリをつけ、社員のワークライフバランスを整えることで、仕事への集中力や意欲を高めることができます。 余裕のあるスケジュールで業務を進め、不要な残業を削減する施策も有効です。
おわりに
仕事に対するモチベーションを維持する方法は、組織メンバーとの日頃のコミュニケ―ションを通じて、欲求を満たしてあげることが重要です。
特に報酬アップなどの外的要因よりも、自己実現欲求を意識した内発的な欲求を満たすことが有効です。
今回ご紹介したモチベーション管理の方法を、あなたの組織に取り入れられることから実践してみましょう。
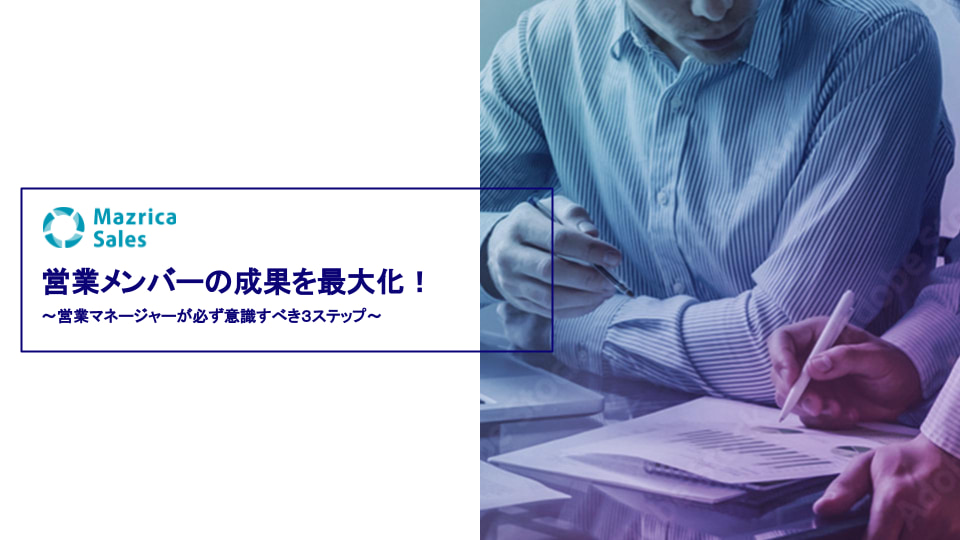
営業メンバーの成果を最大化! ~営業マネージャーが必ず意識すべき3ステップ~
セールスマネジメントのポイントとして戦略立案から部下のモチベーション管理まで3つの観点でまとめています。営業のマネジメントに関わる方向けの資料です。
資料をダウンロードする