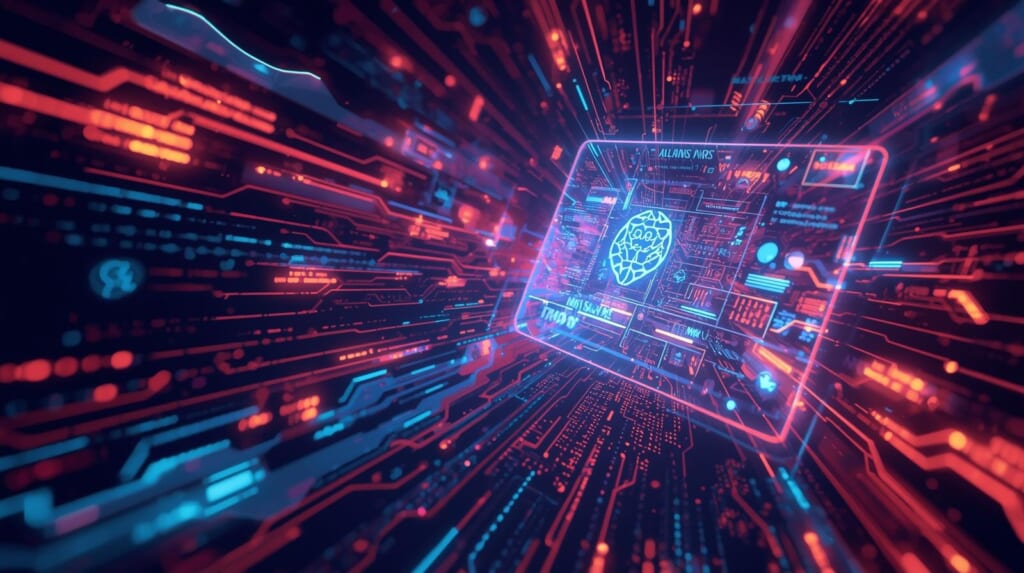CRM(顧客関係管理システム)を構築・導入すれば顧客情報を一元管理し、顧客対応を最適化できるため、将来的な売上向上につながります。
しかし、既存のCRMを導入するのではなく、ゼロから構築する場合、どのようにすれば良いのかがわからない企業担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、CRMの代表的な構築方法と導入形態、7つの構築手順をご紹介します。
CRM構築のポイントもご紹介しますので、自社での構築をご検討中の担当者の方は参考にしてください。
この記事の内容
CRMの構築方法
CRMを独自で構築する方法には、自社で構築する方法と、ベンダーに外注する方法があります。各方法の概要とメリット・デメリットを解説します。
自社で構築する
自社の業務や導入目的に沿ったオリジナルの機能を搭載したCRMを構築したい場合は、自社で構築する自社開発が最適です。
しかし、構築にはCRM構築の知見や経験に長けた専門のエンジニアが必要になり、開発プロジェクトも長期化になる傾向があります。
システムのアップデートやメンテナンスなどの保守・運用は自社で行う必要があり、継続的な人件費が発生します。
また、コストやエンジニア数の都合によりアップデートの頻度が減る場合は、セキュリティの更新が追い付かず、情報漏洩のリスクがある点に留意が必要です。
なお、既存のクラウド型サービスを使えばセキュリティが担保されます。
システム構築は容易になるものの、機能のアップデートには自社で構築する場合と同様に、自社での管理が必要です。
ベンダーに外注する
自社に専門知識を持ったエンジニアがいない場合は、外部のITベンダーに外注する方法をおすすめします。
ベンダーとは、顧客の要望に基づいて最適なCRMシステムを構築する企業です。
経験豊富なエンジニアがシステム設計から導入まで対応し、トラブル時のサポートも提供してくれるのが特徴特長です。
既に導入している業務システムからCRMへの移行サポートも行ってくれます。
ベンダーに外注する場合は、企業によって構築・サポートの対応範囲、開発・導入期間、初期費用やランニングコストが異なります。
事前に公式サイトや問い合わせで確認したうえで、自社の要望に沿う構築をしてくれるのか、費用対効果は高いのかを検討し、選定することが大切です。
CRMの種類
CRMの種類には、オンプレミス型とクラウド型があり、導入形態が異なります。
ここでは、各形態の特徴とメリット・デメリットを解説します。
オンプレミス型
オンプレミス型とは、自社でハードウェアを購入し、サーバーを構築した環境にCRMをインストールする導入形態です。
オンプレミス型CRMツールの導入にあたっては、自社専用のCRMシステムを開発する方法と、既存のCRMシステムを自社サーバーで運用する方法の2種類があります。
自社専用のCRMシステムを開発すれば、自社の業務内容や導入目的に適した独自のカスタマイズが可能になります。
オンプレミス型では、自社開発と既存のCRMのどちらであっても自社サーバーで運用するのでセキュリティ対策を取りやすく、取り扱う情報の安全性に優れているのが特長です。
ただし、システム構築の費用やサーバーの保守・管理費用など、CRMの運用にあたって多額のコストがかかる点やシステム構築やCRM運用に知見のあるIT人材が必須である点がデメリットです。
関連記事:オンプレミスとクラウドを比較!特徴や移行・併用のポイント
クラウド型
クラウド型は、ベンダーが提供するオンラインシステムにアクセスすることで全機能を利用できるサービスを利用してCRMを導入する形態です。
クラウド型のメリットは、インターネット環境と端末があれば、時間や場所を問わず利用可能な点で、バックアップも自動で行われます。
また、自社でサーバーなどのインフラを整備する必要はないため、初期費用や保守・管理などの費用が抑えられます。
一般的には、保守・管理はベンダーが行い、導入側は月額利用料を支払ってサービスを利用するため、利用が長期にわたる場合は、オンプレミス型よりもコストがかかる可能性があります。
クラウド型のデメリットは、機能やセキュリティ対策がベンダーに依存する点です。
オンプレミス型に比べてカスタマイズ性に乏しいため、サービス内容に業務内容を合わせなければなりません。
また、セキュリティ対策はされていても自社が求める要件を満たさない可能性があるため、情報漏洩を防ぐなど、安全性を確保するためのルール策定が必要です。
▶︎▶︎CRMツールごとの違いについてより詳しく知りたい方は併せてこちらの資料もご覧ください。
CRMの構築手順
CRMの構築は、次の7つの手順で進めます。
- 全体的なルールを決める
- 現状の業務や課題を把握する
- 改善策を立案する
- 運用方法を検討する
- トライアルを利用する
- 社内研修・教育を行う
- 効果を検証し改善する
CRMの成果を最大化できるように、システムの構築面だけでなく、チーム編成やルール設定など社内の環境整備も意識してください。
関連記事:CRMの使い方とは?導入前にやるべきことや得られる効果も紹介
全体的なルールを決める
CRM構築にあたっては、社内の各部門を含めた全体的なルールを決めます。なぜなら、CRMの導入には、社内全体の取り組みが重要だからです。
具体的には、営業やマーケティング、経営本部などからリーダーを招集し、導入チームを組織しましょう。
各部門ではCRMの業務への取り入れ方や分析結果からのアプローチ戦略が異なるため、構築の始めに全体的なルールを決定しておくことで、プロジェクトを推進しやすくなります。
ただし、部門それぞれの意見を吸い上げすぎては、収集がつかなくなります。
各部門の意見を尊重しつつも部門間での連携を重視し、各チームが独立しない体制を整えて、CRMの構築・導入による業務改善という共通のゴールに向かって協力することが大切です。
現状の業務や課題を把握する
CRM構築を進めるには、現場の業務や課題を洗い出す必要があります。
例えば、営業であれば現状の業務のワークフローや営業活動のプロセスを見直し、PDCAを回して課題を特定してください。
各部門で業務内容や課題を把握できれば、導入すべきCRMのシステム構成や種類、欲しい要素、機能を洗い出し、自社の必要とする要素を持つCRMを選定します。
現在のシステム構成ではCRMの導入が難しい場合は、各部門において環境整備が必要になることも考慮しておくと良いでしょう。
改善策を立案する
現状の業務や課題を特定できれば、それらに対する改善策を立案します。CRM導入の目的と戦略を明確にすることが大切です。
PDCAフレームワークを活用して課題を発見し、改善策を立案しましょう。
PDCAを回す際は、プロセス達成におけるKPI(重要業績評価指標)を定めることをおすすめします。
適宜確認しながらPDCAを回し、進行具合を確認してください。
プロセスを進めるとともに、CRMに求める要素を洗い出しておくと、導入後の業務に取り入れやすくなります。
運用方法を検討する
自社に適したCRMツールを選定するには、オンプレミス型とクラウド型のどちらを導入するのか、また自社開発を行うのかといった運用方法の検討も必要です。
自社サーバーで運用するのであればオンプレミス型、インターネット上で操作できる便利さを重視するのであればクラウド型が選択の判断基準となります。
ツール選定時は、初期費用やランニングコストなどの費用面で比較することが多いでしょう。
確かに費用対効果を検討することも大切ですが、近年問題となりやすい情報漏洩リスクへの対策や現場導入のしやすさの観点から、セキュリティ面や操作性を考慮することも重要です。
なお、既製品では自社が求める要素が少ない場合や、反対に不要な機能が多い場合もあります。
このようなケースでは、カスタマイズ性に優れた自社システムの構築をおすすめします。
トライアルを利用する
CRMツールの選定は、操作の難易度や業務への取り入れやすさを重視することも大切です。
いかに機能性や操作性に優れていても、現場に定着しなければ導入の意味がないからです。
検討中のツールにトライアルやテスト運用期間が設けられている場合は積極的に利用しましょう。
トライアル時は、以下の点を確認してください。
- 操作のしやすさ
- 画面の見やすさ
- ほかのデバイスからのアクセスのしやすさ・操作性
- ほかのツールとの連携可能性
トライアルを通じて、現場の従業員が使いにくいと感じた場合や外出先での操作が複雑な場合は、他のツールを検討することも大切です。
SFAやMAなどのほかのツールとの将来的な連携性も考慮して選定すると良いでしょう。
社内研修・教育を行う
CRMを円滑に運用するには、導入前に社内研修・教育を行い、全員が使用できる環境を整えておくことも重要ですおきます。
CRMの導入により、業務プロセスやワークフローが変わってしまう場合は、現場からの反発によって運用が定着しない可能性があるからです。
特に、マネージャーや上司は操作方法への理解を深め、部下へのサポート体制を準備しておく必要があります。
また、全社で導入する際は、全体的な運用ルールを設定して運用の統一性を図りましょう。
すべての部門に共通する入力ルールやテンプレートなどを設定したうえで役割を明確にすれば、導入後の運用が定着しやすくなります。
効果を検証し改善する
CRMの効果を最大化するには単に導入するだけでなく、目標を設定したうえで導入効果を検証し、課題があれば改善することが不可欠です。
PDCAサイクルを回すことで課題が可視化され、導入の効果を評価できます。
課題発見だけでなく、より効果が得られるよう改善を繰り返して、導入評価をさらに高めましょう。
▶︎▶︎CRMツールがもたらすメリットについてより詳しく知りたい方は、こちらの資料もご覧ください。
CRMを構築する際のポイント
CRMを構築する際は、以下のポイントを意識することで、より効果的に運用できます。
- 管理者や運用責任者を任命する
- 従業員・顧客双方の使いやすさを確認する
- 最小規模から導入を進めていく
- ベンダーのサポートを利用する
ここからは、各ポイントを具体的に解説します。
管理者や運用責任者を任命する
CRMを構築し導入する際は、システムの管理者や運用責任者を任命することが重要です。
特に、自社開発やオンプレミス型のCRMを構築する場合にトラブルが起こった際は自社で対応する必要があるため、システム管理者を常駐させるのが望ましいでしょう。
また、ベンダーが開発・提供するクラウド型やパッケージ型のCRMを導入する場合でも運用責任者の設置をおすすめします。
社内活用の窓口としてだけでなく、トラブル発生時の指示役として動ける人材を確保しておくことが大切です。
関連記事:CRM設計とは?シナリオ設計の手順やポイント・おすすめCRMを紹介
従業員・顧客双方の使いやすさを確認する
CRMの運用定着を進めるには、社内の環境整備だけでなく、顧客側のUI(ユーザーインターフェイス)の最適化を図ることも重要です。
UIとは、企業と顧客との接点を指します。
例えば、Webサイトに問い合わせフォームを設ける際に、ユーザーにとっての入力のしやすさや、導線がわかりやすいサイト構築になっているかを確認しておきましょう。
社内だけでなく、顧客目線に立った確認をしておくことで顧客体験を向上でき、より効果的な運用を目指せます。
最小規模から導入を進めていく
CRMの導入に不安がある企業は、最小規模から始め、都度導入を進めるスモールスタートがおすすめです。
なぜなら、高機能なCRMを企業全体で導入したとしても、使いこなせず運用が定着しない可能性があるからです。
また、どれだけ準備をしていても、導入後にどのような変化が起こるかは予想できないため、費用を無駄にしてしまう可能性があります。
CRMの効果検証を確実に行うには、初回導入を1チームで行うと良いでしょう。
ユーザー数を絞ることで、導入・運用費用を最小限に抑えつつ、効果的な検証を進められます。
運用する過程で欲しい要素が見つかれば段階的に導入し、さらにPDCAを回して効果を検証していくと良いでしょう。
CRMの導入については、次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:CRM導入の成功事例5選|課題・運用方法・効果・導入時のポイント
ベンダーのサポートを利用する
CRMの運用ではベンダーが提供しているサポートを利用するのもおすすめです。
なぜならCRMの導入には、社内のシステム管理者や責任者が必要になる一方で、人件費や労力がかかるからです。
ベンダーが提供しているサポートサービスを利用すれば、操作方法やトラブルに対応可能です。
また、サポートを利用していればベンダー側で定期的な保守やアップデートが行われるため、常に最新のシステム環境でCRMを利用できます。
また、休日などにトラブルが起こった場合でも対応してもらえるなど社内でのシステム当番が不要になるため、その労力を別の業務に回せるメリットも得られます。
▶︎▶︎より具体的なCRMの活用方法について詳しく知りたい方は、こちらの資料も併せてご覧ください。
まとめ
CRMの構築方法には、自社で構築する方法とベンダーに外注する方法の2つがあります。
自社での構築は独自のカスタマイズができる一方で、保守管理を自社で行わなければなりません。
一方、ベンダーに外注する場合は、経験豊富なエンジニアがシステム設計から導入までを担当し、サポート対応も受けられます。
ただし、ベンダーにより対応可能な範囲やシステムの構築・導入期間が異なる点に注意が必要です。
自社でCRMを構築する際は、各部門で連携し全体的なルールを決め、運用ルールを定めることが大切です。
また、自社に最適なシステムを選定するには、現場の業務や課題を洗い出し、必要な要素を絞り込み、運用方法を検討しましょう。
本記事でご紹介した4つのポイントも参考にして、自社に適したCRMを構築してください。
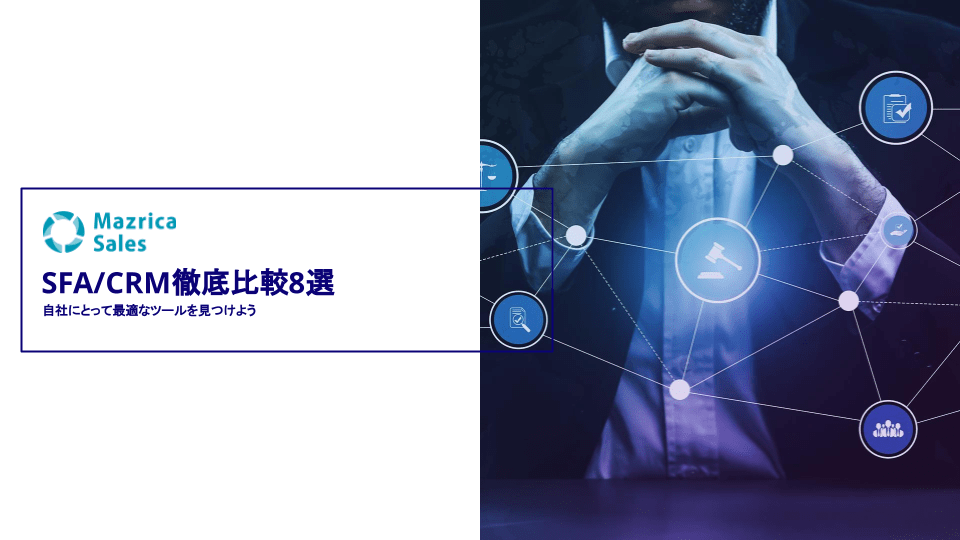
SFA/CRM徹底比較8選
SFA、CRMを導入したいけど、ツールの種類がたくさんありすぎて、それぞれの特徴や自社に合ったものがわからない…という方向けに、SFA/CRMツールを8つピックアップし、それぞれの特徴をまとめてみました。
資料をダウンロードする