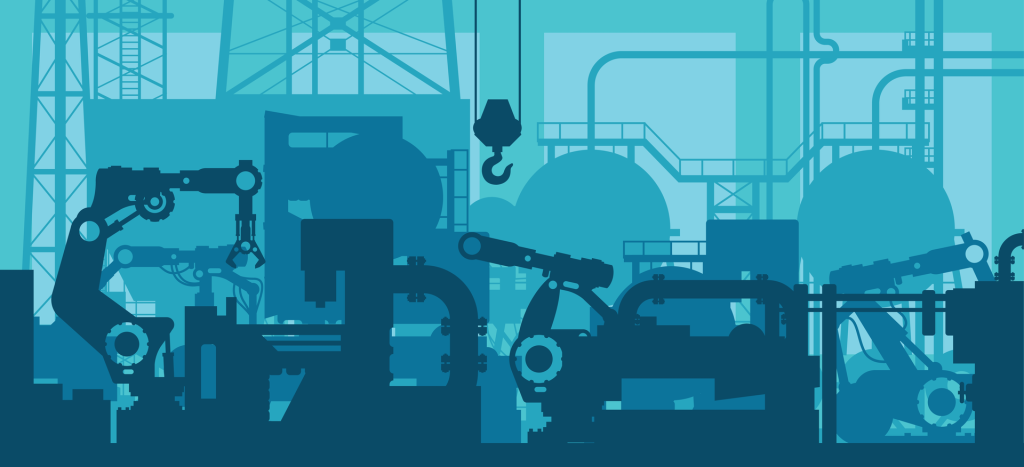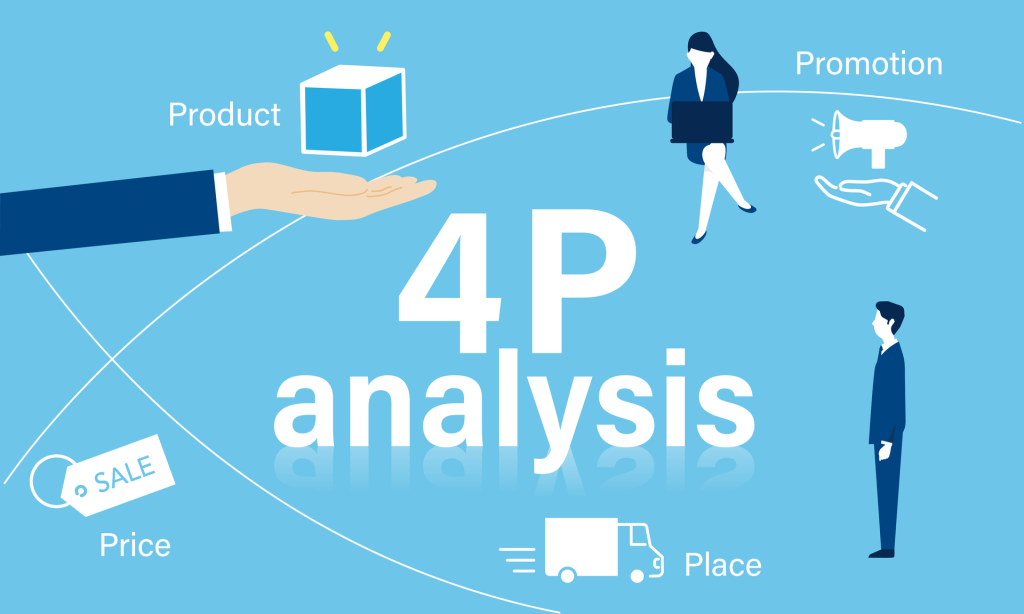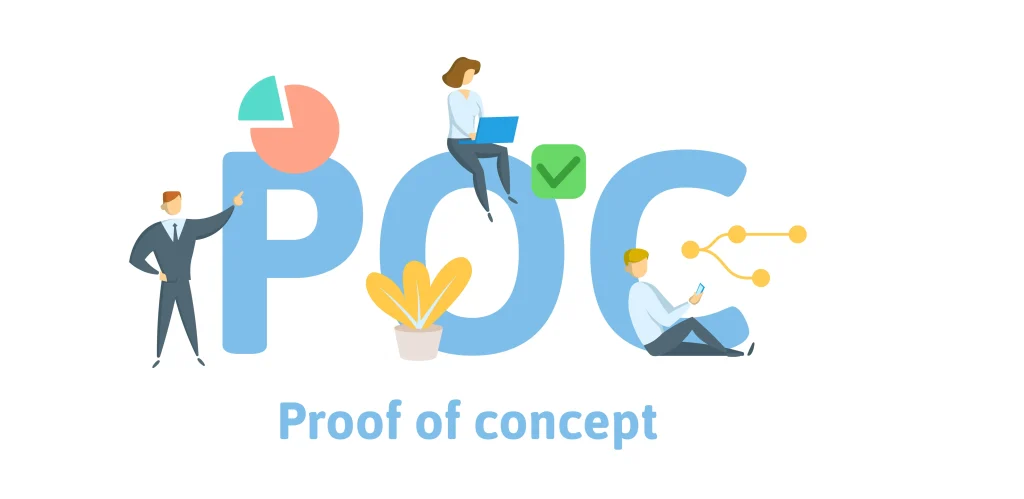OKRという言葉を耳にする機会が増えているものの、他の指標の違いや導入手順について明確なイメージを持てず、活用方法がわからないという声に心当たりのある方も意外と多いのではないでしょうか?
本記事では、OKRの基礎知識から、KPI・KGI・MBO(目標管理制度)との違い、組織での導入方法、運用を成功させるためのポイントを網羅的に解説します。
営業職やマーケティング職における具体的なOKRの設定例も紹介しますので、目標設定によって組織の成果を最大化する実践的なヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の内容
OKRとは?
OKRとは「Objectives and Key Results」の略称であり、組織や個人が達成したい「目的(Objective)」と、それを測定するための「成果指標(Key Results)」を組み合わせて設定する目標管理の手法です。
OKRの特徴は、単なる数値目標の達成を目的とするのではなく、「何のためにその目標を目指すのか」という目的を明確にした上で、3〜5つ程度の達成基準を定める点にあります。
到達すべきゴールを従業員一人ひとりが共通認識として持つことで、方向性を共有しながら自発的に行動する組織体制を構築することができます。
OKRが注目される理由
OKRが企業に広く導入されるようになった背景には、変化の激しいビジネス環境への適応力が求められている現状があります。
従来のトップダウン型の目標管理では、柔軟な対応が難しく、個人やチームの自律的な成長が阻害されることも少なくありませんでした。
OKRは、目標を定期的に見直しながら、社員のチャレンジ精神を促すことができる点で、変化に強い組織づくりに効果的です。特に、短期間(四半期など)で運用を回し、成果に応じて素早く軌道修正できるため、柔軟性の高い組織運営を実現しやすくなります。
また、OKRは組織全体で共有されるため、部署間の連携やチームワークを強化する効果も期待できます。
共通のゴールに向かって協力し合う文化が醸成されることで、社員のエンゲージメント向上にもつながります。
OKRと類似指標の違い
OKRのように目標管理には様々なフレームワークがあり、OKRと似た指標として「KPI」「KGI」「MBO」の3つが挙げられます。
目的に応じた適切な手法を選ぶことが重要なため、各指標のOKRとの違いを解説します。
KPIとの違い
KPI(重要業績評価指標)とは、組織や個人の業務パフォーマンスを定量的に測るための指標のことです。売上件数、サイト訪問数、成約率などがその例にあたります。
KPIは主に「定めた目標に対して、どの程度達成に近づいているか」を把握するための“進捗管理”の道具であり、日常業務の管理や評価に適しています。
OKRはKPIよりも上位の概念であり、KPIが「何をどれだけやったか」を追うのに対し、OKRは「なぜその目標を追うのか」まで含めて全体の方向性を明確にする点が大きな違いです。
関連記事:KPIとは?基本から設定方法、業種別の指標事例まで徹底解説
営業活動におけるKPIの設定や管理には、SFA(営業支援システム)が有効です。SFAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説
KGIとの違い
KGI(重要目標達成指標)は、最終的な成果やゴールを定量的に表す指標です。例えば「四半期売上1億円の達成」や「年間契約継続率95%」などが該当します。
KGIは企業のビジョンや中長期計画と強く結びついており、最終的な評価に使用されることが一般的です。
OKRは、より短期的かつ柔軟な運用を前提としており、チームや個人の成長を促す仕組みとして使われます。
KGIが「ゴールそのもの」であるのに対し、OKRは「ゴールに至るための道筋を明確にする枠組み」と位置づけるとイメージしやすいでしょう。
関連記事:KGIとは?KPIとの違い、設定するメリットと具体例を解説
MBOとの違い
MBOは「Management by Objectives(目標による管理)」の略称であり、上司と部下が合意した目標に対して業務を進め、その達成度合いに応じて評価や報酬を決定する制度です。多くの日本企業でも人事評価制度の形式として採用されています。
MBOは人事評価と密接に結びついているため、目標の達成度がそのまま給与や昇進に影響を与えることが多く、無難な目標設定に陥りやすいという側面もあります。
一方、OKRは評価や処遇とは切り離して運用するケースが多く、「挑戦的な目標」を設定することで、社員の主体性や創造性を引き出すことに重点を置いています。
MBOが管理・評価のための仕組みであるのに対し、OKRは成長と挑戦を支える目標管理手法という違いがあります。
関連記事:MBO(目標管理制度)とは?メリットや目標設定の方法を解説
OKRを導入するメリット
OKRは、単なる目標設定のフレームワークにとどまらず、組織運営や人材マネジメントにさまざまな効果をもたらす仕組みです。
以下では、OKRを導入することで得られる代表的な4つのメリットを紹介します。
重要課題を明確にできる
OKRの設計では、まず「何を成し遂げたいのか」という目標を定義し、その実現に向けて必要な具体的な成果を明文化します。このプロセスを通じて、経営課題や事業上の優先事項が明確になります。
例えば、事業拡大を目指す企業では「新規顧客の獲得」や「既存顧客のリピート率向上」といったテーマが目標として設定されます。曖昧だった重点施策が言語化されることで、組織全体で向かう方向が一致し、判断や行動に迷いがなくなります。
仕事の優先度を明確にできる
OKRでは、目標と成果指標の紐づけにより、「今、最も注力すべき業務」が明らかになります。
すべての業務に同じエネルギーを注ぐのではなく、成果に直結する活動に集中することが可能になります。
例えば「顧客満足度を高める」という目標に対して「サポート対応の満足度スコアを80%以上に向上させる」といった成果指標が設定されると、関連性の薄い業務よりも顧客対応の質向上に力を入れるべきだと判断できます。
このように、業務の取捨選択がしやすくなり、リソースの無駄を削減できます。
社員のエンゲージメントが向上する
OKRの仕組みでは、チームや個人ごとに目標を設定し、全体の方針と連動させることが一般的です。
組織の目標が一方的に押しつけられるのではなく、個々の役割や関心に沿った形で反映されることで、メンバーひとりひとりに当事者意識が生まれます。
また、成果の達成が処遇に直結しない設計である場合が多く、失敗を恐れずに挑戦する文化が根づきやすくなります。
挑戦の機会が与えられることで、社員のモチベーションや満足度が高まり、離職率の低下にもつながります。
社内コミュニケーションが円滑になる
OKRは、目標と成果が全社的に共有される形式をとるため、他部署や他チームの取り組み内容が見える化されます。
この可視化により、連携が必要なタイミングや相手が明確になり、業務のスムーズな進行が期待できます。
例えばマーケティング部門と営業部門がそれぞれのOKRを開示することで、「リード数を◯件獲得する」という目標と「商談化率を◯%にする」という目標の関連性が見えるようになり、共通のゴールに向けた連携が生まれます。
結果、無駄な確認作業やすれ違いが減り、社内のコミュニケーションが活性化されます。
OKRの導入・運用手順
OKRの効果を最大限に引き出すには、段階を踏んだ導入と継続的な運用が重要です。
組織全体から個人の役割まで目標を連動させるための基本ステップを4つに分けて紹介します。
全社でOKRを設定する
最初のステップは、経営層が主導して全社的なOKRを策定する段階です。
経営戦略や中長期のビジョンをもとに、提供価値や進むべき方向性を明確にし、目的と成果指標を具体的に定義します。
全社レベルのOKRは、各部門や個人が目指すべき方向の基盤となります。
全体方針が明文化されることで、現場で設定されるOKRとの整合性が取りやすくなり、統一感ある目標体系が実現します。
部門毎にOKRを設定する
全社OKRをもとに、営業・マーケティング・開発など各部門で独自のOKRを策定します。各部門の役割に応じた目標と成果指標を明確にし、組織全体との方向性が一致するよう調整します。
部門内での目標設計では、単なる数値の管理ではなく、業務がどのように組織成果に貢献するかという視点を持つことが重要です。
役割に基づいた戦略的なOKR設計により、部門間の連携や協働も促進されます。
個人のOKRを設定する
部門で策定されたOKRを踏まえ、各社員が自分の業務内容に応じたOKRを設定します。上司との対話により期待される役割や成果を明確にし、自律的に取り組むための目標と指標を整えます。
個人レベルのOKRにより、日々の業務が組織の方針とどのようにつながっているかが見えやすくなります。
主体的な行動が促されると同時に、自身のキャリア成長を見据えた目標達成への意欲も高まります。
期間終了後に見直しを行う
OKRは一度設定したら終わりではなく、一定の期間ごとに進捗を振り返る仕組みが必要です。
四半期や半年といった区切りで成果を確認し、次回のOKR策定に向けて改善点や成功要因を整理します。
振り返りによって、達成状況だけでなく、取り組み姿勢やプロセスにも目を向けることができます。
実行内容を言語化して共有することで、次の成長につながる学びが得られます。
OKRの運用を成功させるポイント
OKRの仕組みを導入した後、成果につながる運用を実現するには「実践面での工夫」と「組織文化の整備」が欠かせません。
OKRの効果的な活用を支える具体的な4つのポイントを解説します。
目標設定から成果までをオープンにする
OKRの本質は、目標と成果指標を組織全体で共有し、方向性をそろえる点にあります。
全社・部門・個人のOKRを互いに開示することで、各チームの目的や進捗が可視化され、業務の重複や連携不足を防げます。
共有の仕組みとしては、社内ポータルへの掲載や週次ミーティングでの進捗発表などが効果的です。情報の透明性が高まることで、部門を越えた相互理解が深まり、チームワークの質も向上します。
▶▶SFA/CRMとグループウェアツールの連携メリットや連携詳細はこちらの資料をご覧ください
チャレンジングな目標で社員のやる気を引き出す
OKRでは、現状の延長線上では届かない高い目標を掲げることで、社員の潜在力を引き出すことが期待されています。
確実な達成を目指す目標ではなく、努力次第で到達できる水準を設定することが望ましいです。
例えば、売上の前年比120%を目指す目標や、プロジェクトの納期短縮など、達成が難しい数値であっても挑戦意識が生まれやすくなります。
難易度の高い目標に真剣に取り組む姿勢は、組織全体の成長スピードにも良い影響を与えます。
処遇や昇進とは切り離して運用を行う
OKRの成果を人事評価や報酬と強く結びつけると、社員が達成しやすい目標を選ぶ傾向が生まれます。
挑戦する姿勢よりも「失敗しない」ことを優先するようになり、組織としての成長が鈍化します。
より大きな成果を生み出すためには、OKRの達成状況と評価制度を分けて運用することが効果的です
目標に至るまでのプロセスや挑戦の内容に注目し、評価は別軸で行う仕組みを整えることで、自由で創造的な目標設定が可能になります。
定期的な対話とフィードバックで進捗を支援する
OKRは設定後のフォローが非常に重要です。進捗確認を兼ねた1on1面談やチーム内の共有ミーティングを定期的に実施することで、課題の早期発見や方向修正がしやすくなります。
会話の中で、取り組みの背景や達成に向けた工夫などを言語化する機会が増えると、個人としての学びが深まり、次回の目標設計にも良い影響が期待できます。
進捗だけでなく、思考や姿勢にも焦点を当てた対話が、健全なOKR運用を支える基盤となります。
職種別のOKR具体例
OKRの効果を高めるには、業務内容や担当領域に応じた適切な設計が重要です。具体例として、営業職とマーケティング職におけるOKRを紹介します。
自社の業務に合わせた活用のヒントとしてご活用ください。
営業
営業部門では、売上や顧客との関係構築に関する指標が中心となります。ただし、単なる件数目標ではなく「どのような営業活動によって価値を提供するか」という観点が重視されます。
目的(Objective)
- 新規顧客との信頼関係を築き、受注率を向上させる
主な成果(Key Results)
- 初回訪問から提案提出までの期間を平均5営業日以内に短縮する
- 提案内容のカスタマイズ率を80%以上にする
- 月間の商談成約件数を15件以上にする
OKRによって活動の質と成果の両方を明確にすることで、数字の達成だけに偏らない目標設定が可能になります。
マーケティング
マーケティング部門では、リード(見込み顧客)獲得やブランド認知の拡大に関する目標が設定されることが多くあります。各施策が全体戦略とどのようにつながるかを意識することがポイントです。
目的(Objective)
- ウェブ経由の問い合わせ件数を増やし、営業活動を支援する
主な成果(Key Results)
- 月間コンテンツ発信数を8本に増加させる
- 検索流入を前月比30%増加させる
- 問い合わせフォームのCVR(コンバージョン率)を2.5%以上に改善する
成果指標にはアクセス数や件数だけでなく、コンテンツの質や改善の成果も含めることで、マーケティング活動全体の貢献度を可視化できます。
まとめ
OKRは、目標管理を通じて組織の一体感を高め、挑戦と成長を後押しする強力なフレームワークです。
目的と成果を明確にすることで、業務の方向性がはっきりし、組織内での連携もスムーズになります。
営業・マーケティングといった各職種でも応用が可能で、日々の行動と組織の成長を結びつける仕組みとして機能します。
ただし、導入や運用を軌道に乗せるには、正しいステップを踏み、継続的な対話と振り返りを重ねることが欠かせません。
単に目標を掲げるだけではなく、現場の理解と納得感を高めながら運用する姿勢が、成果を最大化するカギとなります。
自社の営業活動が今どのレベルにあるのか、目標設定の観点から見直したい方には「到達度診断シート」もオススメですので、ぜひダウンロードして振り返りにご活用ください!

毎期目標達成する企業がやっている営業改革12項目 営業組織の到達度診断シート
あなたの営業組織はどのレベルまで到達できていますか? 毎期目標達成する企業は、実は様々な営業改革を行っています。本資料は、そんな重要12項目を今すぐ営業組織を診断できるシートです。
資料をダウンロードする