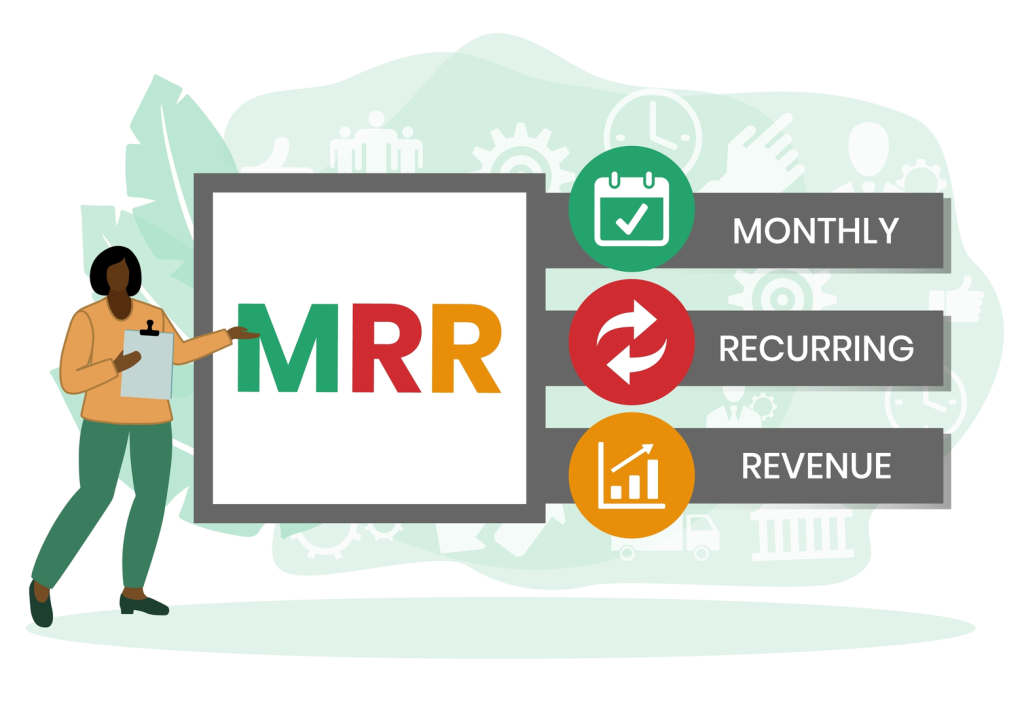近年、多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されています。その中でも、ビジネスのあり方を根本から変える概念として注目されているのが「デジタルファースト」です。
デジタルファーストという言葉を耳にしたことはあっても、具体的な意味や自社でどう始めればいいか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、デジタルファーストの基本から、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、概要や始め方を知りたい方に向けて解説します。
この記事の内容
デジタルファーストとは?
デジタルファーストとは、ビジネスのあらゆる場面において、デジタルな手法やツールを最優先で活用する考え方を指します。
これは単に既存の業務をデジタルに置き換えるだけでなく、最初からデジタルを前提とした新しい業務フローやビジネスモデルを構築することを目指します。
元々は、新聞や雑誌といった紙媒体よりも先に、電子版を制作・提供することを指す言葉でした。そこから転じて、ビジネス全般に広がり、行政サービスまでにもこの考え方が取り入れられています。
類似の言葉に、ITシステムを構築する際にクラウドサービスの利用を第一に考える「クラウドファースト」がありますが、デジタルファーストはクラウドファーストの概念も含んだ、より広範な意味を持つ言葉です。
また、デジタルファーストと似た言葉に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」がありますが、両者は異なる概念です。
DXは、デジタル技術を用いてビジネスモデルや企業文化を根本的に変革することを指すのに対し、デジタルファーストは、そのDXを推進するための手段・考え方の一つと言えます。
関連記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義と成功事例を紹介
▶▶営業DXに必要なツールや実際の企業の声をまとめた詳細資料はこちら
デジタルファーストの具体例
デジタルファーストは、さまざまなビジネスシーンで活用されています。いくつか具体的な例を見ていきましょう。
| 領域 | 具体的な活用例 |
|---|---|
| 業務プロセス | 会議資料や契約書、提案書などをデジタル化し、 クラウド上で共有・管理します。 印刷や郵送にかかるコストを削減し、承認までの過程を早められます。 |
| 意思決定 | 勘や経験に頼るのではなく、デジタルで収集したデータを分析し、 客観的な事実にに基づいた意思決定が可能です。 |
| コミュニケーション | 対面での会議や商談をオンラインに切り替え、 出張や移動にかかる時間とコストを削減します。 |
| 顧客サービス | 実店舗でしか提供していなかった商品やサービスを、 ECサイトやアプリを通じて提供することで、 より多くの顧客に商品提供ができるようになります。 |
| 情報提供 | サービスに関するFAQやマニュアルをウェブサイトに掲載し、 企業の問い合わせ対応の負担を軽減します。 |
業務効率を上げるだけでなく、組織にイノベーションをもたらすための重要な考え方として、デジタルファーストは広く浸透している考え方です。
デジタルファーストが重要な理由
デジタルファーストが重要視される背景には、以下のような理由があります。
| 背景 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 新型コロナウイルスの世界的流行 | リモートワークやオンラインでのやりとりが急増。 対面や紙を前提とした業務が難しくなり、 デジタルへの移行が不可欠になりました。 |
| 顧客行動の変化 | スマートフォンやSNSの普及により、消費者はいつでも どこでも情報を手に入れ、サービスを利用するのが当たり前になりました。 企業は、変化した顧客層のニーズに応えるため、 顧客との接点をデジタル化する必要に迫られています。 |
| 技術の進化と普及 | クラウドサービスやAI、IoTといったデジタル技術が成熟し、導入コストが低下。 中小企業でも手軽にデジタル化を進められるようになりました。 |
| 行政のデジタルファースト法の制定 | 行政手続きを原則デジタルで完結させることを目指す法律。 特定の行政手続き(社会保険・労働保険関連など)の電子申請が 順次義務化され、行政が率先してデジタル化を進めることで、 企業もそれに合わせる必要性が高まりました。 |
デジタルファーストは、一時的な流行で終わるものではありません。デジタルファーストの考え方は、今後ますます企業の競争力に直結していくでしょう。
デジタルファーストのメリット
デジタルファーストを導入することで、企業にはさまざまなメリットがあります。
コスト削減につながる
デジタルファーストを推進することで、多岐にわたるコストを削減できます。
まず、物理的なコストとして、紙の印刷代、郵送費、書類の保管スペース代、そして出張費などが挙げられます。
例えば、営業担当者がオンラインで商談を行えば、交通費や宿泊費といった経費を大幅に減らせるでしょう。また、電子契約の導入は、収入印紙が不要になるため、印紙税の削減にもつながります。
さらに、目に見えるコストだけでなく、見えにくいコストも削減できるのが大きなメリットです。例えば、書類を探す時間や、承認を得るために部署間を移動する時間がなくなります。
時間的コストの削減は、社員一人ひとりの生産性を高め、結果として企業全体の利益向上につながると考えられます。
業務効率化が実現する
デジタルツールを積極的に活用すると、これまで手作業で行っていた業務が自動化され、業務効率が格段に向上します。
例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールを使えば、データの入力や集計、メールの送信といった定型業務を自動化できます。
これにより、社員はルーティンワークから解放され、より時間をかけるべき業務に集中できるでしょう。
また、情報共有を円滑にすることで業務効率化を図ることもできます。
クラウド上のドキュメントやチャットツールを使えば、部署や場所を問わず、リアルタイムでの情報共有が可能です。
結果、情報伝達の遅れや認識のズレが減り、プロジェクトをスムーズに進められるようになります。
関連記事:業務効率化の進め方とは? 6つのアイデア・おすすめツールを紹介
多様な働き方に対応できる
デジタルファーストを進めることで、企業は場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ができるようになります。
クラウドサービスやオンライン会議ツールを導入すれば、オフィス以外の場所でも業務遂行が可能です。
多様な働き方への対応は、社員のワークライフバランスを向上させる上で非常に重要です。育児や介護と仕事を両立しやすくなったり、通勤時間を有効活用できたりと、生活の質が高まるためです。
結果、社員の会社へのエンゲージメントが向上し、離職率の低下にもつながります。
さらに、この柔軟な働き方は優秀な人材の確保にも繋がります。地方在住者や海外在住者など、地理的な制約によってこれまで採用できなかった優秀な人材にアプローチできるためです。
デジタルファーストのデメリット
デジタルファーストには多くのメリットがありますが、一方で導入にはデメリットも伴います。
デジタル移行にコストがかかる
デジタルファーストの実現には、当然ながらコストが伴います。新しいシステムやツールを導入するための初期費用に加え、クラウドサービスのような継続的な利用料も発生する場合があります。
また、目に見える費用だけでなく、隠れたコストも存在します。例えば、既存のデータを新しいシステムに移行する際のデータ移行費用や、社内のIT環境を整備するためのネットワーク構築費用です。
コストを正確に把握し、導入によって得られるメリットと天秤にかけることが重要です。安易な導入は無駄な出費につながる可能性があるので、綿密な事前計画が必要になるでしょう。
セキュリティ対策が必要になる
紙の書類を電子化してクラウド上で管理するようになると、情報漏洩のリスクは高まります。不正アクセスやサイバー攻撃といった脅威から重要な情報を守るためには、厳重なセキュリティ対策が欠かせません。
単にデータをクラウドに保存するだけでなく、二段階認証やアクセス権限の厳格な管理を導入し、限られた人だけが機密情報にアクセスできるようにする必要があります。
また、万が一に備えて、データのバックアップ体制を構築しておくことも大切です。
自社に専門知識を持つ人材がいない場合は、セキュリティ対策に特化したコンサルティングサービスの利用も検討すると良いでしょう。
研修の実施が必要になる
新しいツールやシステムを導入しても、社員が使いこなせなければ意味がありません。
デジタルファーストを成功させるには、ツールを導入して終わりではなく、社員がスムーズに活用できるようにするための研修が不可欠です。
研修の内容は、単なる操作方法の説明にとどまりません。なぜこのツールを導入するのか、それによって業務がどう変わるのかといった目的や背景を共有することが大切です。
結果、社員は新しいツールへの抵抗感を減らし、積極的に使おうという意識を持てるでしょう。
また、一度きりの研修ではなく、新しい機能が追加されたときや、社員からの質問が多い項目について、定期的にフォローアップの研修を行うことも重要です。
ツールの定着を促すために、社内でのサポート体制を整えておきましょう。
デジタルファーストを成功させるポイント
デジタルファーストを成功させるためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
デジタル化が必要かどうか吟味する
闇雲にデジタル化を進めても、期待した効果は得られません。まずは、どの業務をデジタル化すれば最大の効果が生まれるのかをじっくり検討することが重要です。
現在の業務フローを「見える化」し、ボトルネックになっている部分や非効率な点を洗い出してみましょう。
例えば、手作業でのデータ入力や、紙の書類の承認に時間がかかっているなど、具体的な課題を特定することで、デジタル化すべきポイントが見えてきます。
現場理解を深める
どんなに優れたツールでも、現場の社員が使いこなせなければ意味がありません。デジタル化の成否は、従業員のツールへの習熟度と定着率にかかっていると言えるでしょう。
経営層が一方的に導入を決めるのではなく、実際にツールを使う現場の意見をヒアリングすることが大切です。
現場の声を反映させることで、使いやすいツールを選定でき、従業員の「自分ごと」としてデジタル化を進められます。
情報基盤を統一する
部署ごとにバラバラのツールを導入してしまうと、情報が分断され、かえって業務効率が低下する可能性があります。
スムーズな情報連携を実現するためには、全社で共通のツールやシステムを導入し、情報基盤を統一することが大切です。
情報基盤を統一することで、部署を越えたスムーズな情報共有が促され、組織全体の生産性向上につながります。
デジタルファーストの実現に役立つツール
デジタルファーストの推進にはさまざまなツールが役立ちますが、特に営業領域ではSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)が有効です。
SFAやCRMは、営業活動に関する情報を一元管理し、業務効率化や売上創出をサポートします。
具体的には以下のシーンでの活用が想定できます。
| 活用シーン | 具体的な効果 |
|---|---|
| 営業日報・報告業務のデジタル化 | 手書きやExcelで作成していた営業日報をSFA/CRM上で簡単に作成・共有できます。 上司はリアルタイムで進捗を把握でき、的確なアドバイスが可能になります。 |
| 顧客情報・履歴管理の一元化 | 顧客の基本情報から商談履歴、問い合わせ内容、購買履歴まで、あらゆる情報を 一箇所で管理できます。担当者が変わってもスムーズに引き継ぎでき、 顧客に合わせた対応が可能です。 |
ツールを導入することで、営業プロセス全体が可視化され、ボトルネックの発見や改善につながります。情報の属人化を防ぎ、組織全体の営業力が改善するでしょう。
関連記事:
まとめ
デジタルファーストは、単なるツールの導入ではなく、デジタルを前提としたビジネスへの考え方の転換です。業務効率化やコスト削減、新たな顧客体験の創出など、多くのメリットがありますが、導入にはコストやセキュリティ対策、社員教育といった課題も伴います。
デジタルファーストを成功させるためには、全社的に取り組む姿勢と、現場の意見を尊重することが不可欠です。特に営業領域においては、情報の一元管理と業務効率化を実現するSFA/CRMの導入が、デジタルファースト推進の鍵となります。
誰でも使えて誰でも成果を出せるSFA/CRM「Mazrica Sales」を活用することで、デジタルファーストの実現をサポートできます。営業活動のデジタル化に興味をお持ちの方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI
資料をダウンロードする