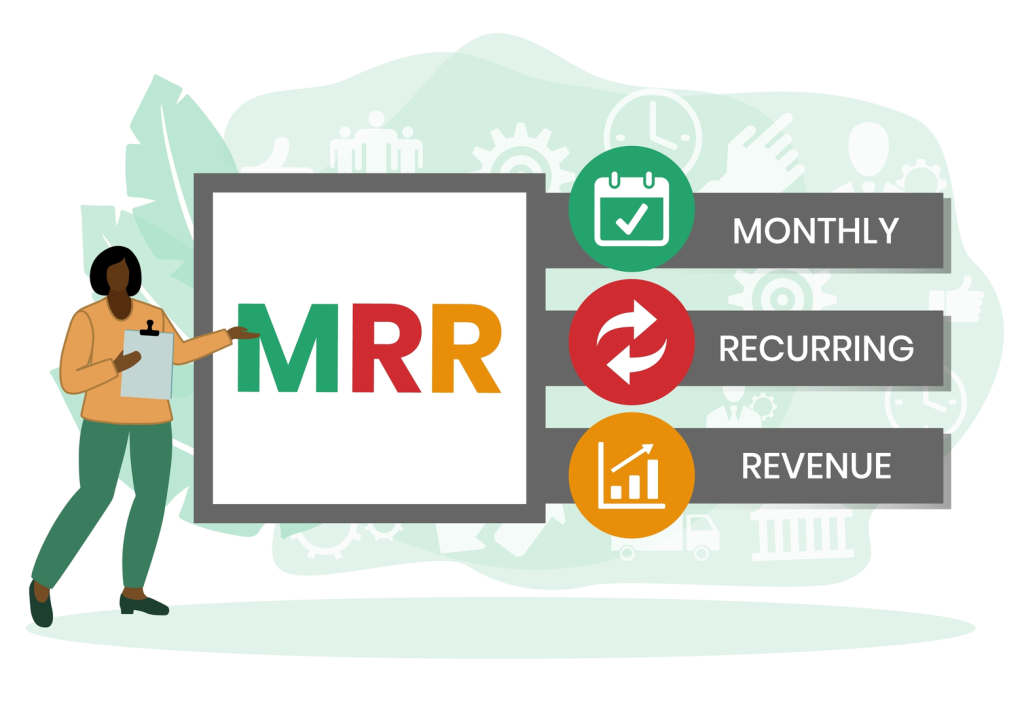「膨大なデータが手元にあるのに、うまく活用できていない」と感じていないでしょうか。
データ分析の専門家がいなくても、自社で保有するデータを活用できないままだと、ライバル企業との差は広がる一方です。非効率な業務に悩まされ、貴重な機会を逃してしまうことにもなりかねません。
しかし、データ分析は、特別なスキルがなくても実践できます。本記事では、すぐに実務で使えるデータ分析の代表的な手法と、その活用ポイントを分かりやすく解説します。
この記事の内容
データ分析とは?
データ分析は、生データ(加工されていないデータ)を意味のある情報へと変換し、パターンや傾向、相関関係などを発見する一連の活動です。
具体的には、統計的手法や機械学習アルゴリズムを用いて、数値の裏にある事実や未来の予測を行います。
例えば、顧客の購買履歴から「なぜこの商品が売れているのか」といった因果関係を解明したり、過去の商談データから「今後どの顧客が成約する可能性が高いか」といった将来を予測することです。
データ分析を適切に活用することで事業の現状を正確に把握し、データに基づいた合理的な意思決定ができるようになります。
関連記事:データ分析に役立つ仮説思考とは?仮説思考を用いた分析方法を解説
データビジュアライゼーションとの関係
データビジュアライゼーションとは、データをグラフや図表などで視覚的に表現することです。膨大なデータから得られた分析結果を、誰にでも分かりやすく伝えるためには欠かせません。
データビジュアライゼーションには、主に以下のようなメリットがあります。
- 直感的な理解:膨大なデータや複雑な分析結果も、グラフや図表にすることで、専門知識がない人でも内容を直感的に理解できる
- 迅速な意思決定:データの傾向やパターンが一目で把握できるため、会議での議論が効率化し、より迅速な意思決定につながる
- 課題の早期発見:データの変化や異常値を視覚的に捉えることで、ビジネスにおける課題を素早く見つけ出すことができる
データビジュアライゼーションを活用することで、データに隠されたパターンや傾向を直感的に把握でき、より正確な意思決定ができるようになります。
代表的なデータ分析の手法10選
データ分析には目的に応じてさまざまな手法があります。そこで、ビジネスで頻繁に活用される代表的な分析手法を10種類紹介します。
バスケット分析
「よく一緒に買われる商品」の組み合わせを発見する手法です。
例えば、小売店で「おむつを買う人はビールも買う」といった購買傾向を把握することで、関連商品の発見やクロスセル・アップセル戦略の構築に役立ちます。
活用シーンは次の通りです。
- 小売業界:商品陳列の最適化、セット販売の企画、顧客への商品提案
- ECサイト:関連商品の自動表示、顧客ごとのパーソナライズされた商品提案
バスケット分析を行うことで、顧客の潜在的なニーズを発見し、クロスセルやアップセルにつなげられ、顧客単価の向上と売上全体の最大化が期待できます。
クロス集計分析
複数の設問項目を掛け合わせてデータを整理・集計する手法です。
例えば、「性別」と「商品Aの購入有無」といった属性を掛け合わせることで、特定の層(例:20代女性)の購買行動やアンケート結果の傾向を詳細に把握できます。
活用シーンは次の通りです。
- マーケティング:顧客アンケートの結果を年齢や居住地で比較し、ターゲット層に合わせたプロモーション施策を検討に活用する
- 商品開発:既存商品の満足度を性別や年代別に比較し、改良点や新商品の開発方針を決定する
データ全体を俯瞰するだけでは見えなかった、特定の層に潜む傾向や課題を発見でき、経験や勘に頼るのではなく、データに基づいた効果的な意思決定が可能になります。
クラスター分析
似ているデータ同士を自動的にグループ分けする手法です。顧客の購買履歴や行動パターンをもとに、類似性の高い顧客層を特定し、ターゲット層の明確化やセグメンテーションに利用します。
活用シーンは次の通りです。
- 顧客管理:顧客を「高頻度で高額商品を購入するVIP層」や「特定のセール時にまとめて購入するライト層」といったグループに分け、それぞれに最適なアプローチを行う
- マーケティング:潜在顧客をセグメント化し、特定のグループに合わせた広告配信やメールマガジンの内容を最適化する
顧客全体を均一に扱うのではなく、個々のグループに最適化された戦略を立てられるようになります。これにより、マーケティング施策の効率が向上し、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上につながります。
ABC分析
商品や顧客を売上や利益への貢献度によって3つのランク(A、B、C)に分類する手法です。貢献度の高いAランクに経営資源を集中させるなど、在庫管理の効率化やマーケティング戦略の最適化に役立てます。
活用シーンは次の通りです。
- 在庫管理:売上貢献度が高い「Aランク」の商品を優先的に在庫確保し、欠品を防ぐ
- 営業活動:売上貢献度が高い「Aランク」の顧客に対しては手厚いフォローを行うなど、営業リソースを効率的に配分する
限られた経営資源(在庫、予算、人員など)を、最も効果的な対象に集中させることができ、業務効率の向上と収益の最大化を図れます。
関連記事:ABC分析とは?|在庫管理を行いやすく仕事を効率化する方法
因子分析
多数の変数に共通して影響を与えている潜在的な要因(因子)を発見する手法です。アンケート結果などから、顧客の購買を左右する隠れたニーズや潜在意識を把握する際に用いられます。
活用シーンは次の通りです。
- 商品開発:顧客アンケートで「使いやすさ」「デザイン性」といった多くの評価項目を調査した際、回答の傾向から「コストパフォーマンス」といった潜在的な要因を特定し、製品コンセプトに反映させる
- ブランド調査:複数のブランドイメージに関する項目から、「革新性」や「信頼性」といった共通の因子を抽出し、ブランドの強みや弱みを分析する
一見無関係に見えるデータ間の関連性を明らかにすることで、顧客の行動の根本的な理由を深く理解できます。結果、より本質的なマーケティングや商品開発が可能になります。
決定木分析(ディシジョンツリー分析)
データを樹木状のモデルで表現し、予測や判別を行う手法です。顧客データから「どの条件を満たす顧客が購入に至りやすいか」といった明確なルールを抽出し、ターゲット絞り込みの精度を高めます。
活用シーンは次の通りです。
- マーケティング:顧客の年齢、過去の購入回数などのデータから、「40代女性で過去に2回以上購入した顧客は、次回も購入する可能性が高い」といった予測モデルを構築し、購入見込み客を特定する
- 与信管理:顧客の属性情報や過去の取引履歴から、貸し倒れのリスクを予測する
分析結果がツリー(樹木)の形で可視化されるため、予測に至った過程を直感的に理解しやすく、分析結果を施策に落とし込みやすくなるのが特徴です。
ロジスティック回帰分析
ある事象が起こる確率を予測する統計手法です。過去のデータをもとに、特定の顧客が「購入するかどうか」「解約するかどうか」といった二者択一の結果を確率として予測する際に利用されます。
活用シーンは次の通りです。
- 顧客離脱防止:Webサイトの訪問回数や閲覧ページ数といったデータから、「この顧客がサービスを解約する確率」を予測し、先手を打った対策を講じる
- 成約予測:過去の商談データから「この案件が成約に至る確率」を予測し、営業リソースを効率的に配分する
特定の事象が起こる可能性を数値(確率)として明確に示せるため、リスク管理やリソース配分といった意思決定の精度を向上させられます。
アソシエーション分析
ビッグデータからデータ間の関連性や連動性を発見する手法です。
ECサイトの購入履歴データから「シャンプーとコンディショナーを同時に購入する顧客が多い」といった関連性を見つけ出し、セット販売や推奨表示に役立てます。
活用シーンは次の通りです。
- ECサイト:顧客の購入履歴から「この商品を買った人は、この商品も買っています」といった推奨機能を実装する
- 小売業界:POSデータから商品の併売傾向を把握し、商品の配置やキャンペーン施策を最適化する
顧客の購買行動のパターンを深く理解することで、クロスセルやアップセルを促す効果的な施策を立案できます。
主成分分析
多くの変数を持つデータを、情報量を維持しつつ少数の「主成分」に集約する手法です。集約することで、複雑なデータを単純化して可視化できるようになり、解釈を容易にします。
活用シーンは次の通りです。
- アンケート調査:顧客の評価データが「機能性」「デザイン」「価格」「サポート」といった多くの項目に分かれている場合、それらを「製品の魅力度」と「顧客満足度」といった2つの主成分に集約し、グラフ化して直感的に理解できるようにする
- データ可視化:膨大な顧客データの中から、重要な要素だけを抽出して可視化することで、データの全体像を把握しやすくなる
複雑で多岐にわたるデータをシンプルに要約できるため、データ分析の初期段階で全体像を把握したり、分析結果を他者に説明したりする際に非常に役立ちます。
グレイモデル
過去の少ないデータから、それに続く未来の数値を予測する手法です。新製品を発売して間もない時期など、過去のデータが十分にない状況での予測に活用されます。
活用シーンは次の通りです。
- 新製品の売上予測:発売直後で過去のデータが限られている新製品の売上トレンドを、迅速に予測したいときに利用する
- 短期的な需要予測:過去のデータが少ない短期的なキャンペーンの効果予測などに活用する
データが少ない状況でも、高い精度で予測を立てられるのが最大の利点です。
データ分析の実施の流れ
データ分析を成功させるためには、闇雲にデータを集めて分析するのではなく、以下のステップに沿って進めることが重要です。
データ活用の目的を明確にする
データ活用の目的を明確にすることから始めます。データ分析を通じてどのような課題を解決したいのか、どのような目標を達成したいのかを具体的に設定しましょう。
例えば「顧客離脱率を10%改善する」「新商品の売上を前年比20%増にする」といった具体的な目標を設定します。
このように目的を明確にすることで、「どの顧客データを集めるべきか」「どの分析手法が最適か」といった方向性が定まります。
「現場の課題を深く理解しているか」「目標は実現可能か」「分析結果をどのように活用するか」といった点に注意することが重要です。
目的が曖昧なままでは、どのようなデータを集めればいいか、どの手法を使えばいいかが定まらず、効果的な分析は困難になるからです。
自社のデータを把握する
次に、目的達成のために必要なデータは何か、自社内にどのようなデータがどの程度あるのかを把握します。
顧客情報、売上データ、Webサイトのアクセスログなど、社内外に散在するデータを洗い出し、分析に活用できるかを確認しましょう。
データの把握をする際は「そもそもそのデータはどこに保存されているか」「データは最新の状態か」「データに偏りはないか」といった注意点を事前に確認しておくことが、その後のスムーズな分析につながります。
データの収集・蓄積を行う
把握したデータをもとに、分析に適した形式でデータを収集・蓄積します。異なるシステムに分散しているデータを統合したり、不完全なデータを補完したりといった作業も行います。
例えば、ECサイトの売上データ(CSV)と実店舗のPOSデータ(データベース)のように、異なるシステムに分散しているデータを統合したり、住所の表記ゆれを修正したり、欠損しているデータを補完したりといった作業です。
「データのフォーマットは統一されているか」「個人情報などの機密データは適切に管理されているか」「データの更新は自動化されているか」といった点に注意することが重要です。
データを探索する
収集したデータの概要を把握し、データの品質を確認します。
欠損値や外れ値がないか、データに偏りがないかなどをチェックし、分析の精度を高めるための前処理を行います。取得できたデータから仮説を立てることも重要です。
例えば、顧客データの「年齢」の項目に「999」という異常値(外れ値)がないか、「購入履歴」のデータが一部欠けていないか(欠損値)などをチェックし、分析の精度を高めるための前処理を行います。
データ全体をグラフ化して可視化することで、データに偏りがないかを確認し「新規顧客はWeb広告経由が多い」といった仮説を立てることも重要です。
「データのどこに異常があるか」「その異常が分析に与える影響はどの程度か」「どのデータを分析に使うべきか」といった点に注意して進めることで、分析作業がスムーズになります。
現状・予測分析を行う
データに基づいて現状の傾向を把握し、統計的な手法を用いて将来の予測を行います。
例えば、現在の売上動向から来月の売上を予測したり、特定の顧客層の行動パターンから将来の離脱リスクを予測したりします。予測分析は現状を客観的に評価し、将来の事業戦略を立てる上で欠かせません。
「予測結果の精度はどの程度か」「予測の前提条件は現実的か」「予測は定期的に見直されているか」といった点に注意することが重要です。分析結果が、事業の意思決定に直結する重要な情報となります。
▶▶営業成果を最大化するデータ活用法についての詳細資料はこちらから
データ分析で注意すべきポイント
データ分析を効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
明確な目標を設定する
データ分析はあくまで課題解決のための手段です。
最終的に何を知りたいのか、どんな意思決定に役立てたいのかを明確にすることで、分析結果がブレることなく、事業に貢献する知見を得られます。
| 失敗例 | 概要 |
|---|---|
| 目的が曖昧なケース | 「とりあえずデータを見てみよう」「データ分析をやってみたい」 といった漠然とした目的で始めると、分析結果から具体的な アクションプランが生まれず、時間やコストだけが無駄に なってしまうことがあります。 |
| 目的がずれているケース | 例えば「売上向上」という目的があるにもかかわらず、 「従業員の満足度データ」ばかりを分析してしまったりなど、 目的に合わないデータを扱ってしまうと、当然ながら有効な 結論は得られません。 |
失敗を防ぐためにも、データ分析を始める前に「何のためにデータを分析するのか」という問いを明確にしておくことが非常に重要です。
適切なデータ分析の手法を選ぶ
目的に応じて最適な分析手法を選択することが重要です。
例えば、顧客のセグメンテーションにはクラスター分析、商品の併売傾向の把握にはバスケット分析が適しています。
| 失敗例 | 概要 |
|---|---|
| 不適切な手法の選択 | 顧客の潜在的なニーズを深く理解したいにもかかわらず、 クロス集計分析といった単純な集計手法に終始してしまうと、 表面的な結果しか得られず、本質的な課題解決にはつながりません。 |
| 手法の誤用 | 新商品の売り上げ予測をしたいのに、 相関関係を見るためのバスケット分析を使ってしまうなど、 手法の目的を誤って利用すると、全く意味のない分析結果になってしまいます。 |
各分析手法の特性や目的を正しく理解し、データ分析のゴールに最も適した手法を選ぶことが不可欠です。
データ分析を目的にしない
分析そのものが目的になってしまうと、多くの時間とリソースを費やしても、事業に活かされない結果に終わってしまいます。
分析結果を施策に活かし、効果を検証するサイクルを回すことが最も重要です。
| 失敗例 | 概要 |
|---|---|
| 施策への落とし込みが不足 | 完璧な分析レポートを作成したものの、 その結果をどうビジネスに活用するか検討されず、 結局は放置されてしまうケースです。 分析結果は、活かされて初めて価値が生まれます。 |
| 仮説検証のサイクルが回らない | 分析結果から改善策を導き出した後、 施策を実行して終わりにしてしまうケースです。 施策の効果を再度データで検証しなければ、 次のアクションにつなげることができません。 |
| 自己満足に陥る | グラフや数字を羅列しただけの、誰にも理解できない 複雑な分析レポートに満足してしまうケースです。 本当に重要なのは、分析の過程からではなく、 そこから得られた知見が事業にどう貢献するかです。 |
分析結果を具体的な施策に結びつけ、その効果を測定し、次の分析につなげるというPDCAサイクルを意識することが不可欠です。
関連記事:PDCAサイクルとは?業務改善につながる回し方のコツやOODAとの違いを解説
ツールを利用する
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールやSFA/CRMなどのツールを活用することで、データ収集から分析、ビジュアライゼーションまでの一連の流れを効率化できます。
| 失敗例 | 概要 |
|---|---|
| 導入が目的化する | 「最新のツールを導入すればデータ分析ができる」と考え、導入したものの、 活用方法が定まらずにツールの利用が浸透しないケースです。 ツールはあくまで手段であり、活用する目的が重要です。 |
| データ連携が不十分 | ツールを導入したものの、基幹システムや他のツールとのデータ連携が スムーズに行われず、データが一元化できないケースです。手作業での データ入力が残ると、効率化や制度の向上といったメリットが得られません。 |
| 一部の担当者しか使えない | 専門的な知識が必要なツールを選んでしまい、一部の担当者しか扱えず、 組織全体でデータを活用できないケースです。誰もが直感的に使える ツールを選ぶことが、データドリブンな文化を浸透させる鍵となります。 |
失敗しないためにも、ツールの導入前に「何のデータを」「誰が」「どのように使って」「何を解決したいのか」を具体的に定義し、自社のデータやメンバーのスキルレベルに合ったツールを選ぶことが重要です。
まとめ
データ分析は、事業の課題解決や意思決定に不可欠なプロセスです。データビジュアライゼーションや適切な分析手法の活用、明確な目標設定が成功の鍵となります。
特に営業においては、顧客データや商談データを効率的に分析することが、売上向上に直結します。そのため、顧客情報や案件進捗を一元管理できるSFA/CRM(営業支援システム/顧客関係管理システム)がデータ分析に非常に有効です。
SFA/CRMを活用することで、営業活動の現状把握や将来予測が容易になり、効果的な営業戦略の立案に役立ちます。
さらに詳しい情報は、以下の資料で解説しています。
特に以下のようなご要望をお持ちの方はぜひご覧ください。
- 営業組織の効率化を進めたい
- 営業のムダをなくしたい
- Excel管理から脱却したい

SFA/CRMとは? -入門編 -
SFA/CRMをご存知でしょうか?SFA/CRMの導入で営業組織が劇的に変わります。 そもそもSFA/CRMとは?何ができるのか?そしてどのような導入メリットはあるのか? 様々な統計データを用いながらSFA/CRMの概要や導入プロセスまでを整理した資料です。
資料をダウンロードする