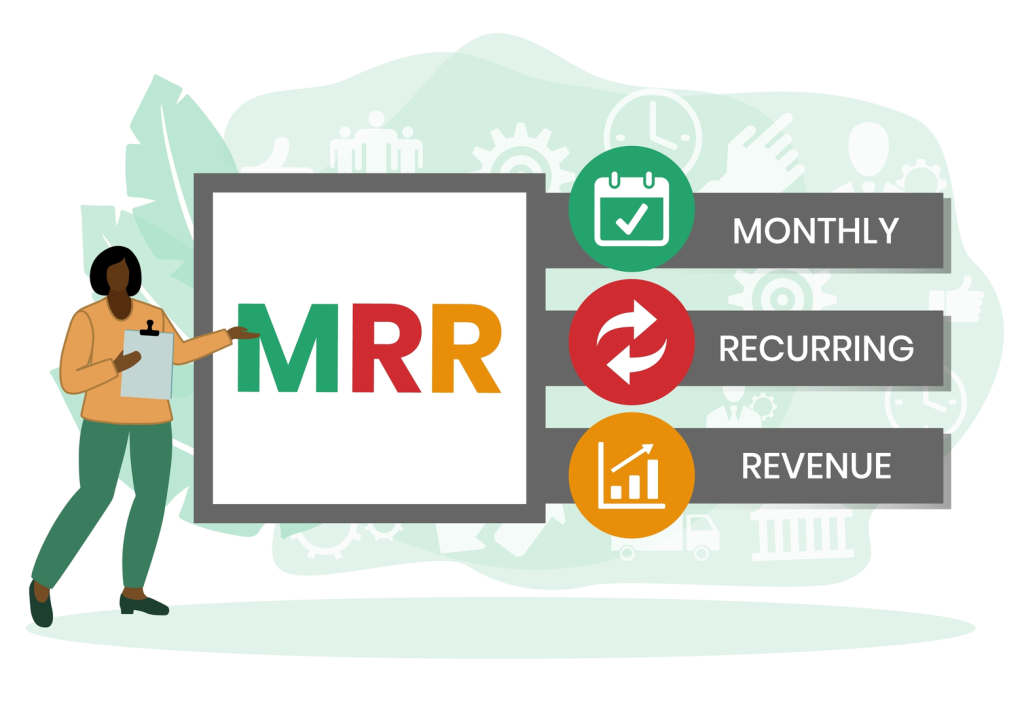売上拡大を目指す企業にとって、マーケティングとインサイドセールスの連携は欠かせません。
しかし、「うまく連携できていない」「情報共有が不十分」といった課題を抱える現場も少なくありません。
本記事では、両部門が効果的に連携するためのポイントや成功事例を交えながら、連携強化による成果最大化の方法を解説します。
営業・マーケティング担当者必見の内容です。
この記事の内容
インサイドセールスとマーケティングの関係性とは?
インサイドセールスとマーケティングは、顧客獲得から商談化、成約に至るプロセスにおいて密接に関わり合っています。
マーケティング部門は、見込み顧客(リード)を獲得・育成し、インサイドセールスに引き渡す役割を担います。
その後、インサイドセールスがリードと接点を持ち、ニーズをヒアリングしながら商談を創出したり、リードの育成を担います。
このプロセスがスムーズに連携されることで、営業活動の生産性が向上し、売上向上につながります。
インサイドセールスとマーケティングの連携による効果を最大化するためには、両者の役割を明確にし、戦略的な仕組みづくりが不可欠となります。
関連記事:マーケティングと営業の連携の秘訣とは?メリット・トラブル解決策を解説!
インサイドセールスとマーケティングの違い
インサイドセールスとマーケティングは、それぞれ異なる役割と目的を持つ部門ですが、営業活動を成功に導く上では、両者の違いを理解し、適切に連携することが重要です。ここでは、それぞれの役割と特徴、そして具体的な違いについて解説します。
関連記事:インサイドセールスとフィールドセールスの違いを徹底解説!役割・分業・連携のポイント
インサイドセールスの役割と特徴
インサイドセールスは、主に電話やメール、オンライン会議ツールなどを用いて顧客と非対面で接点を持ち、見込み顧客のニーズを引き出しながら商談機会を創出する営業手法です。基本的にはオンラインで完結する業務のため、移動の手間がなく効率的に営業活動を進めることができます。
マーケティングから引き継いだリード(見込み顧客)に対してアプローチを行い、顧客の課題や関心を深掘りすることが重要な役割の一つです。そして、購買意欲が高いと判断されるリードをフィールドセールスに渡し、受注に貢献します。
このように、インサイドセールスは営業プロセスの初期段階を担い、商談化率の向上と営業効率の最大化を目指す重要な存在です。
関連記事:インサイドセールスとは?概要やメリット、おすすめツールをわかりやすく解説!
マーケティングの基本的な役割と目的
マーケティングの基本的な役割は、見込み顧客の獲得と育成、そして企業や製品の認知向上やプロモーション活動を行うことです。市場調査や顧客分析を通じてターゲット層を明確にし、顧客のニーズに応じたコンテンツやキャンペーンを展開することで、質の高いリードを創出します。
さらに、リードに対して適切な情報を段階的に提供し、購買意欲を高める「リードナーチャリング(育成)」も重要な業務の一つです。
マーケティングは売上を生み出す前段階として重要な役割を果たし、インサイドセールスや営業部門が効率的に成果を上げるための土台を築くことが主な目的です。
関連記事:マーケティング戦略とは?立案手順・フレームワーク・成功事例を解説
インサイドセールスとマーケティングの主な違い
インサイドセールスとマーケティングの主な違いは、「アプローチする顧客層」と「顧客との接点の持ち方」にあります。マーケティングは、まだ企業への関心が浅い段階の顧客に対して広範囲な情報提供を行い、認知や興味関心を高めることに注力します。一方、インサイドセールスは、すでに何らかの関心を持っている顧客やアクションがあった顧客に対し、具体的なニーズや課題を掘り下げる役割を担います。
また、活動の手法にも違いがあります。マーケティングはWeb広告やメールマーケティング、SNS運用、ウェビナーなど、比較的マスに向けた施策を展開する一方で、インサイドセールスは個別対応が基本です。顧客一人ひとりと対話し、商談化への道筋を丁寧に描いていきます。
このように、両者は異なるアプローチを取りながらも、売上の最大化という共通の目的に向かって補完し合う関係にあります。
関連記事:インサイドセールスとテレアポの違いとは?営業の運用事例とコツを紹介
インサイドセールスとマーケティングの連携が重要な理由
インサイドセールスとマーケティングの連携が重要視される理由は、顧客獲得から成約までのプロセス全体を最適化し、効率的かつ持続的に成果を上げるためです。両部門は地続きの関係にあり、戦略的に情報を共有し連携することで、リードや商談の質を向上させ、売上増加のスピードと確度を高めることができます。
例えば、マーケティング部門が創出したリードの情報がインサイドセールスに引き継がれることで、初回のコンタクトから顧客の関心や課題に即した提案が可能になります。逆に、インサイドセールスがヒアリングした顧客のリアルな声をマーケティングにフィードバックすることで、より効果的なコンテンツやキャンペーンの設計が可能となります。
両者の連携がうまく機能すれば、リードタイムの短縮や顧客体験の向上にもつながります。リードの質を高め、商談化率を改善するためには、マーケティングとインサイドセールスが一体となったアプローチが欠かせません。
連携を強化するためのポイント
インサイドセールスとマーケティングの連携を強化するためには、単に情報をやり取りするだけでは不十分です。両者が戦略的に同じ方向を目指すための仕組みと環境を整備することが大切です。ここでは、実践的な3つのポイントを紹介します。
共通のKPIを設定する
マーケティングとインサイドセールスが連携するうえで、共通のKPI(重要業績評価指標)を設定することは非常に重要です。
具体的には、リード数、商談や受注につながりやすい有効リード数、資料請求や商談希望などのコンバージョン数、商談数などを共通のKPIとして設定します。
これにより、両部門が同じ目標を持ち、進捗状況を把握したり、成果を定量的に評価できるようになります。
▶︎▶︎よく耳にするKPI、実は正しくKPIマネジメントを実行できている組織は意外と少ないのです。
本資料では、KPIの定義から実行のステップまでわかりやすく解説します。
ぜひ併せてご覧ください。
共通のKPIを設定するメリット
組織全体の方向性を統一することができる
マーケティングとインサイドセールスが共通のKPIを設定することで、組織全体の方向性を統一することができます。異なるKPIで活動すると、それぞれが別方向を向いてしまい、連携がうまく機能しなくなります。
共通のKPIを持つことで、両部門が同じゴールに向かって活動し、無駄な施策実行や重複した活動を避けることが可能です。
たとえば「月間商談件数」を共通指標とした場合、マーケティングは商談につながりやすいリードの獲得に注力し、インサイドセールスは商談につながるリードの深掘りや、ターゲットに絞ったアプローチに集中する、といった協働が自然と生まれます。
関連記事:チームビルディングとは?マネージャーがチーム作りで意識すべき3点
リードの質を共通基準で判断しやすくなる
共通のKPIを持つことで、リードの質を同じ基準で判断できるようになります。逆に、共通のKPIがなければ、どのリードを“質が高い”とするかの判断基準が属人化し、対応にバラつきが生まれます。
マーケティング部門が質の高いリードを獲得できたと思っていても、実際にインサイドセールスがアプローチすると質が低いケースや、マーケティング部門が努力して獲得したリードをインサイドセールスが独自の判断で優先順位を下げてしまい、アプローチせず放置してしまう、といった事態はよくある問題です。
共通のKPIを設定することで、両部門が同じ視点でリードを評価できるようになり、互いにフィードバックをし合いながら、効率的な改善活動を行うことが可能になります。
関連記事:リードクオリフィケーションとは?効果的なスコアリング方法を解説
全体として統一された戦略の設計が可能になる
共通のKPIを起点にすると、マーケティングとインサイドセールスが戦略段階から連携を取りやすくなり、全体の事業目標と各部門が統一された戦略を描くことができます。統一された戦略設計ができれば、その後も戦略に紐づき、一貫した施策を各部門が打ち出せるでしょう。
さらに、統一された戦略のもと、適切なKPI設定ができているか、進捗は問題ないかを定期的に評価・改善を行うことで、インサイドセールスとマーケティングの協力体制がより強化され、売上最大化につながります。
関連記事:マーケティング戦略とは?立案手順・フレームワーク・成功事例を解説
業務の流れを整え、部門間で共通化する
業務の流れを整理し、部門間で共有化することで、業務効率化を図ることが可能です。
部門ごとに業務フローが異なると、情報共有のタイミングがずれたり、対応が重複する恐れがあります。そのため、マーケティングからインサイドセールスへのリード受け渡しのプロセスや、対応ステータスのルールなどを明文化し、業務の流れやルールを整えることが重要です。
具体的には、マーケティングチームが獲得したリードを、いつ、どのような方法でインサイドセールスに共有するのか、リードに関してどのような情報を事前に収集しておくべきか(会社名、部署、役職、行動履歴など)などを予め整理し、部門間で共通ルールを決めておきます。
特にリード情報を引き渡す際は、「リードの質を保ちつつ、迅速なフォローアップが可能な状態にすること」です。例えば、リードの流入経路や過去の接点などの情報をCRM(顧客管理システム)に明記し、次のアクションにつながる情報を揃えておくことで、インサイドセールスが即座に適切な対応を行えるようになります。
このように業務フローを整理し、部門間で共通化することで、スムーズな連携を可能にし、全体の業務効率が向上するでしょう。
関連記事:営業アプローチとは?営業手法や成功のポイントを解説
ツールを使って顧客情報を一元管理する
インサイドセールスとマーケティングの連携を強化するためには、ツールの活用も欠かせません。
CRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールを導入することで、顧客情報やリードのステータスを一元的な管理が可能になります。
両部門がリアルタイムで同じ情報にアクセスできるため、対応の抜け漏れを防ぎ、顧客に対して迅速かつ、一貫性のあるコミュニケーションを取ることができます。
さらに、情報をツールに蓄積することで、パーソナライズされたマーケティング活動や営業活動も可能にします。
一元管理されたデータは、顧客分析やマーケティング・営業活動の振り返り、施策の改善にも活用できるため、データドリブンな体制の構築にもつながるでしょう。
▶︎▶︎CRMを導入するメリットをご存知ですか?
本資料では、様々な統計データを用いてCRMの意味やメリットなどを解説しています。
ぜひこちらの資料もご覧ください。
まとめ
インサイドセールスとマーケティングは、それぞれ異なる役割や機能を持ちながらも、最終的には商談、売上という共通の目的を担っています。両部門が連携を深めることで、商談化率や成約率の向上、営業活動の生産性向上、顧客満足度の向上、といった、さまざまな効果を得ることができるでしょう。
両部門の連携を強化するためには、情報の一元管理と業務プロセスの仕組み化が必要不可欠です。CRMやMAツールを活用することで、リードの獲得からナーチャリング、商談獲得までを仕組み化し、強固な連携体制を築くことが可能です。営業成果を最大化するために、CRMやMAツールの役割や導入効果についても理解を深めておくことがおすすめです。