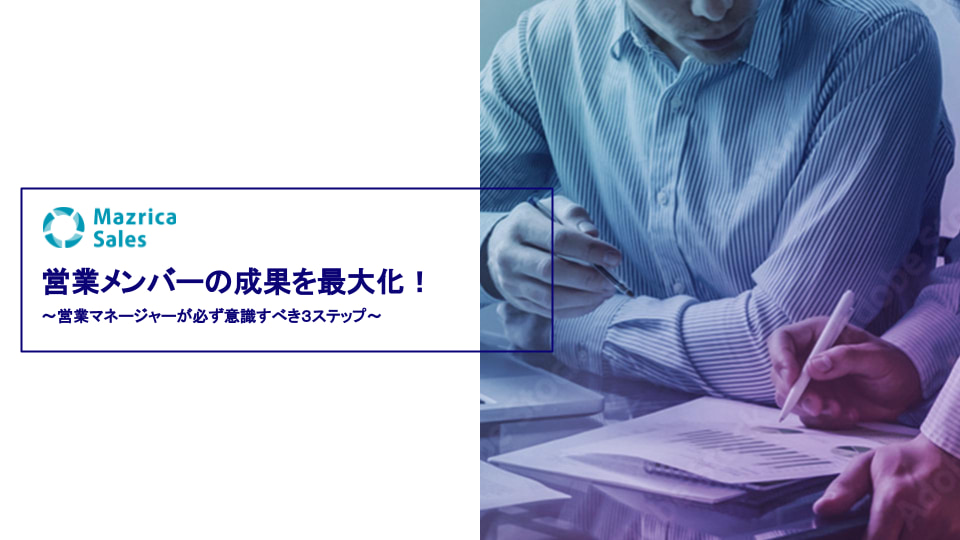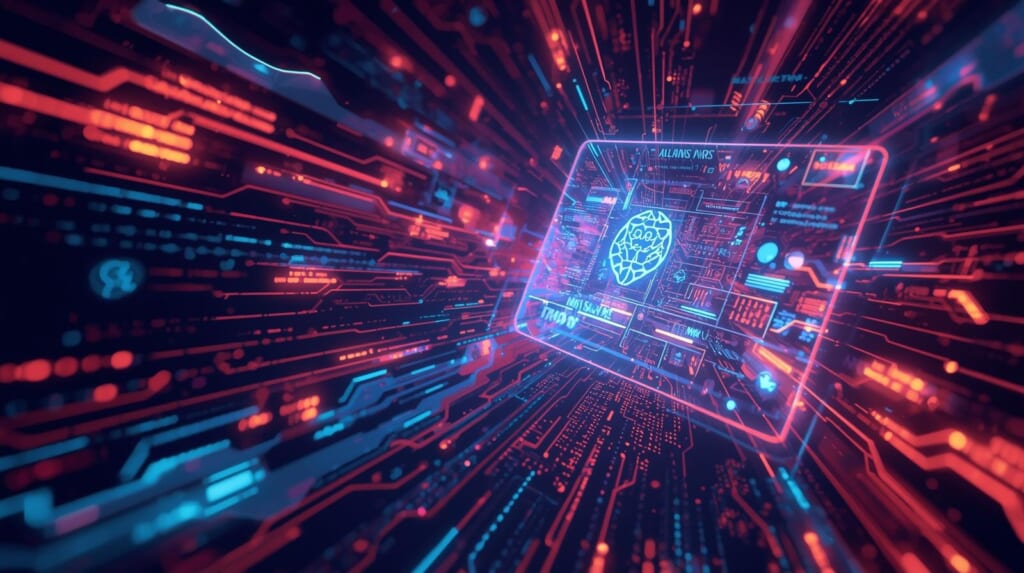企業で働いていると、もしかしたら「嫌いな部下」がいるかもしれません。
嫌いな部下がいるとコミュニケーションが円滑にいかなかったり、ストレスが溜まってしまったり、いいことがないですよね。
しかし、「嫌い」という感情を完全に自力でコントロールするのも至難の業です。
そこで、この記事では嫌いな部下との接し方をご紹介します。
この記事の内容
嫌いな部下がいるのは当たり前

嫌いな部下がいることで、上司失格だと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。
実際には、そんな必要はありません。
「嫌い」という感情を持つことは人間として自然なことだからです。
嫌いな部下と接する方法を身に着けるためには、まずはこの「嫌い」という気持ちを受け入れるところから始まります。
人を嫌いになる原因
人を嫌いになることは自然なことであると哲学者の中島義道氏は述べています。その上で、その段階や要因は8つあると分析しています。
その8つとは、以下の通りです。
(1)相手が自分の期待に応えてくれない
(2)相手が現在あるいは将来自分に危害(損失)を加える恐れがある
(3)相手に対する嫉妬
(4)相手に対する軽蔑
(5)相手が「自分を軽蔑している」という感じがする
(6)相手が自分を「嫌っている」という感じがする
(7)相手に対する絶対的無関心
(8)相手に対する生理的・観念的な拒絶反応
(嫉妬、軽蔑、無関心…、人が人を嫌う8つの要因より)
この8つを見てみると、上司と部下の関係にも当てはまりそうですよね。
相手が自分の指示に従わず、期待に応えてくれなければ、当然上司である皆さんは部下に苦手意識を持つようになります。
そして、指示に従ってくれないということは部署や会社にその相手が損失を出すかもしれないということで、ひいては自分への評価という形で部下に危害を加えられる恐れがあると思います。
しかも、部下に対する軽蔑を抱いたり、「なんでそんなに勝手に自由でいられるんだ」と嫉妬を抱くかもしれません。
さらに、自分が嫌っていると、なんとなく相手も自分のことが嫌いなように思われてきます。
結果として、部下に対する絶対的な無関心や、相手に対する生理的・観念的な拒絶反応が生まれてしまうのです。
部下を嫌いになる原因TOP10
では、実際に部下を嫌いになる原因とは一体どのようなものが考えられているのでしょうか。
ビズパークの調査によると、以下のような特徴が部下を嫌いになるきっかけとして考えられそうです。
1位 嘘をつく、失敗を隠す
2位 怠惰である
3位 他責思考である
4位 指示した業務すらこなせない
5位 ホウレンソウを無視した仕事をする
6位 挨拶ができず態度も良くない
7位 会社や業務に対する愚痴を言う
8位 コミュニケーションを軽視している
9位 視線が合わない
10位 テクニックが無くPDCAを回そうともしない
この表を見ているだけで嫌いな部下を思い出してイライラするという方もいるのではないでしょうか。
しかし、こうした人間関係の鬱憤を軽く見てはいけません。
離職や転職の原因としては「人間関係」が一位であり、上司と部下のトラブルによって相手が転職という会社にとって悪い結果をもたらすことが考えられるからです。
そこで、上司と部下の関係を円滑に進めていく必要があります。
関連記事:やる気のない社員が生まれる原因とは?対処法も解説!
嫌いな部下を分析する

嫌いな部下との関係を改善するための一歩としては、自分の「嫌い」という感情や「嫌いな相手」を分析することが必要です。
研究者がある物を分析し続けていくうちにそれに対する嫌悪の感情がだんだん失せてくる、という現象が度々見られるように、「嫌い」ということを分析することはその「嫌い」を解消する一歩です。
「客観的」に自分の「嫌い」という感情をみてみましょう。
嫌いな理由を書き出す
まずは、嫌いという感情の理由を5つほど書き出してみましょう。
その際、上司だから、などという遠慮は捨てて、一人の人間として忌憚なく思いを紙に書き出しましょう。
5個以上あるならばそれを全て列挙してみて、5個も思いつかないのであれば書けるところまで書いてみましょう。
嫌いである理由が列挙できたら、そのあとは列挙できた理由をそれぞれのカテゴリー分けしていきます。
例えば、「高慢な感じがしていけ好かない」という嫌いな感情の理由があったとします。そうしたら、何が「高慢な感じ」なのかまでを分析していきます。
そうすると、そもそも相手の細縁メガネが高慢な印象を与えて嫌いなのかもしれませんし、仕事を頼んだ時に顔をしかめる癖が嫌いなのかもしれません。さらに、仕事をなんでもそつなくこなし、なんとなく自慢げである感じが高慢な印象を与えている感じもあるでしょう。
これらのことは、「外見」「言動」「考え方」といったカテゴリー分けができそうです。
こうして、自分が嫌いな原因をどんどん分析し、細かな原因までも探っていきます。
すると、だんだん自分の「嫌い」という感情を客観視できるようになってくると思います。
自分との相違点・共通点を探す
そこまできたら、あとはもう一歩です。嫌いな部下と自分の共通点・相違点を15個を目標に探してみましょう。
ここでの狙いは、自分と相手の両方を客観視するところにあります。
例えば、自分にも部下のように感情を表に出してしまう癖があるかもしれません。実は、自分もメガネをかけているかもしれません。でも、相手は細縁で自分は太縁であるという違いがあるかもしれませんね。
共通点も、相違点も15個ほど書き出せた暁には、なんとなく相手への苦手意識が薄れているのではないでしょうか。
嫌いな部下と仕事をするために

では、嫌いな部下への感情を分析して苦手意識を薄められたら、具体的にそのあとどうのように仕事を行えばいいのか解説します。
仕事であると割り切る
第一にはこれにつきます。仕事であると割り切れれば、嫌いな部下ともなんとか接することができるでしょう。
さらに、嫌いな理由を分析できていたら、その嫌いを埋めるような指示の仕方をするといいでしょう。
具体的には、仕事が雑だと感じる社員には、少し割り振る仕事の量を減らしてこれには「これだけの時間をかけてみて」と指示してみましょう。
他にも、「意欲がない」という社員には割り振っている仕事の重要性を伝えてみることも1つの手です。チェック体制を万全にしてからあえて重要な仕事を振ってみるということもいいかもしれませんね。
こうして仕事であると意識して人間関係を築くと、嫌いへの執着が薄れて仕事がうまく進んでいくはずです。
関連記事:パワハラとは?パワハラにならない4つの指導方法と裁判事例2つ
嫌いな部下と付き合うメリットを考える
嫌いな部下と付き合うメリットを考えて、そのメリットに着目して仕事を行うことも重要です。
例えば、誰もが扱いにくいと感じる部下が苦手なら、その部下をうまく使いこなせれば社内での評価が上がりそうですよね。
さらに、仕事が遅い部下を一人前まで育てることができればマネジメント能力が買われるでしょう。
このように、部下と付き合うと得られるメリットをあげてみると、嫌いな部下と付き合うモチベーションも上がってきます。
どうしても相性が合わない場合の対処法
部下との関係改善に努めても、どうしても相性が合わず、ストレスが溜まり続けてしまうこともあります。上司も人間である以上、すべての部下と完璧に関係を築くことは現実的ではありません。このような場合は、無理に感情を抑え込まず、冷静に状況を整理し、適切な対応を取ることが重要です。
人事・上長への相談の目安
相手に改善の余地が見られず、あなた自身の精神的負担が大きくなってきた場合には、人事や上長に相談することをためらう必要はありません。
特に以下のようなケースでは、第三者の介入が有効です。
- 指導を繰り返しても態度が変わらない
- 他のメンバーからも苦情が出ている
- 感情的な対立が表面化し、業務に支障が出ている
- 自身のメンタルが限界に近づいている
相談の際は、感情的な言葉ではなく、具体的なエピソードや行動事実を整理して伝えるようにしましょう。客観的な視点を持つことで、組織としても判断がしやすくなります。
チーム編成やタスク分担の見直し
相性が悪い相手と距離を取るために、業務の配置やチーム編成を見直すのも1つの手段です。
例えば:
- 別プロジェクトへの異動を検討する
- 担当業務を調整し、直接の関わりを最小限にする
- メンターや別の上司の下で育成を進めてもらう
このような対処は、「逃げ」と見なされることもありますが、チーム全体のパフォーマンスや心理的安全性を守るための有効な戦略でもあります。
重要なのは、個人攻撃にならない形で、「どうすればお互いにパフォーマンスを発揮できるか」という観点で提案・調整を行うことです。
上司自身のストレスケアも大切
部下との関係が悪化したままでは、上司自身のメンタルも疲弊しやすくなります。自分自身をケアする習慣を持つことは、マネジメントを続けるうえで不可欠です。
具体的な方法:
- 上司同士で悩みを共有し、客観視する
- 毎週1回、感情を振り返る時間を設ける
- 深呼吸や瞑想、ウォーキングなどで心を整える
- 完璧を求めず、「できる範囲」での対応を受け入れる
感情のコントロールは意志だけでは困難です。仕組みとしてリフレッシュの時間を組み込む、相談できる関係性を持つといった環境づくりが、ストレス軽減に大きく貢献します。
終わりに
嫌いな部下がいるということは人として自然な感情です。そこで、嫌いな感情をどう乗りこなすかということが自分の腕の見せ所。
うまく人間関係の鬱憤をのりこえて、いい社内の雰囲気を作っていきましょう。
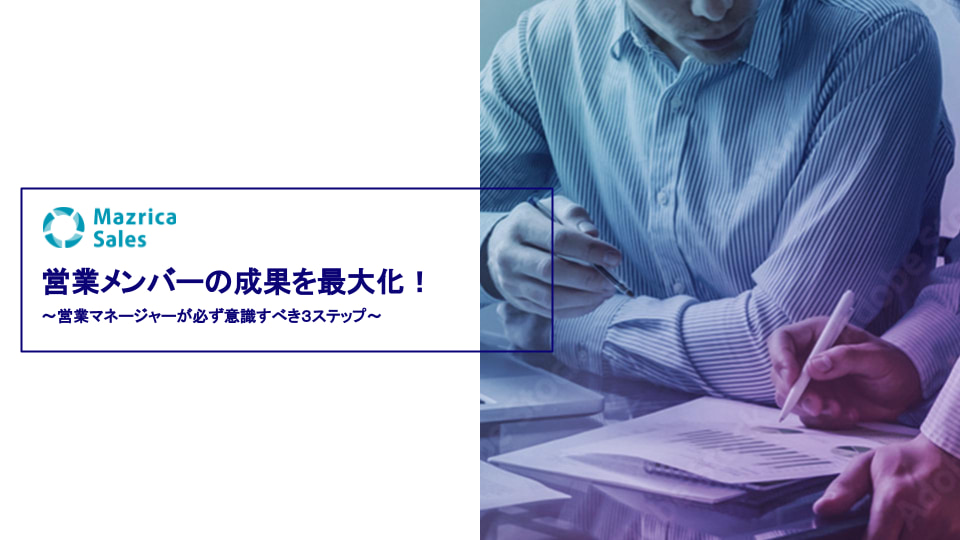
営業メンバーの成果を最大化! ~営業マネージャーが必ず意識すべき3ステップ~
セールスマネジメントのポイントとして戦略立案から部下のモチベーション管理まで3つの観点でまとめています。営業のマネジメントに関わる方向けの資料です。
資料をダウンロードする