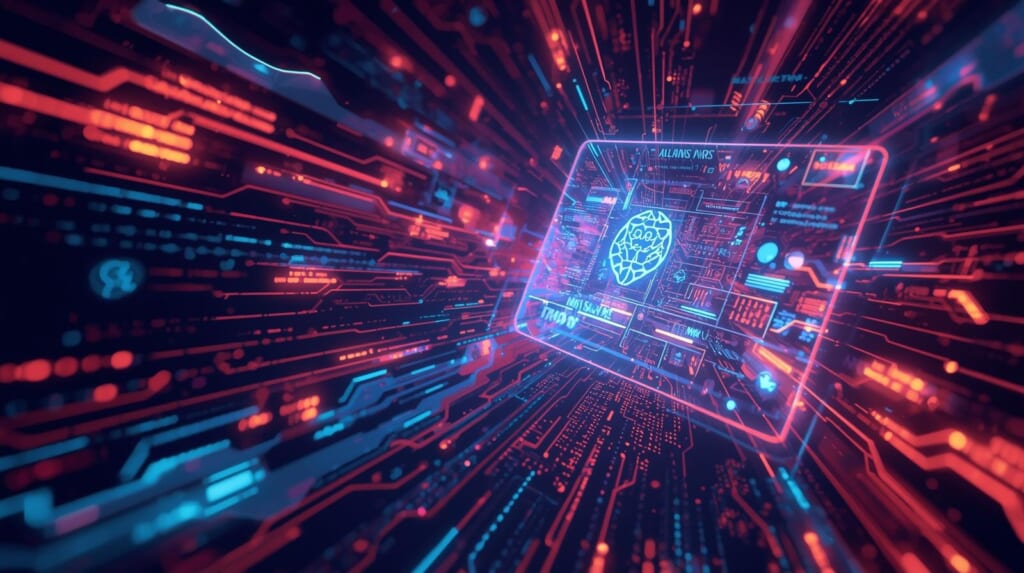近年、ビジネスの舞台は急速にデジタルへと移行し、特にBtoB企業にとって、デジタルマーケティングはもはや選択肢ではなく必須の戦略となっています。
かつて主流だったアナログな営業手法だけでは、変化した顧客の購買行動に対応しきれません。
本記事では、このBtoBデジタルマーケティングの基本から、ウェブマーケティングやコンテンツマーケティングとの違い、そしてなぜ今、これほどまでに重要視されているのかを深掘りします。
さらに、具体的なメリットや効果的な手法、そして導入を成功させるためのステップと役立つツールまで、網羅的に解説します。
この記事の内容
BtoBデジタルマーケティングとは?
「BtoBデジタルマーケティング」とは、文字通り企業間の取引(BtoBビジネス)においてデジタル技術を活用するマーケティング手法を指します。
まずは、この「デジタルマーケティング」という言葉の基本的な意味から紐解いていきましょう。
デジタルマーケティングとは、インターネットやあらゆるIT技術を利用したマーケティング手法全般のことです。
かつては、訪問営業やテレビ・新聞広告といったアナログ的な手段が主流でした。しかし、インターネットの飛躍的な発展とともに、ウェブサイト、SNS、ウェブ広告、メール、アプリなど、多様なデジタルチャネルを活用するマーケティング手法が登場しました。
現在では、業務効率の向上や、少ないコストで大きな成果を得られる点が評価され、デジタルマーケティングは従来の手段に代わり、多くの企業で標準的に採用されています。
データに基づいた効果測定が可能であるため、PDCAサイクルを迅速に回し、継続的な改善を追求できるのも大きな特徴です。
ウェブマーケティングとの違い
「デジタルマーケティング」と混同されやすい言葉に「ウェブマーケティング」がありますが、両者の違いはその「範囲」にあります。
ウェブマーケティングは、ウェブサイトやインターネット上で行われるマーケティング活動全般を指します。
具体的には、Google検索での上位表示を目指すSEO対策や、リスティング広告、SNS広告の出稿などがこれに該当します。
一方で、デジタルマーケティングはウェブの範囲に留まりません。例えば、スマートフォンの位置情報や行動履歴といったオフラインでのビッグデータをデジタルで分析し、実店舗への来店促進や売上向上を図るといったこともデジタルマーケティングに含まれます。
つまり、ウェブマーケティングが「ウェブの世界の中だけ」に焦点を当てるのに対し、デジタルマーケティングは「ウェブの世界に留まらず、あらゆるデジタル技術とデータを活用する」という点で異なります。
コンテンツマーケティングとの違い
コンテンツマーケティングとは、「顧客にとって価値のあるコンテンツを作成し、提供することで顧客獲得や育成を目指すマーケティング手法」のことです。
ブログ記事の投稿、ホワイトペーパーの作成、オンラインセミナーの開催などがその代表例です。これらの手法はデジタルチャネルを通じて行われることが多いため、「コンテンツマーケティングはデジタルマーケティングの一部」と捉えることができます。
しかし、コンテンツマーケティングはデジタルコンテンツに限定されません。
例えば、顧客にとって有益な情報が掲載されたチラシやDM(ダイレクトメール)、FAXを企業へ送付するといったアナログな手法もコンテンツマーケティングに含まれます。
したがって、コンテンツマーケティングが「デジタルとアナログ両方の手法」を取るのに対し、デジタルマーケティングは「デジタル技術を活用した手法のみ」である点が両者の違いとなります。
関連記事:【2025年最新版】コンテンツマーケティングとは?メリット・手法・成功事例をわかりやすく解説!
BtoBデジタルマーケティングの重要性
では、なぜ今、BtoB企業にとってデジタルマーケティングが不可欠なのでしょうか?ここでは、その具体的な理由を2つの視点から深掘りして解説します。
Webでの比較検討が一般化している
かつてのBtoBビジネスにおいて、顧客が商品やサービスに関する情報を得る手段は非常に限られていました。
主な情報源は既存取引先の営業担当者からであり、新規の製品やサービスを検討する際には、限定的な広告や新聞記事などに頼るしかありませんでした。
しかし、現代の顧客は違います。購買を検討する際、まずGoogleなどの検索エンジンや専門の情報サイト、SNSなどを活用して、自ら能動的に広範な情報収集を行うのが一般的になりました。
営業担当者と接触する頃には、既にサービスの比較検討や課題の明確化がある程度進んでいるケースも少なくありません。
この顧客行動の変化に対応するため、BtoB企業はもはやオフラインでの営業活動だけに依存することはできません。
顧客が情報収集を行うWebという舞台で、自社の製品やサービスを戦略的にアピールし、顧客が求める情報を提供することが不可欠となっているのです。
認知拡大にデジタル戦略が不可欠になっている
顧客がWeb検索を通じて情報収集を行う機会が増えたことは、裏を返せば、デジタルコンテンツとして情報発信しなければ、自社の製品やサービスが顧客に認知されにくくなったことを意味します。
従来の飛び込み営業やDM送付といったオフラインの手法は、確かに今も有効な場合がありますが、その効果は限定的になりつつあります。
現代においては、自社のWebサイトを立ち上げて専門性の高いブログ記事を発信したり、SNSでターゲット層に響く情報を継続的に配信したりする方が、効率的かつ広範囲に商品・サービスを認知させる上で非常に有効な手段となっています。
デジタル戦略なくして、現代の市場で存在感を示すことは極めて困難だと言えるでしょう。
BtoBデジタルマーケティングを行うメリット
次に、デジタルマーケティング導入によって得られる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
顧客に最適化した施策が打てる
デジタルマーケティングの最大のメリットの一つは、顧客の興味関心度や購買フェーズに合わせて、個別にアプローチを最適化できる点にあります。
業種、役職、年齢といった属性情報に加え、Webサイトの閲覧履歴やダウンロードしたコンテンツといったオンライン行動データを蓄積・分析することで、リードが抱える具体的な課題やニーズを高い精度で推測できるようになります。
従来の営業では、担当者が個別にヒアリングを行ったり、手作業でメールの内容を調整したりするため、対応できるリード数や提案の質には限界がありました。
しかし、MA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援システム)といったツールを活用することで、これまで手作業で行っていた多くのプロセスを自動化・効率化できます。
これにより、営業担当者は何倍ものリードに対して質の高いパーソナライズされたアプローチが可能となり、具体的な商談数の増加や、顧客ニーズへの迅速な対応による成約率向上が期待できます。
リード獲得のコストが下がる
デジタルマーケティングは、費用対効果の高いリード獲得を可能にします。
ブログ記事、SNS投稿、動画コンテンツなどを一度作成・配信すれば、インターネットを通じて不特定多数のユーザーの目に触れる機会が生まれ、一度に大量のリードを獲得することも夢ではありません。
これらのデジタルコンテンツは、一度作成すれば継続的に活用できるため、極めてコストパフォーマンスに優れていると言えます。
電話営業や展示会などのオフライン手法は、アプローチできる人数に限りがある上、人件費や会場費といった多大な集客コストが発生します。
対照的に、デジタルマーケティングでは、これらの集客コストを大幅に抑えながら、より多くの見込み客にリーチし、効果的にアプローチすることが可能になるのです。
関連記事:リード獲得とは?見込み顧客を集める15の施策と成功のポイント
競合との差別化が図れる
まだデジタルマーケティングの導入が遅れている業界においては、いち早く取り組むことで競合他社に対する決定的な優位性を確立できます。
顧客が情報収集を行うデジタル空間で積極的にプレゼンスを高めることで、自社製品・サービスの認知度において競合と大きな差をつけることが可能です。
これにより、オフラインからの成約に加え、Webサイトからの問い合わせや資料請求、オンライン経由での受注といった新たな収益源を確保できます。
デジタルマーケティング戦略をいち早く推進することは、市場における競争力を高め、他社よりも売上を大きく伸ばす可能性を秘めているのです。
BtoBデジタルマーケティングの代表的な手法
デジタルマーケティングを営業活動に組み込む上で、どのような手法を活用すべきでしょうか。
ここでは、BtoBデジタルマーケティングにおいて特に効果を発揮する5つの主要な手法について解説します。
SEO
SEOは「Search Engine Optimization」の略で、自社のWebサイトコンテンツをGoogleなどの検索エンジンで上位表示させるための取り組みを指します。
BtoBデジタルマーケティングにおいては、主にリードジェネレーション(見込み客獲得)の強力な手段として活用されます。
顧客が抱える課題や疑問を解決するような質の高いコンテンツを作成し、検索結果の上位に表示させることで、ターゲットとなる多くのユーザーを自社サイトへ効果的に誘導できます。
流入したユーザーを、問い合わせフォームへの誘導や資料ダウンロードへと促すことで、購買意欲の高いリードへと転換させることが可能になります。
関連記事:コンテンツSEOとは? 成果を出す8つの手順とメリットを解説
SNS
X(旧Twitter)やInstagram、LINEなどのSNSを活用した情報発信は、BtoBデジタルマーケティングにおいてリードジェネレーションとリードナーチャリング(見込み客育成)の両面で有効です。
リードジェネレーションの場面では、SNS投稿を通じて自社サイトへのアクセスを促したり、有益な資料のダウンロードを案内したりすることで、新たなリードを獲得できます。
一方、リードナーチャリングにおいては、フォロワーに対して継続的に役立つ情報や企業としての価値観を発信し続けることで、自社への共感を深めてもらい、中長期的な関係性を構築します。
Web広告
ウェブ広告とは、インターネット上に掲載される広告全般を指し、BtoBデジタルマーケティングでは主にリードジェネレーションに用いられます。
広告を掲載できる場所は、Google検索結果、Webサイト、主要SNSなど多岐にわたります。
ターゲットを絞り込んだウェブ広告を出稿することで、関心の高いユーザーを効率的に自社サイトへ誘導し、スピーディなリード獲得を目指します。
特に、緊急性の高い課題を持つ顧客や、特定のキーワードで検索している顧客に対して効果的にリーチできるため、短期間での成果創出に貢献します。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、ビジネスにおける特定の課題解決策や有益な知見、調査データなどを体系的にまとめた資料です。
BtoBデジタルマーケティングでは、リードジェネレーションとリードナーチャリングの双方で非常に重要な役割を担います。
リードジェネレーションでは、自社サイトにホワイトペーパーのダウンロードフォームを設置し、企業名や担当者の連絡先などの入力と引き換えに提供することで、購買意欲の高いリード情報を獲得します。
リードナーチャリングでは、獲得した見込み客に対して、その興味やフェーズに合わせた関連性の高いホワイトペーパーを継続的に提供することで、専門知識や信頼性をアピールし、購買意欲を段階的に高めていくことができます。
関連記事:ホワイトペーパーの作り方を7ステップで解説!成果が上がるコツも紹介
メールマガジン
メールマガジンは、BtoBデジタルマーケティングにおいてリードジェネレーションとリードナーチャリングの両方で活用される汎用性の高い手法です。
リードジェネレーションでは、自社Webサイトにメールマガジン登録フォームを設置し、興味を持ったユーザーに氏名やメールアドレスを登録してもらうことで、リード情報を獲得します。
リードナーチャリングにおいては、登録された購読者に対し、定期的に役立つ情報や最新のニュース、セミナー案内などを配信することで、顧客との継続的な接点を創出します。これにより、企業の信頼性を高め、見込み客の購買意欲を醸成し、最終的に商談へと繋げる重要な役割を果たします。
顧客一人ひとりの関心度に応じて内容をパーソナライズすることで、さらに効果を高めることができます。
関連記事:【初心者向け】メルマガの始め方ガイド|作成から一斉配信、効果測定まで完全解説
BtoBデジタルマーケティングの始め方
BtoBデジタルマーケティングを効果的に導入するためには、以下の5つのステップを踏むことが不可欠です。
- ペルソナを設定する
- カスタマージャーニーマップを設計する
- 戦略を策定する
- 施策を実施する
- 効果測定とPDCAサイクルを回す
次章から、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
1.ペルソナを設定する
BtoBデジタルマーケティングの最初の、そして最も重要なステップは、自社の製品・サービスを購買する理想的なターゲット企業やその担当者を具体的に「ペルソナ」として設定することです。
担当者のペルソナを深く掘り下げる際には、単なる部署や役職、年齢といった基本情報に留まりません。
彼らの情報収集の方法(例:検索エンジンを多用するのか、SNSから情報を得るのか)、抱える課題、業務上の目標、さらには休日の過ごし方まで、詳細な属性や行動パターンを具体的に描き出します。
ペルソナを細部まで作り込むほど、どのデジタルコンテンツが、どのターゲットに最も響くかという照準が定まりやすくなります。
関連記事:ペルソナマーケティングとは?ペルソナの設定方法から注意点まで
2.カスタマージャーニーマップを設計する
ペルソナ設定の次に必要なのが、顧客の購買行動プロセスを詳細に分析し、「カスタマージャーニーマップ」として可視化することです。
カスタマージャーニーマップとは、顧客が自社の製品・サービスを「知る」段階から「比較検討」を経て最終的に「購入・契約」に至るまでの心理状態や具体的な行動の一連の流れを「旅」に見立てて表現したものです。
「認知」「興味関心」「情報収集」「比較検討」「意思決定」といった各フェーズにおいて、顧客がどのような感情を抱き、どのような情報に触れ、どのような行動を取るのかを具体的に仮説立ててマップに落とし込みます。
このマップを作成することで、顧客の視点から購買プロセスを理解し、各接点で提供すべき情報やアプローチ方法を戦略的に検討するための基盤を築くことができます。
関連記事:カスタマージャーニーマップとは?作り方やメリット・事例【テンプレート付き】
3.戦略を決める
カスタマージャーニーマップが完成したら、次に具体的なデジタルマーケティング戦略を策定します。
これは、各カスタマージャーニーフェーズにおける顧客の行動や情報収集に合致する、最適なデジタルコンテンツやメディアを特定し、全体の方向性を定めるプロセスです。
この段階では、デジタルマーケティングを通じて達成したい最終的な経営目標(KGI:Key Goal Indicator)を明確に設定します。
例えば、「年間売上〇〇円達成」など、具体的で測定可能な目標を置きます。そして、そのKGIを達成するために追うべき具体的なプロセス目標(KPI:Key Performance Indicator)も同時に設定しましょう。
例えば、「Webサイトからのリード獲得数〇件」「商談化率〇%」といった形で、各施策の成功を測る指標を定めます。
関連記事:マーケティング戦略とは?立案手順・フレームワーク・成功事例を解説
4.施策を実施する
カスタマージャーニーマップが完成したら、次に具体的なデジタルマーケティング戦略を策定します。
これは、各カスタマージャーニーフェーズにおける顧客の行動や情報収集に合致する、最適なデジタルコンテンツやメディアを特定し、全体の方向性を定めるプロセスです。
この段階では、デジタルマーケティングを通じて達成したい最終的な経営目標(KGI:Key Goal Indicator)を明確に設定します。
例えば、「年間売上〇〇円達成」など、具体的で測定可能な目標を置きます。
そして、そのKGIを達成するために追うべき具体的なプロセス目標(KPI:Key Performance Indicator)も同時に設定しましょう。例えば、「Webサイトからのリード獲得数〇件」「商談化率〇%」といった形で、各施策の成功を測る指標を定めます。
関連記事:KPIとは?基本から設定方法、業種別の指標事例まで徹底解説
5.効果測定とPDCAサイクルを回す
施策実施後、一定期間が経過したら、必ずその効果を定量的に測定します。
Webサイトのアクセス数、コンバージョン数(資料ダウンロード数、問い合わせ数など)、リード獲得単価、商談化率といったKPIの目標値と実績を比較し、改善すべきポイントを具体的に洗い出します。
オフラインマーケティングでは把握が難しかったこれらの効果も、デジタルマーケティングでは詳細なデータをリアルタイムで収集・分析できるのが最大の強みです。
このデータを基に、「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」というPDCAサイクルを継続的に高速で回すことが、デジタルマーケティングを最適化し、最大の成果を引き出すための絶対条件となります。
関連記事:PDCAサイクルとは?業務改善につながる回し方のコツやOODAとの違いを解説
関連記事:埋もれたデータを「成果」に変えるデータドリブン営業の極意
BtoBデジタルマーケティングを施行する3つのポイント
BtoBデジタルマーケティングを成功させるためには、ただ施策を実行するだけでは不十分です。
ここでは、その導入と運用において特に意識すべき3つの重要なポイントを解説します。
戦略・具体的なアクションプランを策定する
デジタルマーケティング施策を実行する前に、自社の状況に合致した戦略を設計し、それに基づいた具体的なアクションプランを明確に立てることが重要です。
目的意識のないまま手探りで進めても、成果にはつながりにくいでしょう。
具体的には、以下の項目を詳細に設定していきます。
目的: デジタルマーケティングを通じて何を達成したいのか(例:リード獲得数の〇〇%増加、商談化率の改善など)
強み: 自社製品・サービスのどのような点が市場で優位性を持つのか
ターゲット: どのような企業、担当者層にアプローチしたいのか(ペルソナの詳細化)
施策: ターゲットに到達し、目的を達成するためにどのようなデジタルマーケティング手法を用いるのか
せっかく優れた戦略を立案しても、日々の業務で「具体的に何をすれば良いのか」が不明確では、実行に移すことはできません。
そのため、戦略と合わせて、各担当者がどのような手順で、いつまでに、何を達成するのかという具体的なアクションプランまで落とし込むことが不可欠です。
スモールスタートで始める
デジタルマーケティングの導入は、最初から会社全体で大々的に実施しようとすると、往々にして壁にぶつかります。
従来の営業・マーケティング手法に慣れ親しんだ社員や、デジタルツールへの苦手意識を持つ社員からの反発に遭い、円滑な進行が難しくなるケースも少なくありません。
そのため、まずは担当チームや少数の担当者を選定し、試験的にスモールスタートで始めることを強くお勧めします。小さく成功体験を積み重ね、具体的な成果を社内で示すことで、デジタルマーケティングの効果を可視化できます。
これにより、徐々に社内の理解と協力を得やすくなり、スムーズに全社的な展開へと移行できるでしょう。成功事例を共有し、成功体験を広げていくことが、社内浸透の鍵となります。
適切なKPIを設定する
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を適切に設定することも、デジタルマーケティングの成功を測る上で不可欠です。
プロジェクトの最終目的であるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を頂点とし、その達成に必要なKPIを段階的に設定したものが「KPIツリー」です。
多くのBtoB企業にとってのKGIは、具体的な受注数や売上目標となるでしょう。このKGIから逆算し、達成に直結する以下のようないくつかの指標をKPIとして定めていきます。
- サイトアクセス数
- 申し込み件数
- 問い合わせ件数
- 資料ダウンロード件数
- SNSフォロワー数
- 訪問数
- 回遊率
- CV数(コンバージョン数)
- CVR(コンバージョン率)
これらのKPIをあらかじめ設定した上で戦略を実行し、定期的に効果測定を行うことが重要です。
KPIと実際の数値との乖離を分析することで、どの施策が奏功し、どの部分に改善の余地があるのかを明確に把握できます。
オフラインマーケティングでは難しかった効果の定量的な測定とデータに基づく最適化こそが、デジタルマーケティングの最大の強みであり、持続的な成果へと繋がるのです。
AI活用でデジタルマーケティングを効率化する
近年、デジタルマーケティングの進化を牽引しているのがAI(人工知能)です。
膨大なデータを分析し、顧客行動に対する深い洞察を提供することで、業務の効率と精度を大幅に向上させています。
デジタルマーケティングにAIを導入するメリット
AIの導入によって、デジタルマーケティングのさまざまな領域にメリットがあります。
まず、AIは膨大な顧客データを高速かつ正確に処理し、これまで見落とされがちだった行動パターンや相関関係を明らかにします。そのため、顧客ニーズの予測精度が向上し、よりパーソナライズされたマーケティング施策の実現が可能となります。
また、MAツールと連携させることで、見込み客の行動履歴から購買意欲を自動的に評価し、リードの優先順位を可視化できます。営業担当者は確度の高い顧客に集中することができ、商談の効率と成果が飛躍的に向上します。
さらに、AIはブログ記事や広告文の作成支援にも活用されており、コンテンツ制作にかかる時間とコストを削減します。効果的なクリエイティブを自動生成することで、広告パフォーマンスの改善にもつながります。
ウェブ広告の分野においては、キーワードの選定や入札単価の調整をAIが自動化し、広告費用の最適化と運用効率の向上を実現します。その結果として、高い広告費用対効果(ROAS)も期待できます。
デジタルマーケティングにAIを活用する注意点
AIの導入は多くのメリットをもたらしますが、その一方で注意すべき点も存在します。
まず、AIの精度は投入されるデータの質に大きく依存しているため、正確かつ最新のデータを継続的に整備・管理する体制が必要です。また、個人情報を扱う場合には、法的・倫理的な観点からプライバシー保護への配慮が不可欠です。
さらに、AIはルーチン作業の自動化には優れているものの、戦略の立案や顧客との信頼関係の構築といった、創造性や感情的なつながりを必要とする業務は、依然として人間の役割です。AIによってすべてを
自動化・置き換えるのではなく、人間の業務を補完し強化するツールとして位置づけることが重要です。
そのためには、AIの活用に合わせて人材のスキルアップを図り、組織全体の業務体制やプロセスを見直すことが不可欠となります。
BtoBデジタルマーケティングに便利なツール
BtoBデジタルマーケティングの大きな利点の一つは、顧客の興味関心などのデータを詳細に蓄積できる点にあります。
データの力を最大限に引き出し、施策を成功させるためには、適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、データ分析や記録、さらには業務効率化に役立つ主要なツールを3つご紹介します。
MA
MAは、その名の通りマーケティング業務の多くのプロセスを自動化し、効率を飛躍的に向上させるためのシステムです。
このツールには、多数のリード(見込み客)を一元的に管理する機能が備わっています。
さらに、リードがWebサイト上でどのような行動を取ったかを追跡するトラッキング機能や、リード一人ひとりの関心度に合わせてパーソナライズされたメールを自動で配信する機能も持ち合わせています。
また、顧客の閲覧履歴に応じて表示するWebページの内容を自動で切り替えるパーソナライズ機能も搭載されています。
関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介
SFA/CRM
SFAとCRMは、営業活動を強力に支援するとともに、顧客との関係性を一元的に管理する機能を兼ね備えたツールです。
このシステムは、顧客の基本情報はもちろんのこと、営業担当者のスケジュール管理、過去の商談履歴、提案内容、さらには受注予測といった営業活動に関わるあらゆるデータを集約・分析できます。
営業担当者が日々行っている業務の多くを効率化できるだけでなく、各案件の進捗状況や実績がデータとして入力されることで、それが可視化され、組織全体でリアルタイムに共有可能となります。
また、過去の成約条件や成功事例が蓄積されるため、営業ノウハウが個人の経験に依存することなく、チーム全体で共有され、組織としての営業力強化に貢献します。
関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説
アクセス解析ツール
アクセス解析ツールは、自社が運営するWebコンテンツへのアクセス状況や、サイトを訪れるユーザーの属性を詳細に分析するためのツールです。
Google Analyticsなど、無料で利用できる高機能なツールも存在します。このツールを活用することで、各ページのPV数(ページビュー数)やセッション数、ユニークユーザー(UU)数といった基本的な指標を把握できます。
加えて、サイト内でのユーザーの回遊率や離脱率、特定のページからの直帰率、そして目標達成度合いを示すコンバージョン率など、ユーザー行動の深層を理解するための多様なデータを得ることが可能です。
さらに、ユーザーがどこからサイトに流入してきたのかという経路や、過去の閲覧履歴、行動履歴、さらには性別や年代といったユーザー属性まで解析できるため、デジタルマーケティング施策の効果を客観的に評価し、継続的な改善を図る上で欠かせないツールです。
関連記事:アクセス解析とは?サイト改善に必要な基礎知識|オススメツール9選も紹介
まとめ
デジタルマーケティングを実行する上で、特に重要なのがMAとSFA/CRMのシームレスな連携です。
リード獲得から育成、商談、そして顧客管理までの一連の流れをデータで繋ぎ、部門間の壁をなくすことで、顧客へのパーソナライズされたアプローチが実現し、全体の業務効率と生産性を飛躍的に高めます。
弊社が提供するMazrica製品を活用すれば、MAからSFA/CRMをワンプラットフォーム上で利用でき、営業とマーケティングの連携に役立ちます。
以下に詳細の資料があるため、気になった方はぜひダウンロードしてみてください。