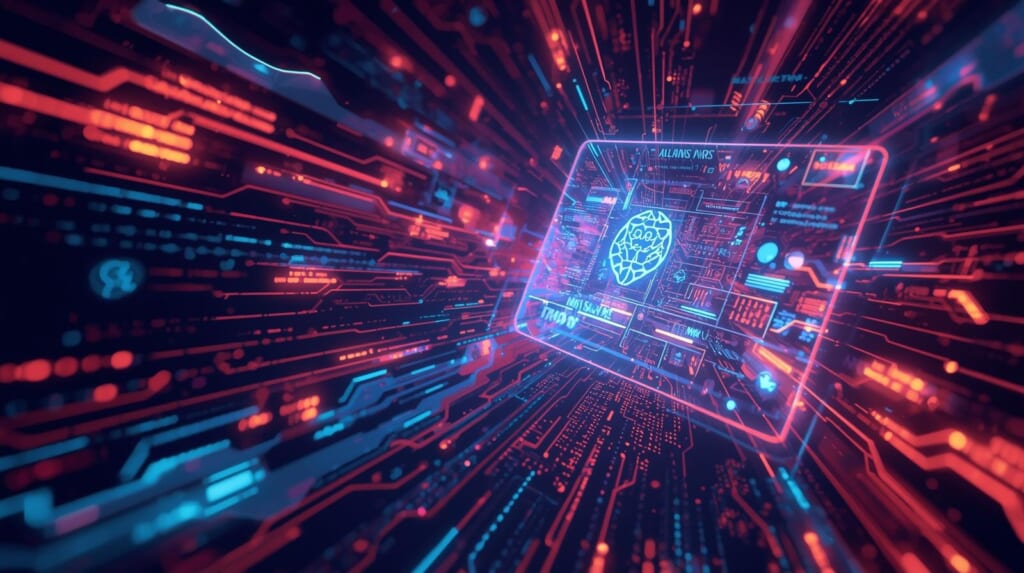ビジネスで生き残るためには「ユーザー視点」が欠かせません。
ユーザーにとって利便性の高い製品・サービスほど多くの需要を得られます。
このようなユーザーにとって使いやすいものは「ユーザビリティが高い」と表現され、ユーザビリティの向上は多くの企業が取り組んでいます。
そこで本記事では、ユーザビリティの定義や概要などをふまえ、ユーザビリティを向上させるためのポイントについて詳しく解説します。
この記事の内容
ユーザビリティとは?
ユーザビリティとはUseとAbilityを掛け合わせた言葉で、日本語では「使いやすさ」「有用さ」などと訳されます。
消費ニーズが多様化しユーザーの目が肥えている現代では、単に「機能が多い」「安い」というだけではモノが売れなくなっています。ユーザーにとっての利便性を重視した製品・サービスでなければ生き残ることができません。そこで「ユーザビリティ」が重要になるのです。
たとえばクラウドサービスを利用したときの「使いやすい」「わかりやすい」「見やすい」などは、ユーザビリティの高さにつながります。またWEBサイトを閲覧した際に「クリックしやすい」「表示されるスピードが早い」「知りたい情報が掲載されている」なども、ユーザビリティが高いと言えます。
このように製品・サービスを開発・提供する際には、ユーザビリティは欠かせない要素です。ユーザビリティが高い製品・サービスは、リピート購入や解約率低下などにもつながるでしょう。
ユーザビリティの改善には、指標となるデータの分析からスタートすることになるでしょう。
関連記事:データ分析とは?分析に求められる仮説思考とは?
ユーザビリティの定義
ユーザビリティは、国際標準化機構により定められたISO 9241で定義されています。
usability extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use
(特定のユーザーが特定の利用状況において特定の目標を達成するためにシステム、製品またはサービスを利用する際の、有効性、効率性そして満足度の度合い)
つまりユーザビリティを考える際には、以下の3項目が重要と言えます。
- 有効性
- 効率性
- 満足度
そしてこの3項目についても、ISO 9241にて定義されています。
「有効性」
accuracy and completeness with which users achieve specified goals
(ユーザーが特定の目標を達成する際の正確性と完全性)
有効性とは、正確かつ完全に目標を達成できるかどうかという指標です。ユーザーの目標を達成できなければ、ユーザビリティが優れているとは言えません。
「効率性」
resources used in relation to the results achieved Note 1 to entry: Typical resources include time, human effort, costs and materials.
(達成した結果において使用されたリソース:時間、労力、コスト、材料)
効率性とは、リソースをかけることなく目標を達成できるかどうかという指標です。目標が達成できたとしても多大な時間や労力などがかかっていると効率が良いとは言えず、ユーザビリティも低くなるでしょう。
「満足度」
extent to which the user’s physical, cognitive and emotional responses that result from the use of a system, product or service meet the user’s needs and expectations
(システム、製品またはサービスを利用した結果、ユーザーの身体的、認知的、および感情的な反応はどの程度ニーズを満たしているか)
満足度とは、ユーザーが期待通りの結果を得られたかどうかという指標です。この際、気持ちの面だけでなく身体的・認知的(思考的)な満足度も向上したときに、ユーザビリティが優れていると言えます。
関連記事:顧客満足度とは?CS向上のための4つのポイントとツール7選
ユーザビリティとアクセシビリティ、UI・UXの違い
ユーザビリティを考えるうえで知っておきたいのが「アクセシビリティ」です。アクセシビリティとはユーザビリティと関連のあるキーワードですが、どのような違いがあるのでしょうか。
また、ユーザビリティと混同されやすい「UI(ユーザーインターフェース)」「UX(ユーザーエクスペリエンス)」についても解説します。
アクセシビリティとは?
アクセシビリティとは「アクセスのしやすさ」という意味から「便利さ」「使いやすさ」などと訳されます。
ユーザビリティと大きく異なる点は、アクセシビリティは万人を対象としているというポイントです。
たとえば高齢者や身体に障がいをもっている人、病気で不自由な人などでも、少しの差もなくその製品・サービスを利用できることを示します。
またさまざまなデバイスや利用状況でも、問題なく利用できる使い勝手の良さを言います。
一方、ユーザビリティとは「特定の利用状況」における「特定のユーザー」にとっての使いやすさです。ターゲットとなる状況やユーザーが明確になっている点で、アクセシビリティとは異なる考え方になっています。
ユーザビリティをアクセシビリティと混同してしまうと、施策の方向性がブレてしまい本来ターゲットとすべきユーザーへのフォローが不十分になってしまうこともあります。違いを理解したうえで、自社はどちらを目指すべきなのか決めましょう。
UI(ユーザーインターフェース)とは?
UIとはUser Interface(ユーザーインターフェース)の略で、日本語では「ユーザーとの接点」と直訳できます。
たとえばWEBサイトの場合、ユーザーとWEBサイトの接点となるのは「ページのレイアウト」「フォントサイズ」「ボタンの押しやすさ」など、WEBサイトを構成する要素となります。
ユーザーはこれらのUIを通じてWEBサイトを利用し、その結果として「使いやすい」「見やすい」といったユーザビリティを感じます。
つまり優れたUIから優れたユーザビリティが生まれるため、相関的な関係であると言えます。
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは?
UXとはUser eXperience(ユーザーエクスペリエンス)の略で、日本語では「ユーザーの体験」と直訳できます。
ユーザーが製品・サービスを利用して得られた体験がUXであり、利用時だけでなく利用前や利用後も含まれます。
たとえば「このサービスは使いやすくて感動した」「この製品を使っても効果が得られなくて残念」といった体験や感想がUXにあたります。
ユーザーは製品・サービスの使用を通じて満足感を得られた場合、優れたUXを得られます。つまりユーザビリティが高い製品・サービスほど高いUXを得られると言い換えられます。
ユーザビリティの結果がUXという関係であると言えます。
ユーザビリティを構成する5つの要素
ユーザビリティの権威であるアメリカのヤコブ・ニールセン博士は、ユーザビリティに関わる複数ある指標のうち、特に重要だとして5つの要素を挙げています。
ちなみに同氏はシステムにおけるユーザビリティを提唱していますが、どのようなものにも当てはまる考え方として紹介させていただきます。
Learnability(学習のしやすさ)
ユーザーがすぐに作業を始められるよう、簡単に学習できるものでなければいけません。使い方が複雑だったり、習得するのに時間がかかったりしてしまうものは、ユーザビリティが高いとは言えないでしょう。
Efficiency(効率性)
ユーザーが操作を覚えられれば、高い生産性を上げられるような効率的なものである必要があります。せっかく操作方法を習得できたとしても、効率が悪いものであれば生産性にはつながらず、ユーザビリティが優れているとは言えません。
Memorability(記憶しやすさ)
しばらく使っていなくても、再度使う際にはすぐに使えるような覚えやすさも重要です。使い方が複雑なものは長い期間触れていないと使い方を忘れてしまいますが、ユーザビリティが高いものは久々に使ってもスムーズに使いこなせます。
Errors(エラーの発生頻度やその影響度)
ユーザーがエラーに遭わないよう、エラーの発生頻度は極限まで低くする必要があります。万が一エラーに遭ってしまっても、簡単に解決できるものであるべきです。さらに致命的なエラーは絶対に発生しないように調整しなければいけません。
Satisfaction(ユーザー視点の満足度)
ユーザーが主観的に満足できて気に入ってくれるよう、快適に使用できるようにします。ユーザーに総合的に満足してもらうために、楽しみながら使用できるよう意識しましょう。
ユーザビリティ向上のメリット
ソフトウェアやクラウドサービス、スマホアプリやWEBサイトなど、さまざまな製品・サービスにおいてユーザビリティ向上の動きが活発化しています。それではなぜユーザビリティが重視されているのでしょうか。
ユーザビリティの向上により、ユーザーが製品・サービスを利用する際のストレスが大きく軽減されます。
たとえば「表示速度が遅い」「知りたい情報がどこに載っているのか探しにくい」といったWEBサイトと、「専門家が分かりやすく情報を書いている」「レイアウトが工夫されていて見やすい」といったWEBサイトであれば、どちらが利用しやすいかは一目瞭然でしょう。
ユーザビリティが高ければ、ユーザーの満足度も当然ながら向上します。その結果、以下のような効果にもつながります。
- コンバージョン数の増加
- WEBサイトの離脱率低下
- サービスの解約率低下
- 商品のリピート購入
- アップセル・クロスセル
- 良い口コミの波及
ユーザビリティを高めてユーザーの満足度を向上させることで、結果として大きな効果が期待できるのです。
ユーザビリティの改善に必要なこと
製品・サービスの開発や提供において、重要な要素であるユーザビリティ。それではユーザビリティを高めるには、具体的にどのような方法があるのでしょうか?主なポイントや、ユーザビリティ向上に役立つツールを紹介します。
動作を軽くする
動作が軽快で、サクサクと進めると「ユーザビリティが高い」と感じられます。
たとえばスマホアプリを起動した際、動作が重くて思うように使用できなかったり途中で落ちてしまったりして、ストレスを感じた経験がある人も多いのではないでしょうか。このように動作が重いとユーザビリティが低下し、満足度も低くなります。
GoogleでもWEBサイトの質を評価する基準として、ページの読み込み速度や初回操作の反応時間などを組み込んでいます。これは「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」という指標で、この数値が優れているほどユーザーにとって有益なサイトであると判断されるため、検索順位が上位になるとしています。
このように、動作の軽快さはユーザビリティを高める要素として軽視できません。
操作方法を簡単にする
操作の簡便さもユーザビリティを高めるための大きな要因です。ヤコブ・ニールセン博士が掲げるように、学びやすく覚えやすい操作方法であることはユーザビリティを高めます。
たとえばシステムを利用する際、操作が複雑で難しいとなかなか覚えることができません。その結果「もう使いたくない」と思ってしまい、定着せずに止めてしまう可能性もあります。
またWEBサイトでも、ページ数が多すぎたり階層が深すぎたりすると、何回もクリックしなければユーザーが知りたい情報にたどり着けないためユーザビリティが低いと判断されてしまいます。
製品・サービスの提供の際には、簡単な操作で使えるよう工夫しましょう。
同時に、配色やデザインにも木を配ることをおすすめします。例えば、重要なボタンを目立たせるために色を工夫することで、使いやすさが向上します。
また、青などの寒色を使うことで、理知的で整然とした印象を与えることも可能です。配色が適切かどうか、ユーザーや機能に合わせて見直すことが重要です。
同時に、デザインをシンプルにすることで、ユーザビリティをさらに高められます。過度な装飾や複雑なデザインは使いにくい印象を与えかねない、無駄を省いた設計が効果的です。
ユーザーにとって利便性の高いコンテンツを充実させる
WEBサイト運営でユーザビリティを考える際には、コンテンツの「質」と「量」を重視しましょう。ユーザーにとって利便性の高い情報が網羅されている記事コンテンツを充実させることで、ユーザビリティの高いサイトと判断されます。
非常に高品質な記事コンテンツが1つしかないサイトも、記事コンテンツの数が多くてもすべて低品質なサイトも、どちらもユーザビリティが高いとは言えません。
ユーザーのニーズを満たす情報を網羅した記事コンテンツを、充分な数だけ発信しましょう。また公開している記事コンテンツをリライトし、質をブラッシュアップすることも大切です。
特定のユーザーの特定の利用状況を想定する
ISOにも定められている通り、ユーザビリティとは「特定のユーザー」が「特定の利用状況」における利便性です。そのため、ターゲットユーザーがどのような状況で利用するのか、どのような課題やニーズを持っているのか、を細かく想定したうえで自社製品・サービスを設計しましょう。
ターゲットユーザーにとって最適化されていれば、ユーザビリティも必然的に高まります。
アクセス解析を行う
ユーザビリティの改善にはアクセス解析ツールを用いることが有効です。
アクセス解析から得られるデータを活用することで、ユーザーの属性や行動を理解し、それに基づいてデザインや機能を改善できます。
たとえば、ユーザーがどの経路から訪れているのか、どの地域に住んでいるのか、使用しているデバイスや年齢、性別などが把握できます。
また、サイトへの訪問頻度やどのコンテンツに興味を持っているのかを確認することで、ユーザーのニーズをより深く理解することが可能です。
これにより、ユーザーの行動パターンに沿った適切な調整を行い、ユーザビリティを向上させることができるでしょう。
関連記事:アクセス解析とは?サイト改善に必要な基礎知識|オススメツール9選も紹介
データを蓄積してツールを活用する
ユーザビリティを高めるにはユーザー視点が必須ですが、社内にいると主観的になってしまい、どうしてもユーザー視点を忘れがちになります。ユーザーにとって最適化するためには、勘や経験に頼らずにデータを活用しましょう。
たとえばWEBサイトでは、ヒートマップを活用するとユーザーの行動を可視化できます。ヒートマップとはWEBページ上でユーザーが熟読した部分、クリックした場所、スクロールした場所などが色分けされて表示されるツールです。
このヒートマップを分析することで、ユーザーが求めている情報や興味を持っているトピックなどを把握でき、ユーザビリティ向上のための施策に役立てられます。
また被験者に協力してもらい、実際に製品・サービスを利用して使い勝手を検証してもらう「ユーザビリティテスト」も有効です。テストのデータを活用し、ユーザビリティを改善します。
関連記事:アクセス解析とは?目的・指標・手順とおすすめツール9選
【事例紹介】ユーザビリティが高いツールとは

ここで、具体的にユーザビリティが高い主に営業領域で活用できるツールを紹介します。
当社が開発・提供している「Mazrica Sales 」は、実際に利用する営業現場にとっての利便性にこだわったSFA(営業支援システム)です。
営業支援に特化したツール、SFA(営業支援システム)に関する記事はこちら:
さまざまな機能が搭載されていますが、特にユーザビリティが高いと好評なポイントは以下になります。
- 案件の進捗状況を一目で把握できる案件ボード
- 最終アクション日からの経過日数で色分けされる案件カード
- 企業名を入力しただけで企業情報を自動収集
- 名刺や議事録の情報が自動で文字起こしできるOCR機能
- GmailやGoogleカレンダーの内容が自動同期
- マルチデバイスで利用可能
- 受注確率や失注リスクを予測するAI機能
- ワンクリックで分析できるレポート機能
上記のように営業現場にとって便利かつ有用な機能を搭載しているだけでなく、Mazrica Salesは学習のしやすさにも力を入れています。簡単な操作で利用できるため、研修時間を設ける必要なく使いこなせるのが特徴です。
今後もユーザーの希望を取り入れた機能を追加し、ユーザビリティを向上させていく予定です。
営業現場で活用しやすいSFA・Mazrica Salesの詳細はこちらの資料内で詳しく解説しています詳しく解説しています。
▶︎▶︎Mazrica Salesの概要資料を無料ダウンロードする
終わりに
ユーザビリティの改善は、これからの時代に自社商材が生き残るための必須項目と言えます。製品やサービスの開発、WEBサイトの運営などを行っている企業は、ユーザーのニーズを満たしているかを考える機会を設けましょう。
ユーザビリティを改善する際には、主観的にならずに実際のユーザーの意見を取り入れることが重要です。既存顧客にヒアリングしたりユーザビリティテストを行いながら、今一度自社商材のユーザビリティを確かめましょう。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI
資料をダウンロードする