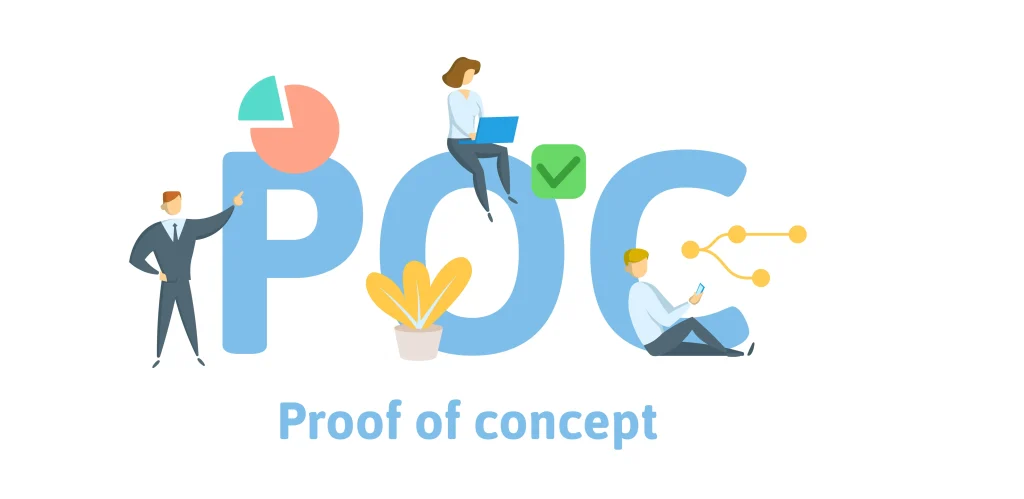市場環境が絶えず変化する中、事業の方向性に確信を持てずにいる方も多いのではないでしょうか。
競合の動きや顧客ニーズの変化、新規プレイヤーの台頭など、事業を取り巻く構造を的確に捉えることは、戦略策定において欠かせません。
そのための有効なフレームワークが、「ファイブフォース分析」です。
業界内外の競争要因を5つの視点から体系的に整理することで、自社の立ち位置やリスク、成長機会を見極める手がかりを得られます。
本記事では、ファイブフォース分析の基本概念から5つの脅威の具体的な内容、分析プロセス、他フレームワークとの比較までを網羅的に解説します。
戦略の精度を高めたい事業責任者の方は、ぜひご活用ください。
この記事の内容
ファイブフォース分析とは
ファイブフォース分析(Five Forces Analysis)とは、業界内の競争構造を把握し、自社の収益性や競争優位性を分析するためのフレームワークです。
この分析では、業界に影響を与える競争要因(フォース)をもとに、外部環境からの圧力や脅威を整理します。表面的な競合関係だけでなく、買い手・売り手・代替品・新規参入など、より広い視野での分析が可能な点が特徴です。
ファイブフォース分析の活用シーン
ファイブフォース分析は、以下のような場面で有効に機能します。
新規事業の参入判断
新たな市場に参入する際、その業界が持つ競争構造を把握することで、事業の成功可能性を予測できます。
例えば、「参入障壁が高く、新規プレイヤーが入りにくい市場」であれば、中長期的に安定した競争優位を築きやすいといえます。
逆に、競争が過熱していたり、代替品が多い市場では、参入リスクを慎重に検討する必要があります。
既存事業の成長戦略立案
すでに展開している事業についても、競争環境を再評価することで、成長の壁や新たな機会を見出すことができます。
例えば、サプライヤーの交渉力が高まりコスト構造が圧迫されている場合は、調達先の見直しやバリューチェーンの最適化が必要かもしれません。
ファイブフォースの5つの脅威
ファイブフォース分析では、業界に影響を及ぼす5つの競争要因を「脅威」として捉え、それぞれの強さや影響度を分析します。
この「脅威」は業界の収益性や競争の激しさを決定づける要素であり、事業戦略の立案において重要な判断材料となります。
5つの脅威について、詳しく解説します。
業界内の競争
同じ業界内の競合企業同士によるシェア争いや価格競争を指します。
競合の数が多く、差別化が難しい場合は、価格競争に陥りやすく、収益性が低下する傾向があります。
例えば、成熟した消費財市場ではブランド間の違いが少なくなり、値下げによるシェア拡大が主な戦略となるケースもあります。
新規参入者の脅威
新たな企業が市場に参入することで、既存プレイヤーのシェアが分散し、競争が激化するリスクを意味します。
参入障壁(資本・規制・ブランド力・ノウハウなど)が低い市場では、この脅威が高くなります。
具体的な例として、ソフトウェア業界などでは、技術力のあるスタートアップが次々と参入し、競争環境が流動的になる傾向があります。
代替品の脅威
自社の商品・サービスと機能的に同じ役割を果たす別の製品や手段の存在です。消費者が容易に乗り換えられる代替手段がある場合、価格競争や顧客離れのリスクが高まります。
一例として、飲食業界においては、外食・中食・宅配といった選択肢が代替し合う関係にあります。
買い手(顧客)の交渉力
顧客が持つ影響力や価格交渉力を指します。買い手の選択肢が多い場合や、大口顧客に依存している場合は、価格や提供条件の見直しを迫られる可能性があります。
BtoB取引においては、特定の大企業に売上の多くを依存している場合、買い手側の要求が経営に直接的な影響を与えることもあります。
売り手(サプライヤー)の交渉力
原材料・部品・技術などを提供する供給元(サプライヤー)の力を示します。
特定のサプライヤーに依存していたり、代替供給先が限られていたりすると、価格や納期の条件において不利な立場に立たされる可能性があります。
近年では、半導体や物流といった業界でサプライチェーンの脆弱性が課題となり、この脅威の影響が顕在化しています。
ファイブフォース分析の実施方法
ファイブフォース分析は単なる構造的な理解だけでなく、実践的な戦略立案に活かせるフレームワークであり、分析の効果を最大化するには順序を立てて進めることが重要です。
ここでは、ファイブフォース分析を実施する際の基本ステップを3段階に分けてご紹介します。
5つの要因を分析する
まずは、自社が属する業界において、以下の5つの競争要因を一つずつ丁寧に洗い出します。
- 業界内の競争:競合他社の数、差別化の度合い、価格競争の有無など
- 新規参入の脅威:参入障壁の高さ、規制の有無、技術的優位性など
- 代替品の脅威:機能的に代替され得る商品やサービスの存在と影響力
- 買い手の交渉力:顧客の数・規模、価格交渉力、スイッチングコストの低さ
- 売り手の交渉力:供給元の集中度、代替サプライヤーの有無、取引依存度
定性的な情報だけでなく、業界レポートや市場データを活用することで、より客観性の高い分析が可能になります。
関連記事:営業のデータ活用を推進する5ステップと企業のデータ活用事例
▶▶営業データを活用したマーケティング活動支援ツールの詳細はこちら
分析結果を評価する
各要因に対して「脅威が強いのか・弱いのか」「自社にとって有利か・不利か」を評価します。
脅威が強い場合は、収益性が圧迫されやすく、慎重な対応が求められます。
逆に、脅威が限定的であれば、競争優位性を築きやすい市場環境といえるでしょう。
例として、競合が少なく参入障壁が高い市場であれば、長期的に高い収益性を維持できる可能性があります。
事業戦略に組み込む
最後に、分析結果を踏まえて戦略立案に落とし込みます。
以下のような観点で、自社の強みやリスクへの対応策を明確にしていくことが重要です。
- 脅威が強い要因に対する対策(例:サプライヤー依存を減らす代替調達の検討)
- 競争優位を活かした戦略の策定(例:高いブランド力を武器にしたプレミアム戦略)
- 新規参入・撤退の意思決定材料としての活用
分析はあくまで「現状を正しく捉えるための手段」であり、それをどう戦略に反映させるかが成功の鍵を握ります。
ファイブフォース分析と他のフレームワークの違い
ファイブフォース分析以外に、ビジネスシーンでは多くの分析手法が用いられており、目的や視点によって適切な使い分けが求められます。
ここでは、代表的なフレームワークとの違いを整理しながら、ファイブフォース分析の独自性と活用のポイントを解説します。
SWOT分析との違い
SWOT分析は、自社の「強み」「弱み」「機会」「脅威」を整理することで、現状を多面的に把握する手法です。
内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)の両方を取り扱う点で、企業全体の総合的な分析に向いています。
一方、ファイブフォース分析は外部環境、特に業界構造と競争要因に焦点を当てた分析です。
業界の収益構造や競争の激しさを明らかにするためには、SWOTよりも精緻な視点が得られるといえます。
関連記事:SWOT分析とは?事例や分析手法をわかりやすく解説
3C分析との違い
3C分析は、「Customer(市場・顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つの視点から戦略を立案するフレームワークです。
マーケティング戦略やプロダクト戦略の立案時によく使われ、主に“競争優位の源泉”にフォーカスします。
ファイブフォース分析では、競合に加えて新規参入者・代替品・買い手・売り手といったプレイヤーも対象に含むため、業界構造の網羅的な把握に優れています。
使い分けとしては、3C分析は「市場のニーズと自社の提供価値をマッチさせる」場面で活用し、ファイブフォース分析は「競争環境の構造的な理解」に活用すると有効です。
まとめ
ファイブフォース分析について解説しまし。.いかがでしたでしょうか?
ファイブフォース分析は業界構造を構成する5つの視点から、市場の本質的な競争要因を浮き彫りにする効果的なフレームワークですが、あくまで構造を把握するための「起点」でしかないことも事実です。
実際の戦略に落とし込むためには、マーケティングや営業といった実務との接続が不可欠です。
事業戦略の今後の一手に迷いがある方こそ、まずは業界構造を俯瞰し、戦略とマーケティングの接点を見直すことが重要です。
ファイブフォース分析で構造を捉えたその先に、BtoBマーケティングの精緻な実践があります。
最新の統計データに基づいたBtoBマーケの動向や、成果に直結する実践知をまとめた資料もご用意しています。ぜひ戦略構築の一助としてご活用ください。