組織マネジメントとは、組織が円滑に機能し、効率よく目標達成や企業成長を実現するための考え方と手法です。人・モノ・カネ・情報といった経営資源を適切に管理し、最大限に活用する取り組みを指します。
本記事では、この組織マネジメントの基本を押さえたうえで、解決できる課題や代表的な理論を解説します。
この記事の内容
組織マネジメントとは?
組織マネジメントは、「ヒト・モノ・カネ・情報」という四つの経営資源を最適に配分し、組織全体を同じ方向へ導くマネジメント手法です。
たとえば“ヒト”では人材配置や評価制度を設計し、“モノ”では設備や在庫を管理、“カネ”では予算や投資配分をコントロールし、“情報”では社内外データを活用して意思決定をサポートします。
こうした資源をバランスよく活かすことで、生産性を高めながら事業目標の達成と企業価値の向上を同時に狙える点が特徴です。
任務を担うのは主に部長や課長などの管理職層ですが、現場メンバーの巻き込みも欠かせません。
トップダウンで示されたビジョンを部門戦略に落とし込み、さらに個人目標までブレイクダウンしてこそ、組織は一丸となって動けます。
近年は DX 推進やリモートワーク定着により、人材の多様化や働き方の柔軟性が増しています。組織マネジメントでは、心理的安全性の確保やデータドリブンな意思決定、柔軟な組織構造のデザインなど、ソフト面とハード面の両方から仕組みを整えることが重要です。
マネジメントとリーダーシップの違い
マネジメント=リーダーシップと語られていることもありますが、似て非なるもの。
リーダーシップはマネジメントの一部であり、必要なスキルの一つです。
ここを混同したままだと、この後の説明がわかりづらくなってしまうので、しっかり切り分けて読み進めていただければと思います。
マネジメント
組織の目標を達成するための戦略や仕組みをつくり、計画を実行、管理します。
メンバー一人ひとりの能力を最大限に発揮させる役割が求められており、結果よりも過程を重視してメンバーや組織を管理していきます。
関連記事:マネジメント能力とは?必要なスキルと高め方を徹底解説
リーダーシップ
メンバーを目標やビジョンの達成へと導いていくスキルです。
みんなを引っ張っていくという意味合いが強く、自分の考えをわかりやすく伝えたり、メンバーのモチベーションを高めていくことが求められます。
リーダーシップについては、こちらの記事内で詳しく解説しています。
関連記事:リーダーシップとは?リーダーに必要な10のスキルと取るべき8つの行動
組織マネジメントの種類
組織マネジメントには、大きく「トップダウン」「ボトムアップ」「ミドルアップダウン」という三つの代表的なアプローチがあります。
トップダウンマネジメント
まずトップダウン・マネジメントは、経営トップが自ら意思決定を行い、その方針を階層構造の下位へ順に伝えていく方式です。
この方法の強みは決裁スピードの速さにあり、緊急時や短期で成果を求める局面に向いています。ただし現場の意見が経営層に届きにくく、現実とのズレが拡大すると修正が難しくなる点が課題です。
ボトムアップマネジメント
対照的にボトムアップマネジメントは、現場の従業員が提案したアイデアを吸い上げ、合議を通じて経営陣が最終判断を下す手法です。
顧客に近い現場の知見や創意工夫が経営判断に反映されやすく、イノベーションが生まれやすい環境をつくれる半面、多くのステークホルダーを調整する必要があるため意思決定のスピードは遅くなりがちです。
また部門ごとの価値観に引きずられると全社最適を損なうリスクもあります。
ミドルアップダウンマネジメント
両者の長所を融合したのがミドルアップダウンマネジメントです。
これは経営陣が示したビジョンを中間管理職が現場レベルの言語へ翻訳して実行計画に落とし込み、同時に現場の声やデータをミドル層が経営層へ還流させることで、戦略とオペレーションを双方向に接続する方法です。
トップダウンの俊敏さとボトムアップの現場力を併せ持つ一方、中間管理職には高度な調整力と情報編集力が求められます。
ミドル層が機能しなければ情報が滞留し片側通行のマネジメントに逆戻りするため、権限設計や報連相の仕組みを整えることが成功の鍵となります。
組織マネジメントに役立つマネジメント理論
組織運営を設計するとき、「具体的にどこをどう変えればいいのか」を指し示してくれるのがマネジメント理論です。
現場でつまずいた際の指針となるだけでなく、改革案を社内で合意形成する際の“共通言語”にもなるため、最低限のフレームワークを押さえておく価値は大きいでしょう。
1. ドラッカーのマネジメント論
オーストリア出身の経営学者ピーター・ドラッカーは、マネジメントを「組織に成果をもたらすための道具・機能・機関」と定義しました。企業が保有するヒト・モノ・カネといった資源を顧客価値へ転換し、利益を生み出すことがマネジメントの本質だという考え方です。
組織の規模や業種を問わず応用しやすく、「成果(アウトプット)から逆算して資源を最適配分する」という視点をもたらしました。
ドラッカーの考え方を現場に落とし込むなら、まず事業部門ごとに「誰のどんな課題をどの資源で解決しているのか」を文章で整理し、採算や顧客価値の薄い活動に投下している人員や予算を段階的に縮小します。
加えて、社内会議を単なる情報共有の場から「成果を生むアクションを決める場」へと再設計し、議題は収益インパクトの大きさで優先順位をつけるようにします。これによりマネジメントが本来の目的である「成果創出」の道具として機能し始めます。
2. チャンドラーの「構造は戦略に従う」
アメリカの経営史学者アルフレッド・D・チャンドラーは、「組織は戦略に従う(Structure follows Strategy)」と提唱しました。
企業の成長過程を分析し、事業の拡大や多角化が進むほど、戦略を円滑に実行できる組織構造を築く必要があると説いています。
チャンドラーの理論を活かす企業は、成長フェーズで戦略が変わるタイミングを逃さず組織図を組み替えます。
新規事業を次々に立ち上げるスタートアップなら、機能別組織から事業部制へ移行し、PL責任を事業部長に一任することで意思決定を加速させます。
国内専業だったメーカーであれば、海外拠点を増設する局面で「地域×事業」のマトリックス型に切り替え、現地の市場特性に合わせた戦略を部門横断で調整できるようにします。
3. バーナードの「協働システム論」
米国の経営学者チェスター・バーナードは、組織が機能する条件として「共通目的」「コミュニケーション」「貢献意欲」の3要素を提示しました。
メンバーが共通のゴールを理解し、円滑に情報をやり取りし、互いに貢献する意志を持ってはじめて組織は存続できるという考え方です。
バーナードが提示した三要素を満たすために、まず共通目的の浸透を狙ってOKRやパーパスを四半期ごとに全社員と対話しながら更新し、各自の日常業務とリンクさせます。
コミュニケーションの質と量を高める施策としては、部門横断で参加できるSlackのオープンチャンネルを設け、疑似的に隣席しているような情報共有環境をつくります。
さらに、成功した案件のストーリーを社内Wikiにまとめ、貢献度の高いチームを表彰することで、組織全体の貢献意欲を継続的に高める仕組みが実現します。
4. アンゾフの「戦略は組織に従う」
チャンドラーと対照的に、イゴール・アンゾフは「戦略は組織に従う(Strategy follows Structure)」を主張しました。
先に組織の仕組みやプロセスを整備し、そのキャパシティに合わせて実行可能な戦略を策定するというアプローチです。
変化の激しい市場でも、土台となる組織システムが成熟していれば柔軟な戦略策定が可能になる、という合理性を示しています。
アンゾフのアプローチを採る場合は、まず組織そのものの能力を底上げする施策から着手します。
たとえばDX推進室を立ち上げ、全社横断のデータ基盤とアジャイル開発体制を整備してからデジタル事業のロードマップを策定すれば、新たな戦略オプションを試行しやすくなります。
人材面ではジョブ型人事制度に切り替え、専門スキルを横断的に活用できる環境を用意してから、新サービス群のポートフォリオを再構築することで、組織のキャパシティに合った戦略を柔軟に設計・実行できるようになります。
組織マネジメントで解決できる課題
組織マネジメントを導入・強化することで得られるメリットは幅広く、マネジメントスキルの底上げや管理職の業務負担の軽減、優秀な人材の離職防止など多岐に及びます。
ここからは、こうしたマネジメント手法によって解消できる代表的な課題を詳しく見ていきましょう。
①組織全体のマネジメント力を向上できる
純粋にマネジメントだけをする管理職を置いている会社は、昨今ではほとんど見かけません。
プレイングマネージャーとして自らも成果を出しながら、マネジメントもすることが求められていることがほとんどです。
この状況で新たに管理職になった場合、プレイヤーとしてはこれまでの経験でなんとかできると思います。
しかしマネジメントの経験がないため、組織の運営が上手くいかず、機能不全に陥ってしまっているケースが多いようです。
そこで、組織マネジメントの研修や能力開発を実施することで、マネジメント力を向上させることはもちろん、プレイヤーとマネジメントを兼任しているプレイングマネージャーも管理職としての責任感を養うことができます。
②管理職の負担を軽減できる
メンバーの育成やサポート、マネジメントは管理職の大切な役割ですが、プレイングマネージャーとして多忙な中で、無限に時間をかけることはできません。
しっかりと組織マネジメントができていれば、たくさんの時間や業務量を費やさなくても、メンバーは自発的に行動ができるようになります。
営業の業務効率化に欠かせない、SFA(営業支援ツール)に関する記事はこちら!:
③個々に合わせたマネジメントができる
非正規社員や業務委託、時短勤務など、今後ますます働き方は多様化していきます。
そこで管理職に求められるのが、メンバーそれぞれの適性や志向、価値観に合わせた仕事の割り振りやサポートを行うことです。
こうした労働環境の変化に対しても、組織マネジメントを活用することで、スムーズな組織運営が実現できます。
組織マネジメントで管理すべき項目
ここまで、組織マネジメントの必要性を説明してきました。
では実際に、「何を」マネジメントしたらいいのでしょうか?
有名なコンサルティングファーム、マッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱している「組織の7S」を用いて説明してみたいと思います。
■ハードのS:組織の構造に関するもの
(1)戦略(Strategy)
競争優位性を維持するための事業の方向性、経営解決の手段
(2)組織(Structure)
集団で最大限のパフォーマンスを発揮するための組織の形態や構造
(3)システム(System)
人事評価や報酬、情報の流れ、会計制度など、組織の活動を円滑にするための仕組み
■ソフトのS:人に関するもの
(4)価値観(Shared Value)
社員で共通認識を持つ会社の価値観
(5)スキル(Skill)
営業力、技術力、マーケティング力など組織に備わっている能力
(6)人材(Staff)
組織が掲げる価値観を共有・共感できる人材、個々の人材の能力
(7)スタイル(Style)
社風や、組織の文化、仕事の進め方など
制度や仕組み、システムなどに関する「ハードのS」は比較的変更しやすいのに対し、人の価値観や能力に関する「ソフトのS」は変更に時間がかかると言われています。
なお、ハードとソフトのどちらが大事、ということはありません。
たとえば、最新のITシステムを導入してもそれをメンバーが使いこなせなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。
まずは7つの要素が、どのように影響し合うのかを理解し、戦略や計画を立てる際には、それぞれの要素が邪魔をせずに効果を出すにはどうしたらいいのかを考えてみることが必要です。
組織マネジメントに必要な6つのスキル
上述した通り、組織マネジメントで管理すべき範囲は幅広く、管理職にもさまざまな能力が求められます。
そこでこの項目では、組織マネジメントを行うに当たり、管理職が身につけておくべき6つの能力について紹介したいと思います。
1.目標設定力
組織として達成すべき目標を理解・把握した上で、計画や施策の立案、最適な人員配置を行います。
目標設定のポイントは、達成できるギリギリのラインに目標をおくことです。ほどよい緊張感があることで、やる気や達成感を引き出すことができます。
2.計画力
目標達成までのプロセスで分割、逆算して、計画をつくります。
具体的なスケジュールに落とし込むことで、迷わずに業務を進めることができます。
3.人材マネジメント力
メンバー一人ひとりの能力や性格を見極めて適材適所に配置、さらに必要があれば、動機づけや指導も行います。
ここで注意が必要なことが2つあります。
①口で伝えるだけでなく、やってみせる
自らの背中を見せることで、メンバーの士気が高まり、自発的な行動を促すことができます。
②モチベーションにこだわらない
モチベーションが低くても成果を出せる仕組みをつくることが、マネジメント側の役割です。
モチベーションは高いに越したことはないですが、低いからと言って精神論に偏った指導をしないように気をつけなくてはなりません。
4.コミュニケーション力
管理職には、まったく別の2つのコミュニケーション力が求められます。
一つは、メンバーに対するもの。
現場の声をしっかり聞き、何でも気軽に話し合あうことで信頼関係が生まれ、働きやすい職場になります。
もう一つは、経営に関わる上位管理職に対するものです。
売上や利益など経済合理性を考える経営層に対して、現場の状況を理解してもらうという高度なコミュニケーションが求められます。
5.リスク回避力
業務の予定や取引条件、市場環境など、ビジネスの世界では日々、さまざまな変化が起こります。
こうした変化にいち早く気付くために常にアンテナを張っておき、大きな課題となる前に手を打つことができるよう対策を立てておくことが必要です。
まずは発生確率と被害の大きさでリスクを分類し、優先度の高いものから対策を立てておきます。
具体的な対策としては、リスクの少ない業務フローへの変更やトラブル時の対応マニュアル作成をしておくことが役立ちます。
6.評価力
いくらがんばっても認められなければ、誰もがいずれはやる気をなくしてしまいます。
優秀な人材、成果を挙げたメンバーには、しっかりと評価をして報奨や役職などインセンティブを与えます。
評価されたメンバーはもちろん、周りのメンバーにもライバル心が芽生えることで、意欲が高まります。
さいごに
組織を効率的に運営していくには、難しいことやクリアしなくてはいけないことがたくさんあります。
一方で、足りない部分を補い合ったり切磋琢磨し合うことで、個人では到底望めないパフォーマンスを発揮し、大きな成果を出せることは、組織ならではのメリットです。
ぜひ、今回ご紹介した組織マネジメントを活かして、個人と組織の目標達成や成果に繋げていただければと思います。
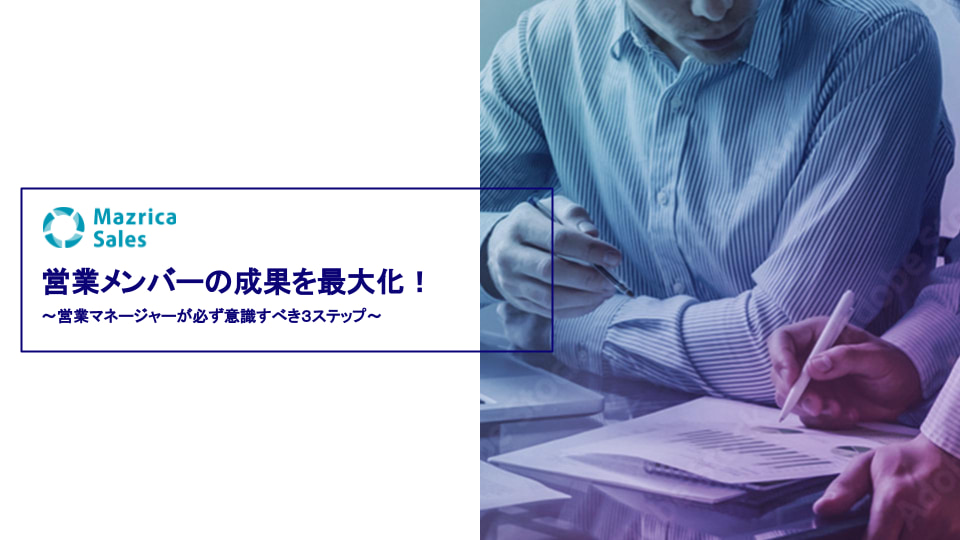
営業メンバーの成果を最大化! ~営業マネージャーが必ず意識すべき3ステップ~
セールスマネジメントのポイントとして戦略立案から部下のモチベーション管理まで3つの観点でまとめています。営業のマネジメントに関わる方向けの資料です。
資料をダウンロードする






















