「マーケティングが獲得したリードに営業をかけても、なかなか成果につながらない」「商談に行っても無駄足が多い」
このような課題を抱えている場合は、リード獲得と併せてMQL獲得にも力を入れてみてはいかがでしょうか。
MQLはリードの中でも確度が高い層を指し、MQLに適切にアプローチすることで効率的に受注を増やすことができます。
本記事では、MQLについて詳しく解説しています。MQLを獲得するための戦略など実践的な内容も含まれているので、ぜひご参考ください。
▶︎▶︎【無料配布】BtoBマーケティングの最新トレンドを知って、自社の施策に生かしたい方はこちら
この記事の内容
MQLとは?
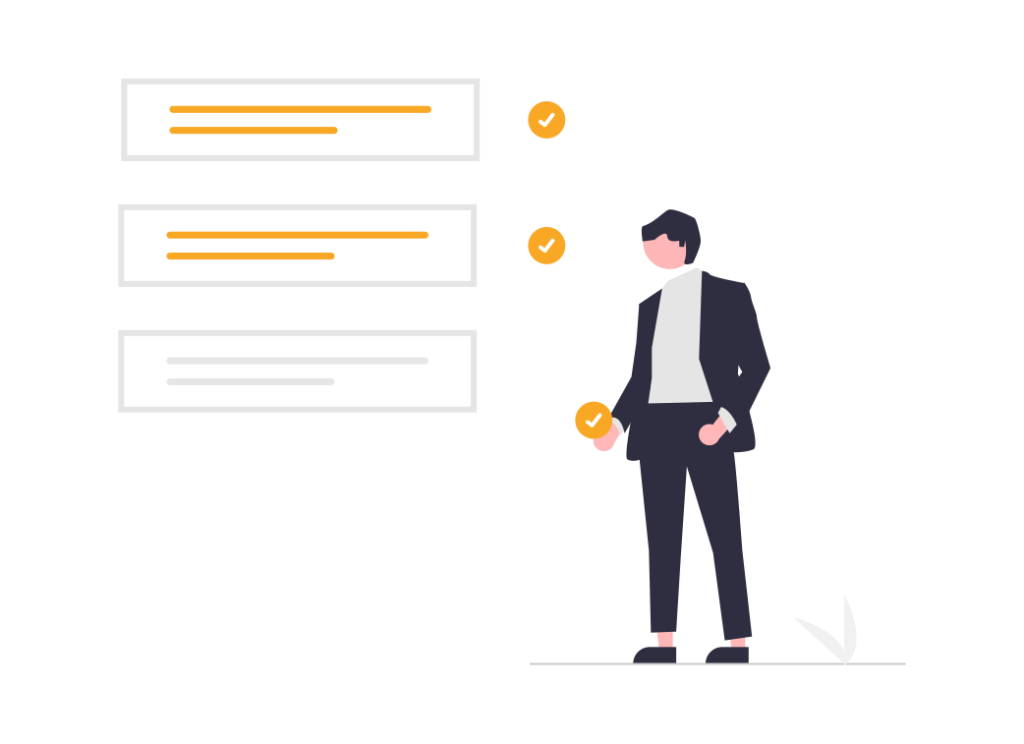
MQLとは「Marketing Qualified Lead」の略称で、マーケティング活動により創出された確度の高いリード(見込み顧客)を意味します。
「Qualified」は「要件を満たした」といった意味を持つため、MQLとは一定要件をクリアしているリードのみが該当します。
そのため、マーケティングで獲得したリードすべてをMQLと言うのではなく、ある程度購買意欲が高く見込み度のあるリードをMQLとする場合が一般的です。
たとえばWEBサイトやセミナー、展示会などで情報を獲得したリードのうち、継続的な情報発信やコミュニケーションなどにより一定以上の購入見込みになったリードがMQLと分類されます。
MQLの判定基準
マーケティング活動で獲得したリードをどのような基準でMQLと判断するかは、企業によって異なります。業種や商材などにより、リードの検討度合いは異なるためです。
リードタイムが短めの商材であれば、資料請求をした段階で検討度合いが高いと判断できる場合もあるでしょう。
一方、高額商材などリードタイムが長めの商材の場合は、資料請求だけでなく料金表のダウンロードやセミナーへの参加などを経て、段階的に検討度合いが高まっていくこともあります。
このように、検討度合いの高いMQLの判定基準は、業種や商材、カスタマージャーニーなどによって大きく異なります。
MQLと判定するのは「特定のアクションを行ったリード」とするのか、「複数のアクションを行い、あらかじめ設定しているスコアを超えたリード」とするのかは、自社商材やカスタマージャーニーを分析してから検討しましょう。
MQLを定義・創出する3つのメリット

MQLの基準を定義し、マーケティング活動でMQLを創出することは、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは具体的な3つのメリットについて解説します。
営業活動の効率化と付加価値提案
MQLは購買意欲が高まっている状態の、いわゆる「ホットリード」です。
そのため、営業担当者は細やかなフォローに手間をかけずに済み、効率の良い営業活動が可能になります。
検討度合いが引き上がった段階で営業部門へ引き渡すことができるため、営業部門は受注確度の高いリードにリソースを集中できます。
また、MQLはSQL(Sales Qualified Lead)に比べてニーズが不確定的な状態の見込み客を指します。
だからこそ、営業担当者はヒアリングを通して、MQLが漠然と思い描いていた以上の、付加価値の高い商品やサービスを提案できる機会があります。
これにより、顧客との関係性を深め、より満足度の高い提案へと繋げることができます。
MQLを定義していない場合、獲得したリードすべてを営業部門へと引き渡すことになります。
よって、リードの購買意欲の高低に関わらず、営業部門はすべてのリードをフォローしなければいけません。
しかしこれでは、購買意欲の低いリードの意欲を高めるためにフォローする時間を取られ、本来優先すべきホットリードを対応する時間を確保できなくなります。
結果としてせっかく購買意欲の高いホットリードも失注してしまう恐れがあり、受注率にも大きな影響を及ぼすでしょう。
一方、検討度合いの高いMQLを営業部門に引き渡すことができれば、スムーズに受注まで進められるため営業活動が効率化します。
結果として受注率も向上し、売上にもつながります。
質の高いフィードバックとマーケターの顧客理解
MQLは質の高い見込み客とも言い換えることができます。つまり、自社を信頼してくれているため、通常のアンケートでは得られない貴重なフィードバックを受けることができる可能性があります。
このフィードバックは、製品やサービスの改善、今後のマーケティング戦略に大いに役立ちます。
MQLを定義することは、マーケターが顧客に関する理解をより深めることにも繋がります。
MQLを獲得するためには、自社のリードがどのようなプロセスで購買意欲を高めていくのか、どのようなアプローチが効果的なのか、といった視点で施策を考えなければなりません。
そのため、おのずと顧客視点で考えるようになります。マーケティングにおいて顧客理解は必要不可欠です。
したがって自社のMQLを定義することでマーケターの顧客理解が深まれば、MQL以外にもマーケティング全般において活かすことができるでしょう。
マーケティングと営業の連携強化
MQLは一般的なリードよりも受注確度が高いため、営業部門は質の高い商談を行うことができ、効率的に成果を出すことができます。
そのためには、MQLの要件を適切に定めた上で運用することが重要です。
「どのような状態のリードであればスムーズに受注につながるか」「その状態にするためにマーケティングはどのようなことをしなければいけないか」といった情報共有を行い、お互いに納得したMQLの要件を導き出すことで、役割分担が明確になり円滑に連携できます。
逆に、MQLが定義できていない場合、「せっかく頑張ってリードを獲得したのに、営業が適切にフォローしてくれなかった」「見込み度の低いリードばかり引き渡されて、受注率が低下している」といった衝突やトラブルを引き起こしかねません。
マーケティングと営業がお互いの役割分担や目標を明確にするためにも、MQLの定義が必要と言えるでしょう。
関連記事:マーケティング・営業の連携の秘訣とは?メリット・トラブル解決策を解説!
MQLとSQLの違い・関係
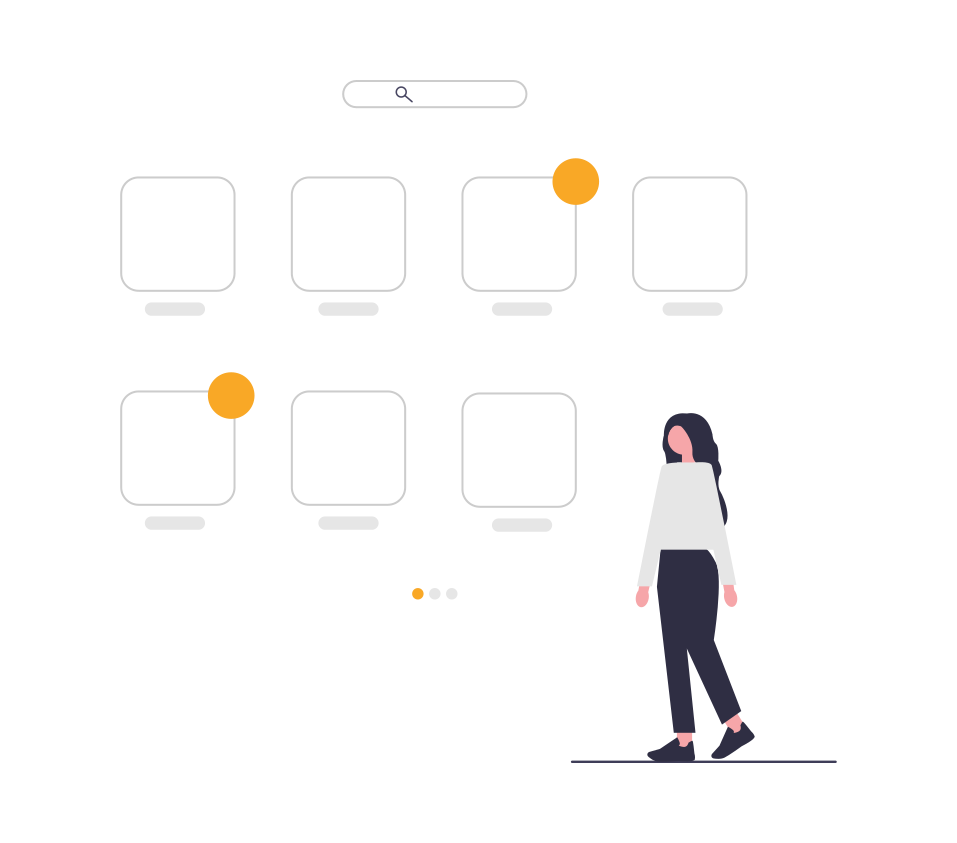
MQLと混同されやすい言葉に「SQL」があります。
SQLとはどのようなリードを指すのか、そしてMQLとはどう違うのか、詳しく解説します。
SQLとは?
SQLとは「Sales Qualified Lead」の略称で、営業活動によって創出されたリード(見込み顧客)です。
MQLと同様に、一定要件を満たした見込み度合いの高いリードを指しています。しかし、MQLは営業に引き継ぐためのリードであることに対し、SQLはMQLの中でも優先的にフォローすべきリードとなります。
SQLは購買ニーズが顕在化しており、購買意欲も高い状態です。そのため営業が適切にフォローすることで、スムーズに受注へとつなげられます。
BtoBマーケティングにおけるMQLとSQLの違い
| MQL | SQL | |
|---|---|---|
| 部門 | マーケティング部門 | 営業部門 |
| 判定基準 | 自社の商品の、サービスに 一定の関心を示したリード |
購買意欲が高いと判断でき、 営業活動の対象となるリード |
| 具体例 | 資料請求 セミナー参加 メルマガ登録 |
予算・導入時期が明確 具体的な相談あり |
MQLとSQLは混同されやすいですが、BtoBマーケティングにおいては明確な違いがあります。
BtoBマーケティングでは、獲得したリードのうち一定要件を満たした質の高いリードをMQLとします。資料請求や料金表のダウンロード、お問い合わせなどリードのアクションを点数化し、高得点のリードをMQLとすることが多いです。
そしてMQLは営業部門へと引き継がれ、インサイドセールスなどが対応します。インサイドセールスが電話やメールなどでMQLにコミュニケーションを取り、優先してフォローすべきと判断したリードをSQLとして判別します。
SQLはニーズが顕在化しており購買意欲も高まっているため、優先的にフォローすることで営業チャンスを損失せずに受注へとつなげられます。
成果につながるリード戦略:MQL創出のための3ステップ
MQLを生み出すためには、以下3つの戦略を実行します。
- リードの獲得(リードジェネレーション)
- リードの育成(リードナーチャリング)
- リードの抽出(リードクオリフィケーション)
この3つの戦略をプロセスに沿って実行することで、確度の高いMQLを創出できます。
リードの獲得(リードジェネレーション)
まずはリードを獲得しないことには、MQLへと育成できません。そのため、リード獲得のための施策を行います。メールアドレスや電話番号など、顧客に対してアプローチするための情報を収集することが目的となります。
オフラインであれば、展示会やセミナー。オンラインであれば、オウンドメディアやWEB広告、SNSなどがあります。
リードの獲得数を増やすことはMQLを創出できる機会も増えることにはなりますが、確度の低いリードばかりを増やしては、コストや手間が無駄になりかねません。
MQLにつながりやすいリードを獲得することで効率的にMQLを増やしていけるので、まずはさまざまな施策を実行して効果の高い施策を見つけましょう。
関連記事:リードジェネレーションとは?意味や手法・おすすめのツール3選を紹介
リードの育成(リードナーチャリング)
次は、獲得したリードの育成です。獲得したリードすべてが購買意欲が高いわけではないので、適切な施策により購買意欲を高めてMQLとして育成します。継続的に情報発信を行うことで、接触回数を増やして購買意欲を刺激することが目的です。
メルマガやSNS、オウンドメディアなどで有益な情報を発信したり、セミナーやウェビナー(WEBセミナー)でコミュニケーションを取ったりする方法があります。場合によっては、アンケートや電話によるヒアリングなどが効果的なこともあります。
関連記事:リードナーチャリングとは?意味や手法・リードジェネレーションとの違いを解説
リードの抽出(リードクオリフィケーション)
育成施策によって購買意欲を高めたら、いよいよMQLとなるリードを抽出します。特に確度の高いリードを見極めるための重要なステップです。
リードの抽出の際には「頻繁に質問してくる」「返答が前向きだ」などの主観的な視点だけでなく、データを基にした客観的な視点も必要となります。
その際に活用できるのが「リードスコアリング」という手法です。
「ホワイトペーパーをダウンロードしたら3点」「お問い合わせをしたら5点」というようにリードの行動に点数を付けて加点していくことで、点数の高いリードほど購買意欲が高いと判断します。
このように、あらかじめ抽出する指標を決めておくことで、適切なMQLを営業へと引き渡せます。
関連記事:リードクオリフィケーションとは?効果的なスコアリング方法も解説
MQLのありがちな課題と改善策
MQLの創出に関して、頻発する課題を解説します。
具体的には、以下の2点です。
- MQLは商談化までに時間を要する
- MQLが売上に貢献しているか把握が困難
- マーケティングと営業の対立が起きやすい
MQLは商談化までに時間を要する
MQLから実際の商談に繋げるまでには、比較的長い時間がかかる傾向があります。
一方、SQLは、インサイドセールスなどによってあらかじめ顧客のニーズ、予算感、導入時期などが整理されている状態で営業に引き渡されるため、商談スピードが速く、受注に結びつきやすい特徴があります。
MQLは潜在的な興味関心はあるものの、中長期的なコミュニケーションを重ねる必要がある段階のリードです。そのため、直近の売上目標を追われている営業部門は、つい手つかずのMQLを脇に置いてしまいがちになります。
そこで、MQLを「すぐに商談」と考えるのではなく、「時間をかけて育てる」という認識をもつことが重要になります。
顧客の興味・関心に合わせた、段階的な情報提供やコミュニケーションを継続する「リードナーチャリング」を徹底しましょう。
MQLが売上に貢献しているか把握が困難
マーケティング部門と営業部門の連携が不十分だと、「MQLが実際に商談や受注に結びついているのか分かりづらい」という課題も生じます。
例えば、営業へ引き継ぐ際のMQLの情報が不足していたり、営業対応後の報告がマーケティング側に上がってこなかったりすると、MQLの行方が見えなくなります。そうなれば、MQLが売り上げに貢献しているのか、失注した場合の原因は何かを特定できません。
このような状況が続けば、マーケティング側も良質なMQLを営業に渡せなくなり、マーケティングと営業の間で悪循環が生まれかねません。
MQLの売上貢献度を可視化するためには、明確な成果指標(KPI)を設定し、継続的にトラッキングすることが不可欠です。
MQLの獲得から売上までを一元的に管理・分析するためには、SFA/CRMの活用が便利です。
マーケティングと営業の対立が起きやすい
「マーケティングから送られてくるMQLの質が低い」「営業がMQLを後回しにしている」など、マーケティング部門と営業部門の間で衝突が生じることは少なくありません。
この問題を解決するには、両部門がMQLに対する共通認識を持ち、互いの役割を正しく理解した上で協力体制を築くことが重要です。
具体例としては、「MQLとはどの状態の顧客を指すか」「SQLへの以降条件は何か」など、定義の明確化をすることが挙げられます。
また、MQLの特性や獲得経路、MQLからのフィードバック内容など、定期的な情報交換をすることも有効です。
MQLをSQLに繋げるためのポイント
ここまでMQLを創出するための戦略について解説しましたが、ここでは獲得したMQLをSQLに繋げるためのポイントについて解説します。
MQLの定義を明確にし、営業部門と共有する
一つ目のポイントは、「MQLの定義を明確にすること」です。
MQLの定義が曖昧なままだと、マーケティング部門がMQLだと判断して営業部門に引き渡しをしたものの、実際に営業をかけたら購買意欲が低く、無駄な工数をかけてしまった、などの問題が発生する可能性があります。
MQLの定義はなるべく具体的に定め、さらにそれを営業部門と共有することで、両部門間で起こるズレを無くしていく工夫が大切です。
MAツールを活用する
MAツールはリード情報を管理できる機能があり、リードごとに氏名や連絡先だけでなく、実行したアプローチ履歴やその反応などのデータを蓄積できます。
また施策を実行するための機能も備わっていて、メルマガ配信や問い合わせフォーム作成、WEB解析などができるツールもあります。
さらにスコアリング機能が搭載されているツールもあるので、MAを活用することでリードの獲得・育成・抽出が1つのツール内で完結できるのです。
スコアリングを用いて、定めたMQLの定義を正確に反映し、営業部門に引き渡すことで、これらの作業を自動化することが可能です。
ちなみに、MAを導入する際にはSFA/CRMと連携できるものを選びましょう。MQL獲得の際にはマーケティングと営業の連携が必須なので、マーケティングで使うMAと営業で使うSFA/CRMを連携することでシームレスな情報共有が実現します。
▶︎▶︎BtoBビジネスに携わるマーケターやセールスパーソンのためのMAツールの選び方を紹介します。
MQL獲得におけるマーケティング・営業連携の重要性
先述の通り、受注につながりやすいMQLを営業に引き渡すことで、営業は確度の高い商談に注力できるため、組織として効率的に受注を獲得できるようになります。
つまり、どのような状態のMQLであれば受注確度が高いか、マーケティングと営業で事前に共有しておくことが重要です。
部門が異なると、認識の違いが生じやすくなります。
たとえばマーケティング視点では「料金表や詳細資料をダウンロードするリードほど購買意欲が高いのではないか」と見えても、営業現場からは「事例集をダウンロードしているリードのほうが購買に対して前向き」という傾向が見える場合があります。
このように認識の齟齬があると適切なMQLを獲得できないため、部門間の食い違いにも発展するでしょう。
また、どのようにしてMQLを獲得したかを営業が把握できていないと、営業は最適な提案ができません。
たとえば「セミナーに参加したあと、複数のホワイトペーパーをダウンロードした」というMQLの場合、ホワイトペーパーの内容によってMQLが抱えている課題やニーズを把握できます。
しかしこの内容が共有されていないと、営業は見当違いな提案をしてしまい、MQLのニーズに応えられない事態も起こりえます。
このような理由から、MQL獲得においてマーケティングと営業の連携は欠かせません。
MQLの放置は機会損失につながる
現在の日本のビジネスシーンでは、MQLの放置が致命傷に繋がります。以前は、SQLのみに注力することで営業活動が成り立っていましたが、状況は大きく変化しています。
BtoBにおいて、顧客が自ら情報収集を行い、比較検討から問い合わせというアクションを起こすことが当たり前になりました。そうなると、マーケティングと営業担当の連携がうまく行われず、MQLを放置してしまったために、競合他社の商材を選んでしまったといったことが起こりやすくなります。
確かに、SQLは直近の売上という意味で非常に重要ですが、MQLを軽視することは、中長期的に大きな損失となります。MQLとSQLは同じ価値があると捉え、営業とマーケティングの連携を図ることが大切です。
終わりに|MQL創出で受注率を上げよう
獲得したリードに対し、手当たり次第にアプローチしては非効率です。購買意欲を高めてMQLへと育成することで、確度の高い商談に集中でき、効率的に受注率を伸ばすことができます。
MQL創出のためには、リードの獲得・育成・抽出が不可欠です。また、マーケティングと営業の連携強化によって、より効率的にMQLを獲得できます。
ぜひ本記事を参考にして自社のMQLを定義し、MQL創出の戦略を立ててみてください。





























