消費者の価値観や購買行動が急速に変化する中で、今後どのような戦略を打ち出していくか頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。
近年、海外のSaaSサービスで多く導入されている「PLG(プロダクトレッドグロース)」は、これからの時代に適した営業戦略として注目を集めています。
そこで本記事ではPLGの定義やSLGとの違い、メリットや企業事例などPLGについて詳しく解説します。
またPLG戦略を実行するポイントも説明しているので、ぜひ参考にしてください。
▶︎▶︎【無料ダウンロード】急成長の米国メガベンチャーが教える成功の鍵!営業戦略の秘訣を手に入れよう!
この記事の内容
PLG(Product-Led Growth)とは?

PLGとは「Product-Led Growth(プロダクトレッドグロース)」の略で、日本語で直訳すると「プロダクトが主導した成長」という意味です。
具体的には、プロダクトの中にマーケティングやセールス、カスタマーサクセスなどが組み込まれ、昨日することによって事業の成長につながっていくことを指します。
プロダクトがユーザーの解約率を下げたり、アップセル・クロスセルにも繋がるモデルとも言えるでしょう。
PLGに対応するプロダクトを開発できれば、マーケティングセールスプロセスに人的リソースを充分に確保できなくても事業が成長していくのです。
PLGはSaaSビジネスで多く取り入れられています。
無料で利用できる期間を設けた「フリートライアル」や、無料で利用できる一方で機能が制限された「フリーミアム」戦略を採用することで、新規顧客を獲得していきます。
そして、利用できる機能や期限、人数や容量などを開放するために、無料プランから有料プランへと誘導する仕組みです。
関連記事:アップセルとは?クロスセルとの違い・具体事例を解説
PLGが注目されている背景
市場が成熟して類似品・代替品が多く流通している現代では、ほとんどの市場がレッドオーシャンとなっています。
またインターネットの普及に伴い、消費者は自発的にあらゆる情報にアクセスできるようになり、営業担当者がいなくても購買プロセスを進められるようになりました。
このような時代に生き残るためには、限られた人的リソースを有効に活用し、ユーザーにとって大きな価値のあるプロダクトを設計する必要があります。
そこでユーザーが利用する価値を見出し、能動的にサービスを利用する仕組みであるPLGが注目されるようになったのです。
PLGは海外のSaaSスタートアップで多く導入され、SlackやZoomなど日常やビジネスで欠かせないツールとなっているSaaSサービスでもPLGは導入されています。
「簡単に使えるから」「無料で使えるから」などの理由でユーザーが爆発的に増加し、直接的なセールスをしなくても急成長しています。
このような成功事例を背景に、PLGは日本でも注目を集めているのです。
関連記事:SaaS営業とは?必要なスキルとSaaSビジネスモデルの特徴まで紹介
PLGとSLGの違い

PLGが広がる前は、SLG(Sales-Led Growth)が一般的でした。
SLGとは主にセールスが主導となり、プロダクトを売り込む戦略です。
まずはマーケティング部門がリードを獲得し、インサイドセールスがリードを育成してアポイントを獲得。フィールドセールスが商談をして受注を獲得して、カスタマーサクセスが導入後のフォローをするという、いわゆる「THE MODEL」です。
▶︎▶︎THE MODEL型の営業を加速するSFA/CRMツールはこちら
SLGは企業からの能動的なアクションが起点となっているため、受注やアップセル・クロスセルなどがメンバーのスキルや経験に左右されます。
また営業人員数が限られており、幅広い顧客数をカバーできずにハイタッチのフォローになりがちです。
一方のPLGではユーザーがプロダクトを使い始めた時点でセールスが始まるので、まずは導入してもらうためにフリートライアルやフリーミアムなどが設けられています。
またプロダクト主導のため、メンバーの人数やスキルに左右されずに各顧客のフォローが可能です。
このように、SLGとPLGではセールスの進め方に大きな違いがあります。
そのため自社プロダクトがSLG向きなのか、PLG向きなのかを見極めることが重要です。
関連記事:SLGとは?PLGとの違いや組織体制・ツールも紹介!
PLGとフリーミアム・フリートライアルの関係
PLGでは、ユーザーがプロダクトの価値を自ら見出すことが鍵となります。
そのためには、まずはプロダクトを無料開放してユーザーが試しに利用できる状況を整えることが必要です。
そこで重要となるのが「フリーミアム」と「フリートライアル」です。
この2つは、PLGと切り離せない関係性と言えます。
フリーミアムとは「フリー(無料)」と「プレミアム(有料)」を組み合わせたモデルで、基本的な機能は無料で提供されますが、より高度な機能は有料で提供されます。これにより、ユーザーは無料で利用を開始し、必要に応じて有料プランに移行することができます。
一方で、フリートライアルとは「Trial=試し」という意味を持ち、有料プランの機能を一定期間限定で試すことができるモデルです。ユーザーは期間内にプロダクトの価値を評価し、契約に至るかどうかを判断します。
どちらが適しているかはプロダクトやユーザー層により異なります。
フリーミアムの場合、ユーザーは基本的な機能を無料で利用し続ける可能性がありますが、フリートライアルの場合は期間内に十分な価値を見出せなければ契約に至らない可能性があります。
そのため、無料開放後の戦略も含めて充分に検討しましょう。
PLGの3つのメリット
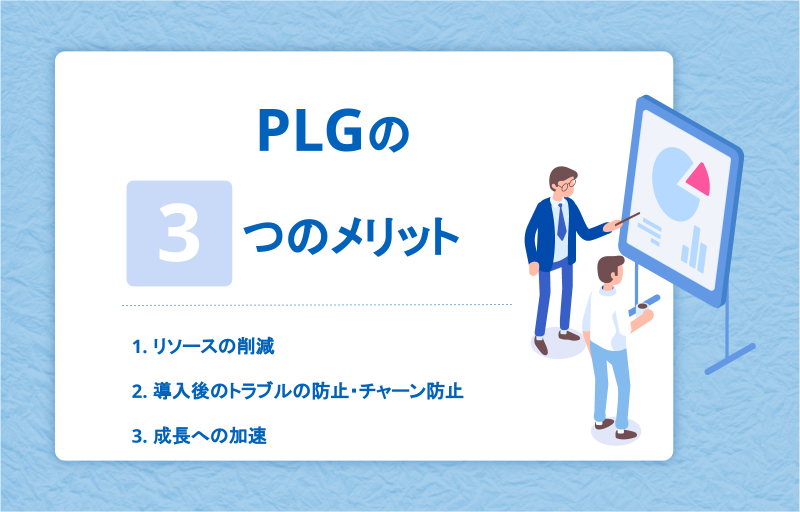
PLGのメリットにはどのようなものがあるか、具体的に説明していきます。
1. リソースの削減
PLGを取り入れる大きなメリットは、「リソースの削減」です。
従来の営業戦略(SLG)では、成果を上げるためには多くのコストや人手を必要としました。
またユーザーの解約を防ぐために適切なフォローをしなければならず、受注後のリソースもかかります。
しかしPLGでは、まずはフリートライアルやフリーミアムでユーザー自身がプロダクトの利用価値を実感できます。
そのため、自社の営業リソースをかけなくてもユーザーを有料プランやオプション契約などに誘導できます。
人的リソースやコストの削減に加え、導入までの時間の短縮にもつながるでしょう。
2. 導入後のトラブルの防止・チャーン防止
従来のSLGでは、ツールの導入が企業の上層部によって決定され、現場ユーザーとのギャップが生まれることがありました。
一方で、PLGでは現場ユーザーがまずプロダクトを無料で体験でき、有料契約の前に使用感を確かめられるため、導入後のトラブルを防ぐことができます。
ユーザーの実際の利用感や使いやすさを確認できることで、解約(チャーン)を防ぐための戦略を構築できます。
たとえばユーザーが使いこなせていない機能があれば、その機能に関するマニュアルやデモ画面を提案すると、ユーザーが自発的にプロダクトの機能を学んで使いこなせるようになり、利用価値を見出せます。
関連記事:チャーンレート(解約率)とは?計算方法や改善方法を解説
3. 成長への加速
PLGのもう一つの重要なメリットは、企業の成長を加速させることです。従来の営業戦略では、新規顧客の獲得や収益の増加には時間がかかることが一般的でした。
しかし、PLGを活用することで、顧客が自らプロダクトを試用し、その価値を理解するプロセスが早まります。
具体的には、PLGでは顧客が無料トライアルやフリーミアム版を利用して、製品やサービスの価値を直接体験できます。このような早期の顧客エンゲージメントにより、顧客が製品やサービスに対する興味や関心を高めることができます。
そして、顧客が自ら製品やサービスの価値を確認した後は、有料プランへの移行や追加機能の購入など、収益を生み出す行動につながる可能性が高まります。
PLGを導入した企業の成功事例
現在では欠かせないツールとなっているSlackやZoomも、PLGを取り入れたことが急成長のカギとなっています。
2社の事例について、詳しく解説します。
Slack
ビジネスチャットツール「Slack(スラック)」は、今や仕事上のやり取りには欠かせないツールになっています。
さまざまな外部サービスとの連携も可能なので、Slackがないと困る人も少なくありません。
Slackは基本的なチャットや機能は、無料のフリープランで利用できます。
しかし、ストレージ容量の拡張やセキュリティレベルの向上など、さらに高度な機能を利用したい場合は有料プランへの切り替えが必要です。
有料プランは「プロ」「ビジネスプラス」「Enterprise Grid」の3プランが設けられており、自社に最適なプランを選択できます。
Slackは有料プランへの移行を促す営業活動はせず、ユーザー自身がSlackの利用価値を見出して有料プランへと自発的に移行していくPLGを実現しています。
関連記事:Slack連携ツール・アプリおすすめ10選!スケジュール・タスク管理を効率化
Zoom
オンラインミーティングツールの「Zoom」は、コロナ禍での非対面コミュニケーションの活性化を背景に急成長したプロダクトです。
Zoomも基本的な利用に関しては無料です。
ただしミーティングの時間は40分、最大出席者数は100名という制限があります。
そのため「2時間利用したい」「100名以上のミーティングをしたい」といった場合は有料プランへの移行が必要です。
有料プランではライセンス数が拡張されたり、録画データをクラウドストレージに保存できたりする機能も追加されるため、ユーザーはそれらに魅力を感じて自発的にアップグレードするでしょう。
▶︎▶︎効率的なPLG実現!営業・顧客情報を一元管理する効果的なSFAツールとは?
PLG戦略を実行するための4つのポイント
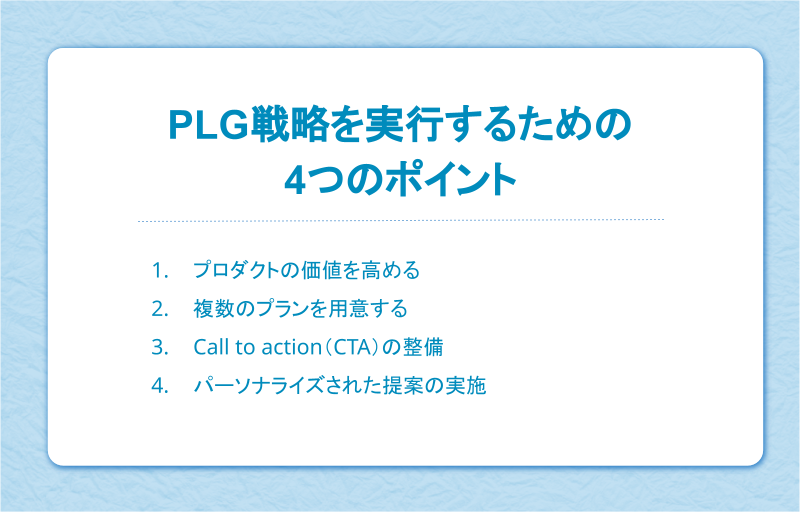
PLG戦略はどのように進めたら良いのでしょうか。
ここではPLG戦略に必要な4つのポイントを解説します。
1.プロダクトの価値を高める
PLGを実行するにあたり、大前提となるのがプロダクト自体の価値です。プロダクトの価値が高くなければ、ユーザーの契約や利用継続につながりません。
そのため、まずはプロダクトの価値を高めましょう。
「課題を解決できるか」「なくてはならないツールになれるか」「料金を支払って利用する価値があるか」といった視点で、客観的にプロダクトを分析します。
実際の利用者にヒアリングしたり、ユーザビリティテストを実行したりしても良いでしょう。
2.複数のプランを用意する
料金プランの見直しも必要です。以下のように複数のプランを用意しましょう。
- フリープラン
- スタンダードプラン
- プロフェッショナルプラン
- プレミアムプラン
各プランの機能も併せて検討し、ユーザーがスムーズにアップグレードできるよう設計します。
またオプションも用意しておくと、クロスセルを促し顧客単価を引き上げられます。
3.Call to action(CTA)の整備
ユーザーの行動を促すCTAの整備も重要です。
たとえばユーザーが利用しているストレージを超えた場合、ワンランク上のプランを提案するポップアップを表示すると、ユーザーはスムーズに行動に移すことができます。
また、解約手続きに進もうとしているユーザーに対して、FAQやデモ画面などを表示して使い方についてのレクチャーを行い、解約を防ぐこともできるでしょう。
4.パーソナライズされた提案の実施
ユーザーによって課題や必要な機能が異なるため、一人ひとりのユーザーにパーソナライズされた提案が求められます。
たとえば機能を充分に使いこなせていないユーザーに対し、さまざまな機能の使い方や活用方法についての提案をすることで、プロダクトに魅力を感じてもらえます。
利用頻度が高いユーザーに対しては、より便利なオプションを提案することでクロスセルを促せます。
このようにパーソナライズした提案を行うためには、ユーザーの利用状況の把握が必須です。
利用データを分析でき、分析結果から最適な提案ができる仕組みを作りましょう。
関連記事:パーソナライズとは?意味やメリット・デメリットとツール紹介
PLGを学ぶためのおすすめ本
PLG(Product-Led Growth)に関する理解を深めるためには、以下の書籍がおすすめです。
『PLG プロダクト・レッド・グロース「セールスがプロダクトを売る時代」から「プロダクトでプロダクトを売る時代」へ』
- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 著者:ウェス・ブッシュ(著), UB Ventures (著), 八木映子 (翻訳)
- 単行本:362ページ
- 備考:電子書籍版あり
この書籍は、PLGの基本から実践的な方法までを網羅しており、セールスがプロダクトを売る時代からプロダクトが自らを売る時代への変化を解説しています。
そして、自社のプロダクトがPLGに合っているかどうかを診断するための手法も提供されています。PLG戦略の導入を検討している方にとって、必読の一冊と言えるでしょう。
終わりに
PLGはプロダクトがプロダクトを売り込む営業手法で、海外でも多くのSaaSサービスに取り入れられています。
今後ますます少子高齢化による労働力不足が深刻化する日本では、人的リソースを削減しながら成果を出せるPLG戦略が、より求められていくでしょう。
本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ自社プロダクトについて見直し、PLG戦略にお役立てください。

セールスイネーブルメント -経営層・営業マネージャーが取り組むべき営業改革-
セールスイネーブルメントをご存知でしょうか?セールスイネーブルメントの概要や実践方法に関する資料です。
資料をダウンロードする

























