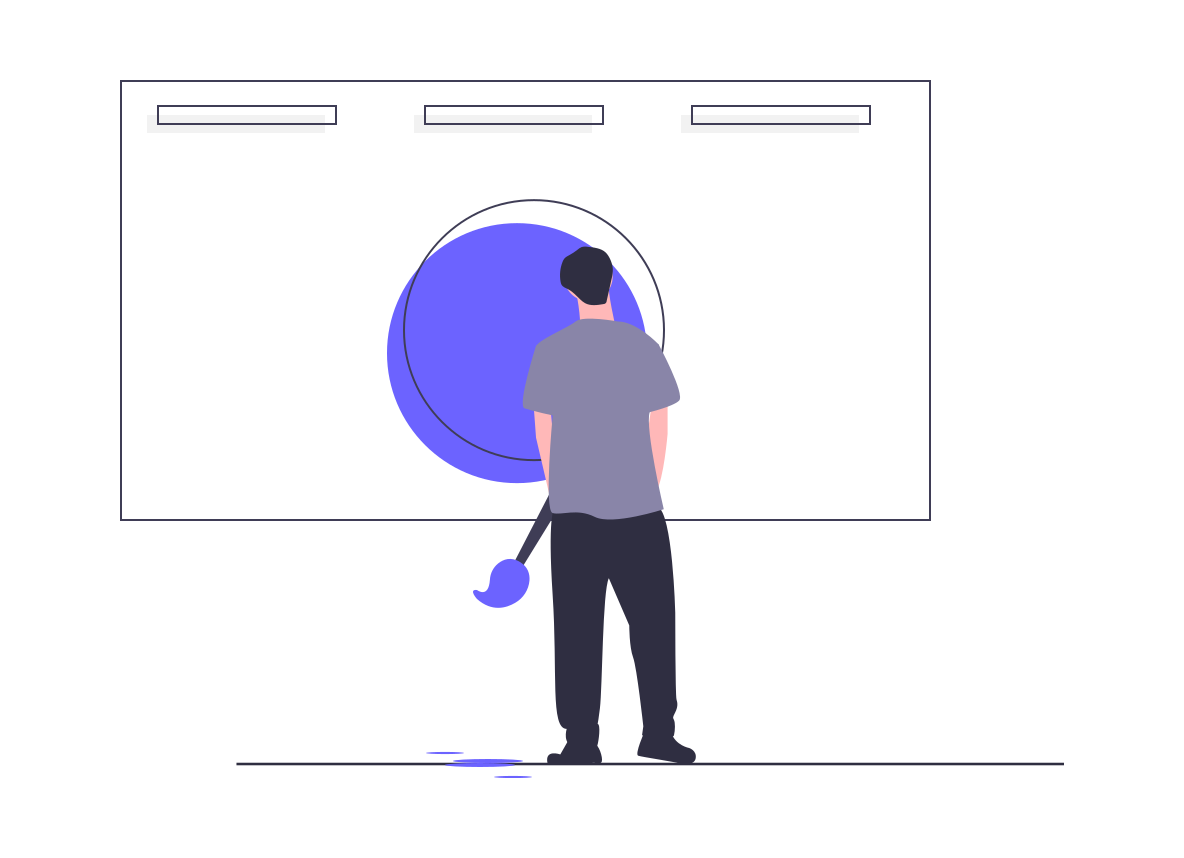「誰がどの案件を進めているかわからない」「営業ナレッジが共有できず成果に差が出ている」など、営業情報の共有に関する課題を抱えている営業組織は少なくありません。営業情報の共有により、組織の課題や状況が明確になり営業力アップも期待できます。
本記事では、営業情報を共有する重要性やメリットと、共有すべき項目を解説します。役立つツールや成功ポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の内容
営業の情報共有の目的と重要性
営業組織では、組織内の円滑な情報共有が成果に結びつきます。営業の情報共有はなぜ必要なのか、目的と重要性を解説します。
関連記事:情報共有の方法とは?社内外の営業情報共有の最適な仕組み作り
営業の情報共有の目的
営業の情報共有の目的は、組織の課題や業務フローなどにより多岐にわたります。主な目的は以下のようなものが挙げられます。
- 対応の漏れ・遅れの防止
- 組織内のコミュニケーション促進
- 意思決定の迅速化
- 営業ナレッジの展開
案件情報や顧客情報などの共有により、上記のような目的を実現できます。
営業の情報共有の重要性
情報共有がなぜ重要なのかと言うと、営業組織内の状況や課題を見える化できるためです。営業活動は属人化しやすいですが、一元管理して共有することで、今まで見えなかった「個人のボトルネック」や「停滞案件」、「進捗状況」などを全体で把握できるようになります。そのため、状況に応じて適切なフォローや、個人や案件の課題に沿ったアドバイスができます。
また、属人化していると、営業ナレッジや成功事例は個々のものとなってしまいます。その結果、営業プロセスやアプローチ方法がバラバラになり、成果に差が出やすくなります。しかし、営業の情報共有ができていれば、成果につながりやすい提案書やセールストーク、効率的な業務の進め方などが組織内で共有でき、組織の営業力を底上げできるでしょう。
さらに、顧客ニーズの把握にも役立ちます。自社が抱えているすべての顧客情報や商談履歴などを分析することで、導入背景や購買傾向などを把握できます。そうしたデータを基に顧客ニーズに沿ったアプローチができるため、時代やトレンドの変化にも対応できる組織になります。
営業の情報共有を行うメリット
営業の情報共有によって、どのようなメリットや効果が期待できるのか、詳しく見ていきましょう。
関連記事:情報共有のメリットとは?目的やおすすめツールを紹介
1. 属人化の防止
日々の商談や顧客とのコミュニケーションなどは営業担当者個人で行うことが多いため、営業活動は属人化しやすいという側面があります。属人化が進むと、周囲は案件の進捗状況を把握できないためトラブルが起きても気づかなかったり、営業ナレッジがチーム内に広まらず成果に差が出たりするなど、組織としてネガティブな影響も出てくるでしょう。
しかし、営業情報を組織で共有できれば、属人化が解消されて一人ひとりの動きが見えてきます。停滞している案件があればマネージャーがフォローしたり、抱えている案件が多すぎる人がいれば他のメンバーがフォローしたりできるため、成果を出しやすくなるでしょう。また、個人の進捗状況やボトルネックだけでなく、組織の現状や課題も把握できるようになることで組織の営業力を底上げできます。
2. 営業プロセスの可視化
顧客とのやり取りの内容だけでなく、営業プロセスも属人化しやすい傾向にあります。
たとえば、Aさんは初回商談時にクロージングまでしている一方、Bさんは初回商談後に2度の商談を経てクロージングをしているという場合もあります。しかし営業情報が共有できていないとAさんとBさんの営業プロセスの違いを把握できないため、どちらのほうが自社の商材に適しているか判断できません。
営業情報の共有により、誰がどのようなプロセスで営業活動を進めているか把握でき、より効果的な営業プロセスを取り入れることが可能です。
また、営業プロセスを可視化できれば、各営業担当者のアプローチや商談時の努力も把握できます。アプローチの際の工夫や商談時のセールストークなどが見えるため、適切な評価にもつながるでしょう。
3. 営業ナレッジの蓄積と活用
初回アプローチでのヒアリング項目、商談時のセールストーク、使用している提案資料なども、属人化しやすいと言えます。属人化すると成果にばらつきが生じ、組織全体の利益にも影響が出るかもしれません。
営業情報を共有していれば、それぞれが営業活動で気を付けているポイントや、受注につながった成功事例などを全体に共有できます。こうした営業ナレッジの活用によって、新人がスピーディに戦力化できたり、成果が出にくかったメンバーもスキルアップできたりするなど、組織にポジティブな影響が及ぶでしょう。
▶︎▶︎営業マネージャーが取り組むべき営業改革について知りたい方はこちらの資料もご覧ください。
営業で共有すべき項目
営業情報と一口に言っても、膨大な情報が該当します。具体的にどのような項目の情報を共有すべきなのか紹介します。
顧客情報
まず必要なのが顧客情報です。BtoBの場合は会社名・連絡先・担当者名など、BtoCの場合は氏名・連絡先・勤務先などの情報があります。ほかにも、過去の取引履歴や商談履歴、クレーム履歴、決裁者情報なども必要です。
BtoBの場合、担当者や決裁者の交代、決裁・稟議フローの変更なども起こる可能性があるため、情報はこまめに更新しましょう。正しく情報を更新できていれば、もしも異動や退職で営業担当者が変わった場合にも、顧客は一から説明する必要がないため信頼関係を構築できます。
関連記事:顧客情報とは?一元管理方法・活用術とCRM(顧客管理システム)を紹介!
営業の進捗・商談情報
案件ごとの進捗状況や商談履歴の情報も必要です。
- 顧客名
- 獲得チャネル
- 初回アプローチ日
- 商談日
- 提案商材
- ヒアリング事項と回答
- 受注予定金額
- 受注予定日
- 顧客の反応・宿題
このように詳細な情報を共有しておけば、マネージャーのアドバイスや周囲のフォローなどがしやすくなります。また、もしも失注してもその原因を分析しやすいため、次に活かせるでしょう。
関連記事:営業の進捗管理の方法とは?5つの管理項目と無料テンプレート
営業活動中の対応事例
顧客からの宿題やクレームなどへの対応事例も、共有するべき営業情報のひとつです。他のメンバーが同じような状況の際に参考にできるため、組織にとっても資産となります。
また、成功事例や失敗事例も共有するとよいでしょう。成功事例を参考にセールストークや提案資料を横展開できれば、組織の営業力を底上げできます。また、失敗事例を共有して原因や問題点を洗い出せば、同じ事態を二度と繰り返すこともなくなり、事前に対策を講じることが可能です。
営業情報共有に活用できるツール
営業情報の共有にはツールを使うと便利です。必要な項目にデータを入力するだけで組織内のメンバーに情報を共有でき、蓄積された情報は検索機能で簡単に探し出せます。
ここでは、営業情報の共有に便利なツールを紹介していきます。
▶︎▶︎営業の効率化ツールについて、より詳しく知りたい方はこちらの資料もご覧ください。
営業支援ツール(SFA/CRM)
営業組織に特化した営業支援ツール(SFA/CRM)は、顧客情報や案件情報、アクション情報などさまざまな営業情報の蓄積・共有ができます。案件の進捗状況や商談履歴などが顧客情報に紐づいて管理できるため、自社の営業活動が可視化され効率化や改善が見込めます。
営業支援ツール「Mazrica Sales」は、営業現場での使いやすさにこだわっているため、日々忙しい営業担当者でも手間なく営業情報の入力・共有が可能なツールです。
案件の進捗状況を直感的に把握できる案件ボード機能や、画像から文字データを認識して自動で登録するOCR機能、簡単な操作で複雑な分析ができるレポート機能など、営業現場で負荷なく利用できる機能を搭載しています。また、AIが受注予測や類似案件のレコメンドなどをしてくれる機能もあり、蓄積された営業情報を活用して戦略やネクストアクションを立案できます。
外部ツールとの連携も充実しているため、普段から利用しているツールをそのまま利用しつつ、営業活動の効率化を図れるでしょう。
関連記事:【2025年最新】SFA(営業支援)ツールおすすめ比較10選|CRM・MAとの違いも解説
DSRツール
顧客との情報共有にも活用できるのが、DSRツールです。DSRとは「デジタルセールスルーム」の略称で、顧客専用のルーム内でメッセージのやり取りや営業コンテンツの共有ができるツールを指します。
電話やメールでやり取りしなくてもDSR上で手軽にコミュニケーションを取ることができ、情報が蓄積されているため必要な情報にすぐにアクセスできるのもメリットです。もちろん営業組織内の他メンバーも情報を確認できるため、円滑な情報共有が可能になります。
具体的なDSRツールとして「Mazrica DSR」があります。顧客向けの専用ページに営業コンテンツを集約でき、Mazrica DSRでコミュニケーションを取れるため顧客の購買意欲を後押しできるでしょう。どのコンテンツをどのくらい閲覧したかといったデータも解析できるようになり、顧客の関心度をリアルタイムで把握できます。
また、社内向けにコンテンツ管理機能や商談テンプレート機能もあるため、組織内の営業ナレッジを一元管理して生産性向上を実現します。
関連記事:デジタルセールスルーム(DSR)とは?複雑化するBtoB営業プロセスに有効な情報共有の場
チャットツール
ビジネスチャットツールを活用すると、チャット形式でリアルタイムのコミュニケーションができ、手軽に情報共有ができます。チャットは電話やメールよりも即時性や利便性が高いため、意思決定もスピーディになるでしょう。
個別のチャットだけでなく、部署やチーム、プロジェクトなどのグループごとにもチャットが可能です。また、チャット機能以外にも、タスク管理機能やファイル共有機能など多彩な機能を搭載しているチャットツールもあるため、使い方次第でさまざまな情報共有に活用できます。
関連記事:ビジネスチャットツールおすすめ比較12選|失敗しない選び方を解説
グループウェアツール
グループウェアツールは、会社や部署などのグループでのコミュニケーションや情報共有を円滑にする機能が豊富です。具体的には、チャット機能やスケジュール管理機能、ストレージ機能、タスク管理機能などがグループウェア上に包括的に搭載されています。
別々のツールを導入する必要がないため、シームレスにさまざまな情報にアクセスできるのがメリットと言えるでしょう。
関連記事:【2025年】グループウェア比較15選!機能/費用/特徴を紹介
営業情報共有を効率化するポイント
営業情報の共有を始めようとしても、社内の体制やルールが整備されていないと失敗してしまうケースも少なくありません。そこで、営業情報の共有を効率化するためのポイントをお伝えします。
ルールと運用フローを明確化する
ルールと運用フローが明確でなければ「どの営業情報を共有すればよいのだろう」「どうやって伝えるべきだろう」など、無駄な時間がかかってしまい非効率です。また、必要な情報が共有されなかったり、逆に不必要な情報まで入力したりすることになり、正確な情報共有ができません。
どのタイミングでどの項目を誰に共有するのか明確に定め、効率的に情報共有しましょう。また、入力の際のルール(大文字/小文字、全角/半角など)も細かく決めておくと、重複データを防ぎ正確に分析できます。
社内の情報共有文化を醸成する
これまでずっと属人的に営業をしてきた人の中には、自分の営業情報を開示することに抵抗を感じるメンバーもいるかもしれません。そのような抵抗感や障壁となり、必要な営業情報を入力してくれなかったり、組織に対してのエンゲージメントが低下したりする場合もあります。
まずは営業情報を共有するメリットをメンバー全員に伝え、理解してもらうことが重要です。情報共有は組織をよりよくしていくための手段の一つだと意識を変えていき、社内にポジティブな文化を形成することで、営業情報の共有が促進されるでしょう。
ツールを活用し、負担を最小限にする
日々忙しい営業現場のメンバーたちは営業情報の入力や共有に負担を感じる可能性もあるため、ツールの導入をおすすめします。
Excelなどを使うと自身でフォーマットや項目を作成しなければなりませんが、営業情報の共有用ツールを活用すると必要な情報を入力するだけで済みます。スマートフォンに対応しているツールであれば出先でも入力・確認ができるため、外出の多い営業担当者にとって非常に便利です。
▶︎▶︎営業のDX化について詳しく知りたい方は、こちらの資料もご覧ください。
コストをかけすぎない
手間のかかる運用方法や入力が面倒なツールを採用してしまうと、情報共有に時間がかかりコストが高くなります。営業情報の共有によって業務効率化や生産性向上を目指していても、情報共有にかかるコストが膨大になると、費用対効果は期待できません。
そのため、コストを意識して効率的に情報共有できる方法を取り入れましょう。
まとめ|営業の情報共有は適切なツール選定と運用が成功の鍵
今までブラックボックス化していた営業情報を共有することにより、組織全体で案件の進捗状況や営業ナレッジを把握できます。その結果、フォロー体制が強化されたり、営業力が底上げされたりするため、組織の売上にもプラスに働くでしょう。
しかし、手間のかかる方法では円滑な情報共有ができず、かえって生産性を低下させる要因になりかねません。自社に適したツールの選定と、効率的に取り組める運用方法を策定し、営業情報の共有を促進しましょう。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI
資料をダウンロードする