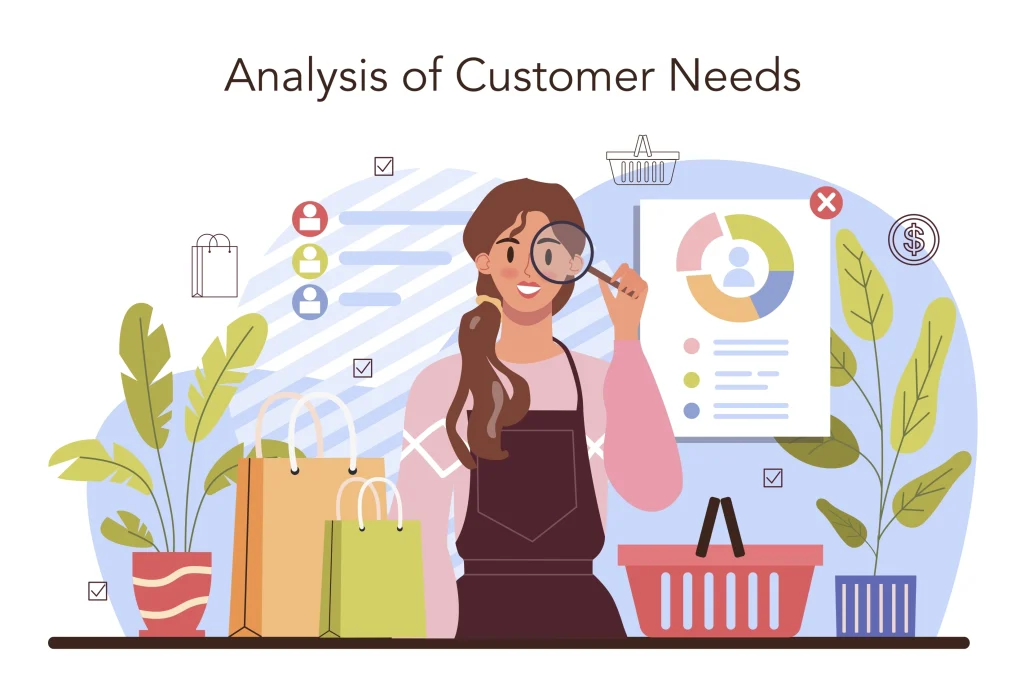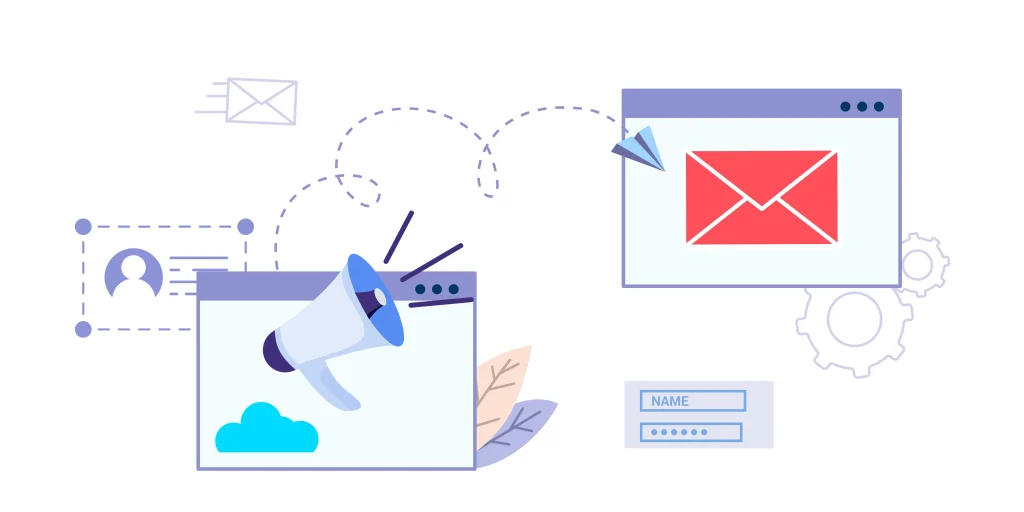近年、「パーパス(存在意義)」を軸にした経営手法が注目を集めています。企業が社会にどのような価値を提供するのかを明確にし、その目的に沿って事業活動を進める「パーパス経営」は、単なる利益追求を超えた企業のあり方として広がりを見せています。
これまでも一部の企業が取り組んでいましたが、地球環境問題や経済の不確実性が増す中で、企業の信頼性や共感を高める手法として、多くの経営者がパーパス経営に注目するようになりました。
本記事では、パーパス経営とは何か、導入によって得られるメリットや背景、そして実際の事例までをわかりやすく解説します。
企業の方向性を見直したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
※営業組織の改革にも関心がある方へ。毎期目標を達成し続ける営業組織が実践している「12の改革項目」をまとめた資料をご用意しています。あわせてご覧ください。
パス経営を導入したい人はぜひ参考にしてください。
▶︎【無料】Japan Sales Report 2024 大企業 vs スタートアップのダウンロードはこちら
この記事の内容
この記事でわかること
-
パーパス経営の基本
「企業の存在意義(パーパス)」とは何か、その定義とビジネスにおける意義を理解できます。 -
パーパスとMVVの違い
Mission・Vision・Value(MVV)との役割や視点の違いを明確に整理します。 -
注目される背景要因
SDGsやサステナビリティ、DXの進展、ミレニアル世代の価値観変化、VUCA時代の不確実性といった4つの社会的トレンドを解説します。 -
パーパス経営のメリット・デメリット
ステークホルダー支持、従業員エンゲージメント向上、イノベーション創出などのメリットと、パーパスウォッシュやKPI設定の難しさなどの注意点を整理します。 -
導入ステップ
ステークホルダー/自社分析、パーパスの言語化、日々の業務への反映という3つの実践フェーズを具体的に示します。 -
成功企業の事例
ソニーやネスレなど、実際にパーパス経営を具現化し成果を上げている企業の取り組みを紹介します。 -
組織づくり・人材育成のポイント
パーパスを浸透させるためのコミュニケーション、採用・評価制度、研修やリーダーシップの役割についてヒントをお伝えします。
パーパス経営とは?
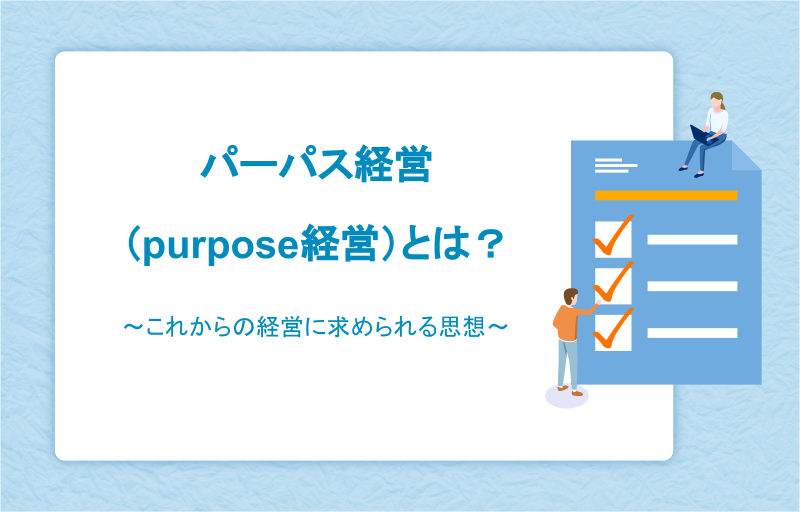
パーパス経営(purpose経営)とは、企業の経営理念として自社の存在意義を明確にして、どのように社会貢献していくのかといった「パーパス」を掲げるという意味です。
もともとpurpose(パーパス)とは「目的・意図・意思」などの意味をもち、そこから「存在意義」や「志」などの考え方に広がりました。
変動的な世界情勢や不安定な経済などを背景に、社会に対して貢献したいと考える企業が増え、自社の存在意義を明確にする「パーパス」を重視する傾向になっています。
消費者心理としても、社会的に存在価値の高い企業の商品・サービスを利用することで自身も社会に貢献できるため、パーパスを重視している企業を支持する消費者が増えています。
▶【経営層・営業マネージャ必見】パーパス実現のために、今やるべき経営改革とは?
ビジネスにおける「パーパス」とは?
ここで改めて、ビジネスにおける「パーパス」とは何かについて考えてみましょう。
ビジネスにおけるパーパスは「企業の存在意義」と解釈されます。
「存在意義」とは何かというと、その存在による価値や重要性です。つまりパーパスとは、企業が存在していることで生み出される価値だと言えるでしょう。
そのためパーパスがあれば、企業は社会のために何をすればいいのかが具体化します。人間も同じですが、自分が存在する意味がわからなければ、どのような行動をしたら良いのかもわかりませんよね。
ゆえにパーパスは企業活動の軸となるものであり、企業が社会にもたらす価値を表明するためにパーパスの提言が有効なのです。
パーパスとMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の違い
パーパスとよく混同されるのが「MVV」です。
MVVは「Mission(使命)」「Vision(未来像)」「Value(価値観)」の略で、多くの企業が経営の方針や文化を示すために用いています。
- Mission:企業の存在目的
- Vision:目指す将来像
- Value:行動や判断の基準となる価値観
MVVは自社の方向性を内向きに示す一方、パーパスは「社会にどんな価値を提供するか」という外向きの視点を持っています。
また、MVVは未来志向なのに対し、パーパスは「今こうあるべき」という現在への意識が強いのも特徴です。
両者は異なる役割を持ちつつも、現在の在り方(パーパス)が未来のビジョン(MVV)につながるという点で、相互に関係しています。
▶▶【無料ebook】パーパス実現に近づくセールス・イネーブルメントの実践方法とは?
パーパス経営が今必要な3つの理由
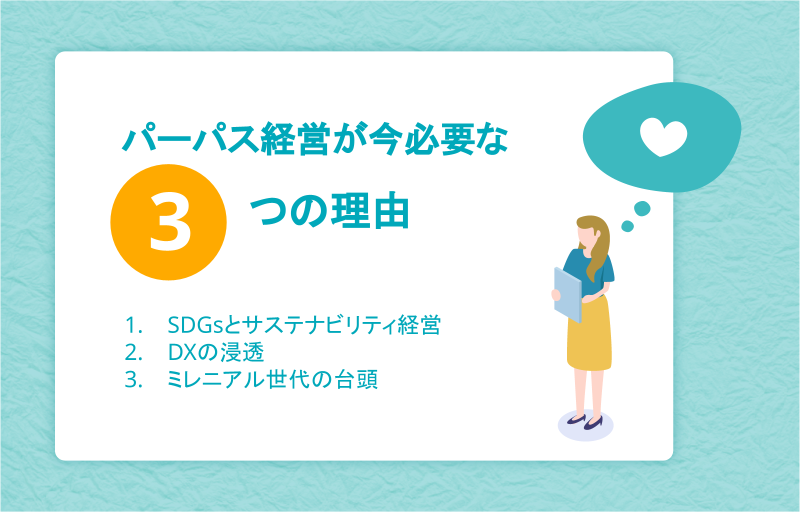
パーパス経営の波が広がっていますが、なぜ企業はパーパス経営に取り組むようになったのでしょうか。背景には、以下のような要因があります。
- SDGsとサステナビリティ経営
- DXの浸透
- ミレニアル世代の台頭
- 予測不能な時代の到来
それぞれ詳しく解説します。
1. SDGsとサステナビリティ経営
以前からパーパス経営に取り組む企業は存在していましたが、本格的に多くの企業にパーパス経営が広まったのは2010年代以降です。
パーパス経営が広がった背景には、2015年の国連サミットでのSDGs(持続可能な開発目標)採択が大きなきっかけとしてありました。
SDGsとは持続可能性=サステナビリティな社会を実現するための世界目標です。
SDGsには2030年までに達成するべき17の世界目標が設定されており、環境・社会・経済の観点での目標が定義されています。
SDGs目標の中には個人レベルの取り組みだけでなく、企業が主導して取り組むべき課題も含まれています。
また、世界的に取り組むSDGs達成に向け、日本政府は「SDGsアクションプラン2021」を設定し、具体的な方向性を示しました。
(参考:持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割|外務省)
SDGsの広がりなどを受けて、企業活動においても環境・社会・経済におけるサステナビリティを重視して、事業の持続性を向上させる「サステナビリティ経営」が注目されるようになったのです。
サステナビリティ経営を実現するためには、自社の社会的な存在意義を明確にして今後どのように取り組んでいくかを再度見直す必要があります。そこで自社の存在意義である「パーパス」の見直しが求められるようになりました。
2. DX(デジタルトランスフォーメーション)の浸透
デジタル技術を活用して事業をよりよい方向に導こうというDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が広がっています。
DXは単なる「ITツールの導入」ではなく、ITツールを導入することによる企業の「変革」や「改善」を目的とする取り組みです。
関連記事:DX戦略とは?戦略立案・推進のポイントとDX化の成功事例を紹介!
ところが、現実にはIT導入のみで満足してしまい、その先にある変革まで進めていない企業が多いことも事実。理由として、組織全体がDX推進に対して足並みが揃っていないことに原因があると考えられます。
今一度「なぜ自社がDX化をするのか」というDX化の目的を振り返り、自社の在り方や社会に対する貢献の仕方、つまりパーパスについて見直さなければいけないのです。
▶▶【無料ebook】パーパス経営導入の土台に。営業DXの始め方・便利ツールをご紹介
3. ミレニアル世代の台頭
パーパス経営が広がった背景には、ミレニアル世代の台頭もあります。
ミレニアル世代とは1980年代~1990年代半ばに誕生した人たちを指し、今後の企業活動や消費行動の軸となる世代です。
ミレニアル世代は幼い頃にバブル崩壊を経験しており、経済情勢が厳しい日本で育った世代です。
そのため、ミレニアル世代は「社会に貢献したい」という強い気持ちをもっているという特徴があります。
つまり、自分たちの存在意義であるパーパスを確実に理解して事業に取り組んでいる企業ほど、ミレニアル世代の共感を得られるのです。
これからの時代の社会を担うミレニアル世代の支持は、企業の成長に欠かせない要素となるでしょう。
関連記事:ミレニアル世代・Z世代の違いとは?購買活動の特徴を解説
4. 予測不能な時代の到来
技術革新や予測不能な事態が相次ぐ現代、企業には「変化に左右されない明確な指針」が求められています。
こうした不確実性の高い時代は「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」と呼ばれ、従来の経験や計画だけでは対応が困難です。
その中で注目されているのが、企業の存在意義=パーパスを軸とする経営です。パーパスを明確にすることで、経営層から従業員、株主、取引先まで方向性を共有でき、判断や行動の一貫性が生まれます。
パーパス経営はスローガンではなく、組織がぶれずに進むための実践的な指針として、その重要性が再認識されています。
関連記事:ミVUCA(ブーカ)の時代に必要な営業スキルとは?|混沌の中のサバイバル術
パーパス経営の3つのメリット
パーパス経営を行うことで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。具体的に3つのメリットについて解説します。
- ステークホルダーから支持される
- 従業員のエンゲージメントが高まる
- 革新や変化を生み出す
順番に見ていきましょう。
1. ステークホルダーから支持される
パーパスに対して実直に取り組んでいる企業は、信頼できる印象を与えます。消費者や株主など企業のステークホルダーが、パーパスに共感して支持してくれるようになるでしょう。
誰しも、自分が共感する企業を応援したいと思うのは当然のこと。パーパスに共感し応援してくれるステークホルダーが増えるほどブランディング効果も高まり、成長にもつながります。
2. 従業員のエンゲージメントが高まる
パーパスの設定は、自社の従業員のエンゲージメント向上にも役立ちます。
パーパスが定まっていないと従業員は「私は何のために働いているのだろう」と思ってしまい、モチベーションが低下します。
しかしパーパスがあれば仕事における自分の存在意義が明確になるため、従業員のモチベーションが向上してエンゲージメントが高まります。
エンゲージメントが高まれば従業員のパフォーマンスも向上し、企業の成長にもつながるでしょう。
従業員エンゲージメントの重要性については以下の記事でも解説しています。
関連記事:エンゲージメントとは?ビジネス上の意味・重要性・向上させる方法を解説
3. 革新や変化を生み出す
企業のパーパスがあれば、従業員も同じ方向性に足並みをそろえられます。自分たちが何のために仕事をして何を実現するのかが明確になっているので、パーパス実現のために何を生み出すべきか定まります。
また従業員全員が同じ方向に向かえば組織の一体感が生まれ、アイデアを出し合ったり他の人の意見を受け入れたりできるようになるでしょう。
こうして今の自社に必要なものが明確になるので、革新や変化を生み出し企業のさらなる成長が実現するのです。
革新や変化とは、新商品の開発、既存サービスの改良、業務フロー改善、ビジネスモデルの変更など多岐にわたります。革新や変化の実現により、時代の変化に負けない柔軟で骨のある企業へと成長するでしょう。
▶▶【無料PDF】営業組織が生まれ変わる「セールスイネーブルメント」とは?
パーパス経営のデメリット
パーパス経営のデメリットとして、実際の企業行動がパーパスに合わないパーパスウォッシュにつながる可能性があります。
これにより、従業員は自分の仕事から切り離されていると感じ、最善を尽くす意欲を感じなくなる可能性があります。
また、成功の明確な指標がないため、企業がパーパス イニシアチブの成功を測定することも困難な場合があります。
パーパスの実現が難しく感じる場合には、パーパスを実現するための具体的な数値指標を立てると良いでしょう。
関連記事:KPIマネジメントとは?KPIの設定方法とマネジメント事例を解説
パーパス経営の実践手順3ステップ
実際にパーパス経営に取り組む手順は、以下の3ステップです。
- ステークホルダーと自社の分析をする
- パーパスを言語化する
- 運営に反映させ業務にあたる
順番に解説します。
1. ステークホルダーと自社の分析をする
【ステークホルダーの調査項目】
- 顧客情報
- 仕入れ先情報
- IR情報
- CSR・SR など
【自社分析方法】
- 3C分析
- SWOT分析
- コンピテンシー分析 など
まずは、どのような顧客・従業員がいて、評価はどうなっているか確かめましょう。また、自社商品はどういったブランドを確立しているか分析することで、パーパスを考えやすくなります。
2. パーパスを言語化する
分析をし終わったら、自社があるべき姿を言語化していきます。言語化したら従業員に周知して、会社全体で同じ方向を向くようにしましょう。
パーパスだけでなく、パーパス設定に至った背景も伝えると従業員が理解しやすく、共感してもらいやすいです。
3. 運営に反映させ業務にあたる
パーパスを策定したら、事業運営に反映させていきます。これにより、一貫性のある経営を行えます。
そして、パーパスに基づいて経営戦略や立案を行っていきましょう。戦略立案が終わったら、それを日々の業務に落とし込んでいきます。
従業員がパーパスについて深く理解できるよう、機会や時間を確保することも大切です。
▶【無料ebook】パーパス経営を実現するための経営改革の基盤を徹底解説します!
パーパス経営で求められる5つの条件
パーパス経営で求められる条件は、以下の5つです。
- 自社で実現できるか
- 自社の利益を確保できるか
- 自社の事業内容と関連性はあるか
- 社会の課題を解決できるか
- 従業員のモチベーションを保てるか
順番に解説します。
1. 自社で実現できるか
パーパスを実現するために、他社の力が必要となると実現が難しいです。
労働力や資金面などから、自社のリソースで実現できるかを考えるようにしましょう。
2. 自社の利益を確保できるか
社会貢献をしている事業であっても、利益がなければ存続はできません。パーパス経営はボランティアではなく事業であり、業績が落ちるようでは継続は困難です。
初期費用がかかる場合は、コストをシミュレーションしたうえで実現できるか検討してみてください。
3. 自社の事業内容と関連性はあるか
自社の事業と全く関係のない内容であれば、相乗効果が見込めません。
ノウハウや経験がないため成果につながりにくく、利益を損ねることにもつながりかねないでしょう。
4. 社会の課題を解決できるか
パーパス経営は自社の存在意義を明確にするものであるため、社会にどう貢献できるか検討する必要があります。
自社のサービスや理念で、どうやったら社会に対して良い影響を与えられるか考えましょう。
環境問題、人権、労働環境など、解決すべき課題は山積みです。
5. 従業員のモチベーションを保てるか
従業員がやりがいを持って業務に当たらなければ、会社の業績は上がりません。一人ひとりが主体性を持って取り組める環境を作る必要があります。
そのためにも、自社の目的や社会に貢献していることを周知しましょう。
関連記事:モチベーション管理とは?仕事のモチベーションが下がる理由と維持する方法
パーパス経営を成功させる企業の特徴とは?
パーパス経営を成功させる企業は、単に「目的」を掲げるだけでなく、それを経営戦略として体系的に実行に移し、社会的な影響力を持つ存在となっています。成功する企業には共通する特徴があります。以下にその特徴をいくつか挙げてみましょう。
1. 経営層の強いコミットメント
パーパス経営を成功させるためには、経営陣がその理念に対して強いコミットメントを持ち、積極的に推進していることが不可欠です。特に経営層が自身の行動でパーパスに従う姿勢を示すことが重要です。経営陣の言葉と行動が一致して初めて、組織全体にパーパスが浸透します。
2. パーパスを企業文化として根付かせる
成功する企業では、パーパスが単なるスローガンに留まらず、企業文化の一部となっています。パーパスは従業員の日々の仕事において意思決定の指針となり、行動の背後にある価値観を明確にする役割を果たします。そのため、全社員がパーパスを深く理解し、共有することが重要です。
3. 社会的インパクトに焦点を当てた戦略
パーパス経営を掲げる企業は、社会課題への貢献を事業戦略に組み込んでいます。具体的には、製品やサービスの提供を通じて、SDGs(持続可能な開発目標)や環境問題、貧困撲滅など、社会的課題にどのように貢献するかを明確にしています。こうした企業は、利益だけでなく、社会的なインパクトを重視しています。
4. 透明性と誠実さを重んじる
パーパス経営を実践している企業は、外部と内部に対して透明性を持ち、誠実な活動を行います。パーパスを掲げる企業が評価されるのは、その活動が信頼できるものであると認識されているからです。したがって、企業は積極的にその活動内容や進捗を開示し、社会に対する責任を果たす姿勢を見せることが求められます。
5. 従業員のエンゲージメントを重視
パーパス経営を成功させる企業は、従業員のエンゲージメントを重視します。企業が掲げるパーパスが従業員一人ひとりのモチベーションと直結するため、従業員がその目的に共感し、自分の役割を感じることが重要です。高いエンゲージメントが得られると、業務に対する熱意やパフォーマンスの向上が期待できます。
パーパス経営を実現する組織づくり・人材育成のヒント
パーパス経営を実現するためには、単に目的を掲げるだけでは不十分です。それを実行に移し、組織全体で浸透させるための仕組みや人材育成が必要です。以下に、パーパス経営を支える組織づくりと人材育成のヒントを紹介します。
1. パーパスを共有するコミュニケーションの強化
パーパス経営が成功するためには、全社員が共通の目的に向かって進む必要があります。そのためには、パーパスを定期的にコミュニケーションし、従業員に浸透させることが不可欠です。全社員向けのワークショップや社内イベントを通じて、パーパスの重要性を繰り返し伝えると効果的です。また、リーダーシップチームが率先してそのメッセージを発信することが求められます。
2. パーパスを軸にした人材採用と評価制度
パーパス経営を実現するためには、採用プロセスにおいてもパーパスに共感できる人材を選ぶことが重要です。採用基準に「パーパスへの共感」や「社会的価値の提供」に対する意欲を加えることで、組織に適合した人材を集めることができます。また、社員評価の軸をパーパスの実現度にリンクさせることで、日々の業務においてパーパスが重要な指標となります。
3. フラットな組織構造でエンゲージメントを高める
パーパス経営を推進するには、従業員のエンゲージメントを高めるための組織文化が必要です。フラットな組織構造は、従業員同士のコミュニケーションを促進し、意見やアイデアを自由に交換できる環境を作ります。エンゲージメントが高まることで、従業員はパーパスに対して強い共感を持ち、その実現に向けて積極的に行動するようになります。
4. 継続的な学びと成長の機会を提供
パーパス経営を実現するためには、従業員に継続的な学びの機会を提供し、個々の成長を支援することが重要です。例えば、パーパスに関連するスキルや知識を学べる研修プログラムや、社会的課題に対する理解を深める勉強会を実施することが有効です。こうした取り組みによって、従業員はパーパス経営に積極的に関わり、その実現に貢献する意識が高まります。
5. リーダーシップによる模範的な行動
パーパス経営の実現には、リーダーシップが欠かせません。企業のリーダーは、自らがパーパスに基づいた行動を示すことで、従業員に対して模範を示すことが求められます。例えば、企業の社会的責任を果たす活動に積極的に参加したり、社会貢献に関するプロジェクトを立ち上げたりすることが、社員の意識を高めます。
パーパス経営に成功している企業事例
パーパス経営に取り組む企業は増加傾向にあります。ここでは、特に著名な事例としてソニーとネスレのパーパス経営を紹介します。
ソニー|2019年に自社のパーパスを発表
ソニーは2019年に「Sony’s Purpose & Values」にて自社のパーパスを発表しました。ソニーのパーパスは以下の内容です。
クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。
(引用:Sony’s Purpose & Values)
コロナ禍になり社員たちは従来のような円滑な仕事が困難になったなかでも、パーパスの策定により社員の意識が統一されて足並みがそろっていました。
あらゆる制約が増えてストレスを抱えている消費者を喜ばせようと、プレイステーション5の発売や「鬼滅の刃 無限列車編」の映画公開などに尽力したのです。
その結果、2020年度はコロナ禍でありながら過去最高益を出しました。
また新型コロナウイルスの影響を受けている世界中の人を支援するため、2020年4月には「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を設立。
支援対象は医療関連や教育関連だけでなく、コンサートの中止や映画・テレビ番組の制作中断などで大きな影響を受けているクリエイティブコミュニティも対象としました。
ソニーの取り組みは社会的貢献度が高く、同社のパーパスを具現化したと言えるでしょう。
ネスレ|会社の存在意義としてのパーパスを掲げる
ネスレもパーパス経営をしている企業です。同社のパーパスは以下の内容です。
ネスレは、食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます。
(引用:ネスレの存在意義)
ネスレは上記のパーパスに則り、SDGsを達成するための以下の目標も掲げています。
- 5,000万人の子どもたちがさらに健康な生活を送れるように支援
- ネスレの事業活動に直結するコミュニティに暮らす3,000万人の生活を改善
- ネスレの事業活動における環境負荷ゼロ
(引用:ネスレ、「持続可能な開発目標」を支援する2020年のコミットメントと長期的目標を発表」)
このようにネスレはパーパスを動機にし、食を通じて社会が持続可能になるような取り組みを定めています。
▶【無料PDF】毎期目標達成するトップセールスの4つの法則を徹底解説!
パーパス経営が学べるおすすめ本
ここまでパーパス経営に関する詳細をお伝えしてきましたが、最後にパーパス経営について学べる書籍を紹介しておきます。
書籍の中には「パーパスマネジメント」「パーパスデザイン」「パーパスドリブンな組織の作り方」など、様々な本が出ていますが、今回ご紹介するのは「パーパス経営」ど真ん中の書籍「パーパス経営: 30年先の視点から現在を捉える」です。
パーパス経営: 30年先の視点から現在を捉える
名和 高司(著)/2021年4月21日発売/ISBN-10 : 4492534369 ISBN-13 : 978-4492534366
2021年に出版された508ページに渡るパーパス経営のバイブル。
一橋大学ビジネススクール客員教授の名和 高司氏によって書き下ろされた書籍です。
本書では、Purpose(目的、存在意義)を「志」と置き換えて、心の内側から湧き出てくる強い思いを持って企業経営を推進して欲しいという著者のメッセージが込められています。
一過性のバズワードではなく、時代を超えた企業経営の軸に据える必要がある「パーパス経営」。
本書はボリュームが多く、全てを読み切るのは困難かもしれません。一度読んだだけでは、内容を理解するのが難しいかもしれませんが、ポイントを絞り何度も読み返す価値のある書籍となっています。
まとめ|パーパス実現のための人材育成~トップセールスの4つの法則〜
社会情勢の変化や価値観の多様化が進む中、企業が持続可能な成長を遂げるには、自社の「存在意義=パーパス」を明確にすることが重要です。
パーパスが定まることで、企業の進むべき方向が明らかになり、社会的な貢献へとつながります。
いまこそ、自社の在り方を見直し、パーパス実現に向けた人材育成に取り組むことが求められています。